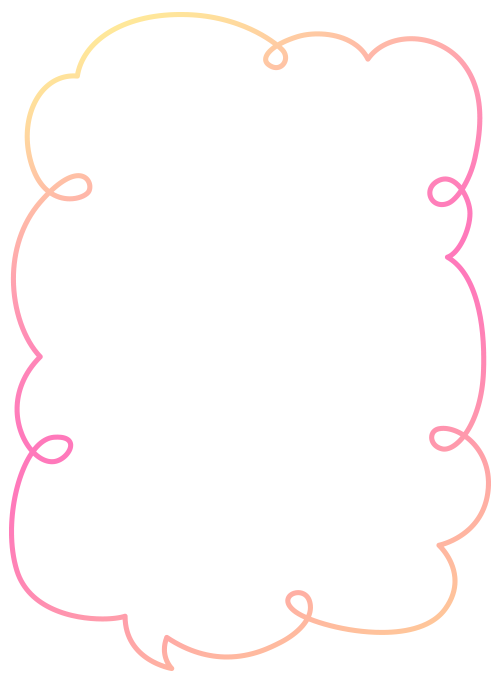夜も深まり始めた頃、私は自室でノルマの手紙に封蝋を押す。
今回は書くことがたくさんあって良かった。
アトル様方に城下を案内し、概ね好評だったこと。うちの屋敷で陸の料理を振る舞ったら、少々味付けが濃いと言われたが、食べられないほどではないとのこと。海では甘味があまりないらしく、デザートのケーキが特に喜ばれたこと。そして時間も遅くなったので、今晩はお二人が我が家に泊まっていくことになったということ。
リカ様に送った手紙は、ミハエル様にも読まれ、その内容は国王陛下にも伝わっていると宰相のお父様談。つまり、この手紙はリカ様のご機嫌とりと、人魚交流の定期報告を兼ねている。正式な報告はお父様がしているのだろう。だが、あくまで私本人からの進捗順調な報告に、陛下共々ひと安心しているらしい。過去の婚約破棄に遺恨を残していない――と。
「はあ」
私はため息を零し、手紙を机の脇に寄せた。代わりに出すのは、束ねた紙束。辞書並みの厚さになってしまっているそれを捲って、私は再びペンにインクを付けた。
その時だ。
「今度は何を書くのかな?」
「ひゃぁっ」
突如背後から聞こえた声に、私は肩を上げる。振り返れば、うちが用意した寝間着に着替えたアトル様。お風呂に入ったばかりなのだろう。濡れた髪を下ろし、肩が濡れてしまっている。ランプの明かりでいつもより赤みを帯びた艷やかな長い髪。顔に這うそれを気にすることなく小首を傾げた様が、いつもより大人びて見える。
爆ぜる胸をなんとか押さえつけて、私は極力平然な声を出した。
「ど、どうして……いや、どうやってここに?」
扉が開いた様子もないし、そもそも来客があれば気づかないはずがない。見渡せないほど広い部屋というわけでもないし、ベッドとクローゼットとサイドテーブルに椅子が置いてあるくらいの、シンプルな部屋なのだから。しいていえば、テーブルの上に積まれた本が少し多いくらい。
私は書いていた紙束を本の下に隠し、無理やり笑顔を作る。
アトル様は少し気まずそうにこめかみを掻いた。
「驚かせてごめんなさい。魔法で転移してきたんだ」
「てんい?」
「瞬間移動というか……近距離なら、いきなり好きな場所に現れることが出来るというか」
「本当に、魔法ってすごいですね……」
「まぁ、さすがにこんなこと出来るのは僕だけみたい、かな」
アトル様はまるで悪いことのように言っているけれど、すごいことなのでは?
だけど、アトル様はすぐに机の上を覗き込む。
「本がたくさんだね。ヴェロニカ様も本が好きなの?」
「えぇ、まぁ……」
「図書館でも本を探していたもんね。どんな本を……」
彼が一冊取る手を、私は止めることが出来なかった。ああ……だめ。それは、特にだめなやつ……。
案の定、アトル様は表題を見て顔をしかめる。
「『死体の有効活用案』? え、こっちは『歴代の悪女』? 『世界の毒物』? これは『素敵たのしい拷問術』?」
「資料です! 小説書くための資料です! 断じてそういう趣向があるとか、あまつさえアトル様に危害を加えようというわけではございませんので何卒っ‼」
「あ、うん……大丈夫かな。きみに殺意を抱かれたところで、稚魚に鱗を剥がされそうになるみたいなものだし」
稚魚……つまり子供みたいなものってことですよね? それはそれで、なんとも馬鹿にされているような気もしますが……とりあえず誤解はされていないようで、安堵の息を吐く。
だけど、そうは問屋が卸さなかった。
「ヴェロニカ様って小説書くの?」
あ、なんかアトル様の目がキラキラしている。すごく興味持たれちゃったやつだ。これは根掘り葉掘り聞かれてしまうやつ。
「……そ、そんなことより、どうしてアトル様が私の部屋に?」
「マルスコーイに、『一つ屋根の下にいながら婚約者を独り寝させるのはマナー違反』て言われたから。そんなことより――」
そんなことじゃないです! とても大きな間違いを教えられていますよアトル様⁉
あの教育係……今頃あのギザギザを歯をにんまりと見せているのが簡単に想像つくわ。そもそも正式な婚約もまだ結んではございませんが⁉
「それならば、どうしてわざわざ魔法なんかでいらっしゃったのです? それも海のマナーなのですか?」
「……それは婚姻前だし、廊下にはメイドさんとかもいたからお義父さんにもすぐ伝わるだろうし、さすがにヴェロニカ様も気まずいかなって。でもそんなことより――」
「あ、そうそう。アトル様も私のことを愛称で呼んでくださいね。私だけアトル様と愛称でお呼びしてしまい申し訳ありませんでした。これからはお互い愛称で呼び合って二人の距離を――」
縮めていきませんか? だからお願い。今日のところはこのまま帰って。
度重なる「そんなことより」攻撃を躱そうと奮闘する私に対して、
「……ニカ」
アトル様は私越しに机に手を置く。だからまるで、座ったままの私は覆いかぶされるようで。距離が近い。その湯上がりの少し上気した肌が、濡れた金糸が、真剣な男らしい瞳が、見れない。アトル様の息遣いを肌で感じる。
アトル様が机から私が隠した紙束を取り出した。呆然とする私をよそに、それをパラパラと捲る。
な……なな……どこで覚えてきたんですか、そんな技っ⁉
私が目をパチクリさせていると、視線に気が付いたアトル様がこちらを見る。
「あれ、ニカ。どうしたかな?」
「ど、どうしたって……」
「『ヴェロニカ』の愛称って、『ニカ』で合っているよね? あ、それとも実際に呼ばれてみて嫌だって思ったかな。それだったら僕は今まで通り『ヴェロニカ様』と呼ぶよ。でも『アトル』て呼ばれるのは好きだから、ヴェロニカ様は今まで通り呼んでほしいかな」
「それは……大丈夫です……」
本当はそれも大丈夫じゃないです! ニカって……いきなり呼び捨てって……。ミハエル様にも、呼ばれたことなかったのに。
子供の頃は、お互い愛称で呼び合っていたのだけど。でも、お互い立場あっての付き合いだったから。大人になってからはかえって距離感を縮められずに、いつしか正式名で呼ぶ仲になっていた。
だけど、正式な夫婦になったらまた『ミーシャ』と呼んでみたいと思っていたっけ。そして『ニカ』と呼ばれることを夢見ていた時もあったっけ……。
「なら良かった」
アトル様のふにゃっと緩んだ笑みが、私の重たい胸のつっかりをスッと取り除く。
だけど、彼が再び視線を落とした物は――、
「て、そんな場合じゃありません! 返してください、それ!」
「あ、結構これ本格的な小説だね……本当にニカが書いたの?」
「そ、そうですが……」
ああああああああ、バレてしまった! 誰にも見せたことも、話したことも、言ったこともないのに! だってそうでしょう? いい歳した女が夜な夜な空想を紙に綴っているなんて、そんな子供じみたことをどうして人に言えようもんですか。しかも女性らしい恋愛小説ではなく、女主人公の英雄譚ですよ。勇者の娘が父の威光を越えようと一人世界を冒険するお話ですよ。たまに男性キャラと恋愛じみた展開になりますけど……だけど男よりも冒険を優先させるようなお粗末な物語ですよ⁉ 文字を覚え始めた子供の時から、一人で少しずつ書き足して言った独りよがりの夢物語ですよっ!
パラパラと、アトル様はページを捲っていく。そしてボソリと呟いた。
「おもしろい……」
「え?」
「おもしろいよ、ニカ! これ公表してないの?」
「わ、私が一人で書いているだけの駄作ですが……」
「もったいないっ! こんなおもしろい小説、始めて読んだ! これ読んでいい?」
いや、もうすでに許可なく読んでおりますよね……?
そんな指摘する気も起きず、思わず「どうぞ」と告げると、アトル様は顔をぱあっと晴れやかにした。
「ありがとう! あ、ニカは先に寝ていいからね。僕勝手に読んでいるだけだから。でも出来たらこの前の部分も出してくれると嬉しいかな。どうせなら始めから読みたい」
「か、かしこまりました……」
私がクローゼットの奥に隠していた紙束五冊を出してくると、アトル様は無邪気な子供のように喜んでくれて。私が座っていた書斎机を明け渡すと、遠慮なく座って読みふけっている。
私が「おやすみなさい」とベッドに入っても、彼は「おやすみ」と返事を返すだけで一視もくれなかった。
そして温かい布団に包まれた私は、いつしか睡魔に負けて。
それでも睡眠が浅かったのか、カーテンから漏れる朝陽が眩しくて、私は目を覚ます。
アトル様は寝る前と変わらない姿勢で、紙束を読み続けていた。一晩中、彼はベッドの令嬢を無視して本に夢中だったというの……?
その真剣で楽しそうな横顔をぼんやりと見つめて、思った。
もちろん嬉しい。初めての読者が、こんなにも熱中してくれているのだもの。書いてて良かった。今までの不毛だと思っていてもやめられなかった時間が、報われた。
だけど乙女……淑女の寝室での一夜の過ごし方として、これは如何なものなのでしょう。
――この複雑な気持ちのやり場を、どうしろと⁉
拝啓、親愛なるリカ=タチバナ様
私の見合い相手は、とても紳士的な御方のようです。
ですが……紳士の言葉の定義が、どうもわからなくなってきました。