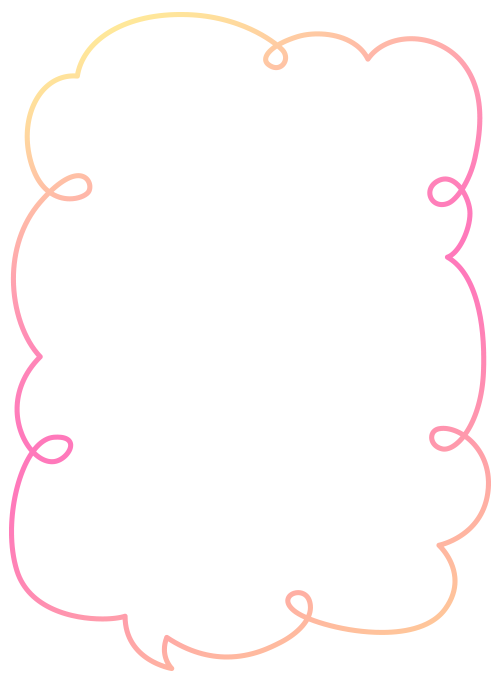さて、マルス様ばかり楽しませても仕方ない。私の見合い相手はアトル様なのだから。
「アトル様、このあと行きたい所はありますか?」
「あ、どこでも……いい、かな」
「何かお好きなものとかは?」
「特に……」
困った。本当は馬車で案内したいところだが、こうも煮え切らないとどこへ向かえばいいのかわからない。海の人だし、男の子だし。自ら案内してほしいと頼んできたくらいだから、行きたい所に連れて行ってあげようとノープランだった過去の私を呪いたい。
仕方無しに、商店街を散策してみることにした。
あれが王族御用達の靴屋。あれが騎士御用達の武器屋。あれが最近噂の化粧品屋。マルス様はちょいちょい「ちょっと見ていきましょうか!」と興味を示してくれるものの、アトル様はあまり関心のない様子。
そして行き着いた先は、貴族図書館だった。ある程度の身分がないと利用出来ない書庫は、王室に負けないくらいの書物が貯蔵されている。正式な手続きを踏めば、一定期間借りることも可能。無論、どれだけ本を所持しているかでその貴族の格の証明になる時代もあった。それでも世界中の本を集めることは不可能に近いし、読まない本を持つことは無駄な行為。瘴気戦争で多くのものを失ってしまったからこそ、今では本を共有することで効率的に知識を集めることこそ、重宝されている考え方。
そうして最近出来た貴族図書館に足を踏み入れるのは、私も初めてだった。興味はあったけど、ずっと忙しかったしね。お見合いで。
高い天井いっぱいまで伸びた本棚は圧巻。心なしか目が輝いているアトル様に、私はそっと胸を撫で下ろす。
「それじゃあ、アタシはあっち見てくるわ!」
やっぱり自由に散策を始めてしまったマルス様はおいておいて。
「アトル様はどんな本にご興味ありますか?」
「じゃあ……歴史書を……」
「こちらみたいですね」
案内板を見ながら棚に向かえば、アトル様はさっそく興味ある本を見つけたようだ。「借りたい本がありましたら教えてください」と声をかけ、私も興味ある本を探す。アトル様たちとお見合いする前に海や人魚にまつわる本をメイドに借りてきてもらおうと思ったことがあったのだけど、収穫は子供向けの絵本だけだった。
いざ自分で探しても……やっぱり見当たらないわね。仕方ないわ、暇つぶしに面白そうな空想小説でも。恋愛小説は趣味じゃないのよね、冒険譚的なものはないかしら……?
束の間の一人時間に油断していた時、
「ヴェロニカ様は本がお好きなのですか?」
後ろから突如話しかけられて、私は肩を上げてしまった。振り返れば、一冊の本を抱えたアトル様。
「あ、その本借りて行かれますか?」
「え、あ……はい。お願いしたいです」
「では、少々お待ち下さいね」
私がその本を預かり、受付に手続きをしに向かう。無事に手続きを終えれば、アトル様は入り口の長いソファにちょこんと座っていた。
「お待たせいたしました。マルス様は?」
「あ、まだ見たい本があるそうです」
今までの話しぶりからして、二人とも勤勉ねぇ。
「それなら、お隣失礼してもよろしいですか?」
話して待とうと声をかけると、アトル様が「はい、もちろん!」と慌てて座り直す。その可愛さに顔が緩まないように堪えつつ、私はワンピースを整えながら隣に失礼した。
「アトル様は……海でどのようにお過ごしだったんですか?」
私の世間話に、アトル様はゆっくりと首を傾げる。
「特に……本を読んでいたくらい、かな」
「読書がご趣味なのですか?」
「趣味ってほどじゃ……僕は、勉強しか取り柄がないから……」
ああああああ、そんなしょんぼりしないで!
どうにか話を盛り上げようと話題を探していると、アトル様が顔を上げる。
「お気遣いありがとうございます。でも僕、ちゃんと今日も楽しんでますよ。陸のことは本で色々読んだけど……やっぱり実際に見ると、全然ちがうかな」
にこりと微笑んだアトル様が、外へ出ていこうとする。慌てて私が追いかけると、彼は空を仰ぎ見ていた。
「それに、空がとても綺麗だ」
今日は特別いい天気というわけではない。雲が少し厚くて、だけど雲間から太陽は見えて。暑くもなく、寒くもない。
それを満足げに見上げては、今後は下を見る。灰色の石畳。埋め込まれた石の一つ一つの色が当然異なるから、何とも言えない色合いを造り出している。そんな地面を何度か踏みしめて、アトル様が聞いてきた。
「その細い靴で、歩き辛くないのかな?」
私が履いているのは、当然ハイヒールだ。アトル様は底の薄い革靴。甲の部分は紐で編み上げる、街で見かけるどうってことないもの。
確かに、社交界に入る前はヒールが石畳の間に入って抜けなくなってしまったこともあったが――そんな少女時代は、遠い昔。
「もう慣れましたよ。今度アトル様も履いてみますか? けっこう変な場所の筋肉使うんですよ」
「ぜひお願いします!」
私の冗談に、アトル様は満面の笑みで乗ってくる。可愛い。
うん、今度それとなくドレスを着せてみよう。そんな野望をこっそり胸に秘めた時だった。
「危ないっ!」
アトル様が叫ぶ。 え? と思ったのと同時に、ズバッと脳天に圧力を感じた。だけど、それはさほど痛くなかった。中腰になった私は、誰かに無理やり頭から抱きかかえられているらしい。その誰かとは誰なのか――少し視線を上げればすぐにわかった。アトル様がとっさに私を守ってくれたのだ。
それでも、全身はびしょびしょ。私は後頭部や背中が濡れてしまったくらいだが、アトル様は頭の先からつま先までずぶ濡れ。それでも、彼の顔は天へ向いていた。私も習って見上げると、くすくすとした笑い声が聞こえる。その主は、図書館の二階の窓から私たちを見下していた。
「あらぁ、あれは『元』王太子婚約者のヴェロニカ様ではございませんか?」
「ふふ、まさかぁ。あのヴェロニカ様ともあろう御方が、こんな場所で庶民とデートなんでねぇ。貴族の誇りを捨てたわけじゃああるまいし」
「まぁ、王太子に捨てられた令嬢なんて、あとは落ちるだけではございませんか。行き遅れた身体を売って少しでも家に財を残そうとするなんて、とても健気だと思いませんか?」
あぁ、なるほど。たまにいるのよね。昔私を恨んでいた令嬢が、ここぞとばかりに悪戯してくるの。別に当時も彼女たちに何かした覚えはないのだけど……まぁ、あの王太子ミハエル殿下の婚約者というだけで、目の上のたんこぶだったのだろう。
言っていることも下賤な憶測。貴族の誇りを捨てているのは、どちらの方かしら――と、何か言うだけ無駄ね。
そう思って、私はアトル様を連れて早々立ち去ろうとしたのだけど、
「デュフフフフフ……」
アトル様は笑っていた。あの気持ち悪い笑い方で。ギザギザの歯を覗かせて。
「アトル……様?」
「デュフフ……あぁ、ヴェロニカ様。すぐ乾かすね」
ぱちんっと、アトル様が指を鳴らした途端、ふわっと温かい風が私のまわりを踊る。風が通り過ぎて行ったかと思えば、私の髪や服はもう乾いていた。
「寒くないかな?」
「え、あ、はい……」
アトル様が私の赤い髪を一筋手に取り、にこりと微笑んでくる。あ、これは普段の可愛い顔。だけど、私が頷くと、またすぐに尖った歯を見せた。
「デュフフ、それじゃあ少し待っててね」
そして、アトル様は飛ぶ。飛ぶ――飛ぶっ⁉
ふわっとアトル様が舞い上がり、見上げる私からは彼の靴の裏が見える。濡れた彼から、ポタポタと雫が落ちていた。
彼は令嬢たちのいる二階の窓の前まで上がると、彼は張り付いた金の前髪を払ってから片手を胸に当て、立派な男性貴族のお辞儀を披露する。
「はじめまして。レイチェル=ジルコン氏。アナスタシア=クオーツ氏」
彼は名前、家名共に完璧に言い当て――おそらく、ニヤリと笑ったのだと思う。
「いやぁ、本当に綺麗な人たちですなぁ。ドレスの下の軟らかそうな肌に歯を立てるのを想像するだけでヨダレが落ちそうでござるよ。その可憐な笑顔が笑い声が悲鳴に変わる瞬間なんて想像するだけでゾクゾクする。拙者はもう我慢たまらずBダッシュで駆け寄って左右左Aを決め込み――」
あ、逃げた。
本当に絶叫をあげた青い顔の令嬢たちは、我先にと窓から離れていった。「幽霊だ!」「おばけだ!」「魔物だ!」「呪われる!」等々、男性の声も混じっているから、令嬢に協力した執事などもいたのだろう。もしかしたら、まったく関係ない図書館員かもしれないけど……これでもかと恐怖におののく言葉が、どんどん遠ざかっていく。
「まだまだこれからだったのに……」
それに、なぜかしょんぼりした様子で、アトル様は下りてくる。とんっと地面に足を下ろすと、彼は視線を所在なさげに動かしてモジモジしていた。
「穏便にね……解決してみたんだけど、どうだったかな? ほら、あの喋り方陸だと煽っているみたいに聞こえるんでしょ? 穏便にやり過ごすにはちょうどいいかなって思ったんだけど」
穏便とは?
あの令嬢たち死ぬ寸前みたいな顔をしていた気がしたけど、穏便とは?
「……空、飛べるのですね」
思わず見当違いの質問をする私に、アトル様は苦笑した。
「うん。魔法かな。陸ではなるべく使わないようにしているんだけど……」
「そうですね。今はあまり目立ちすぎない方がいいと思われるので……あと今後、同じようなことがあっても今みたいなことはやめていただければ――」
「どうして?」
純粋な目で、アトル様が首を傾げている。
どうして――貴族間でトラブルを起こさないに越したことはないじゃない。それに、アトル様は人魚で、異種族。国王の許可の元こうしてお見合いさせていただいているけれど、他貴族や国民に受けいられるか定かではないのだから。こんな嫌がらせは大したことないのだし、放っておけばいいこと。どうしても我慢ならなくなったら、しっかり裏付けをとって、正式に『スーフェン家』として抗議すればいい。
それなのに、アトル様は無垢に疑問を重ねてくる。
「ヴェロニカ様は水をかけられて、嫌じゃなかったのかな?」
「それは……」
「僕は嫌だったよ。ヴェロニカ様が事実じゃないことで愚弄されるだなんて。馬鹿にされても黙っているのが、陸の『いい男』なのかな?」
「そんなことは……ないかと」
「でしょう? それに……あいつらの逃げていく時の顔、ちょっと面白かったね」
ふっと目を細めた彼に同意を求められた時、
「アンタたち~、アタシを無視して何楽しそうなことしてんのよぉ~」
図書館の位置口から、これまた大量を本を抱えたマルス様。ぱっと見、医学書が多いようだ。意外だわ。
「それ、全部借りてきたんですか?」
「そうよぉ。アンタがいなかったから手続きに手こずっちゃったじゃないのぉ~」
「それは申し訳――」
と謝ろうとすると、器用に本を抱え直したマルス様が、私の額を手袋をした指先で弾く。
「でも、ちょっと見直したわ」
「え?」
「さっきのアンタの悪い顔ぉ。案外いい性格してんのね!」
さっきの私の悪い顔……?
アトル様に視線を向けると、濡れたままの彼もそれに同意なのか、頷きながらクスクスと笑っている。
自分で顔を触ると、思い出すのはニヤリと上げた口角の感覚。
それに思わず、私も小さく笑った。
「……そんなことありませんわ」
弾かれた額は、あまり痛くない。
拝啓 親愛なるリカ=タチバナ様
今日は少しだけ、楽しいことがありました。
ところで――私ってそんなに性格悪いですか?