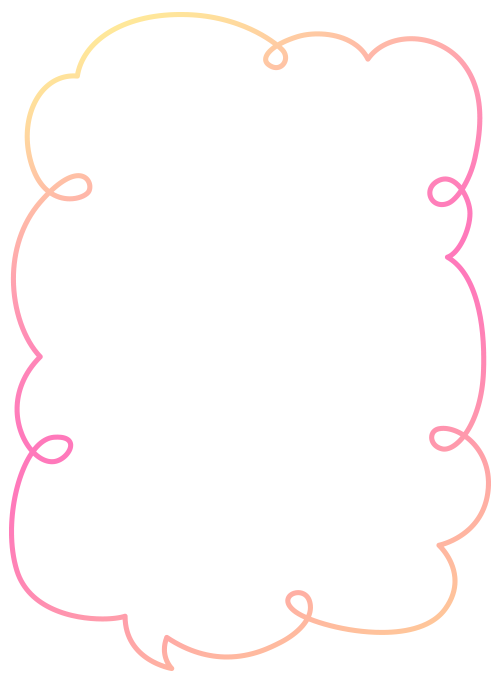「人魚はね、体温が人より低いのよ」
あの後、マルス様は教えてくれた。
「アタシたち、いつも手袋しているでしょう? それは自衛なの。素手で触れ合うと、アタシたちは火傷してしまうから」
まるで呪いね――そう笑うマルス様は悲しそうだった。
「知らなかったんでしょう? アンタは何も悪くない」
アトル様は応急手当をしたあと、再び眠っている。魔法で治せないかと思ったんだけど……そういう便利な魔法はないという。癒しは、あくまで聖女のみ許された力。それは海でも共通の事実だったらしい。なんで、こんなことに限って……。
落ち込む私に、マルス様は言う。
「やめるなら、今のうちよ。結婚」
その言葉に、私の胸がズキンと痛んだ。
「別にやめさせたいんじゃない。アタシもアンタのことは気に入ってるわ。アンタがアトクルィタイのお嫁さんになってくれたら、アタシも嬉しい。でもね……」
マルス様は少し言い淀んで。それでも、私の顔をしっかりと見て告げる。
「愛する者同士が触れ合えないって、とても辛いことなんじゃないかしら……アンタの顔を見ていたら、改めてそう思ったのよ」
私は……どんな顔をしていたんだろう。
怖くて、窓に映る自分を見ることが出来ない。打ち寄せる波の音が聞こえる。
知らなかったから、仕方ない。
だから、私は悪くない。
本当に――それでいいの?
翌日、私は図書館へ赴いた。探すのは、海についての本。海はどんな場所? どんな種族がいるの? そして人魚とは。人魚の生態は?
図鑑や参考書、史実。やっぱり……あらゆる書棚を探しても、海に関する本はない。唯一あるのは、児童書の中にある絵本のみ。
私は場違いを気にせず、可愛らしい椅子に腰掛けた。昔、お父様に読んでもらったことがある。
海に憧れた少年が、船を作り航海する。
しかし船を漕いでも漕いでも、どこにも辿りつかない。
水や食べ物が底を付いた時、少年は綺麗な歌声を聴いた。その直後、海から現れた巨大な魔物に船ごとまるのみされ、少年は死んでしまう。
そんな怖いだけの御伽話。
だけど、今の私は知っている。彼らはそんな酷いことをする人たちじゃない。きっと遭難している子供がいたら、食べ物を分け与えて親元へ帰してあげるような優しい――
「あながち嘘じゃないわよ、その絵本」
聞き馴染みのある女言葉の男性の声に、私は顔を上げた。
「海からしたら、陸の生物なんて食糧みたいなものだもの。試しに食べてみよう、と思う輩がいたって何もおかしくない。アタシたちの交流だって、本当は何年、何十年かけて、少しずつ歩み寄るべきなんだと思うわ」
今日も奇抜な格好をしたオネエが、私の隣の床に座る。私も低い椅子に座っているからか、顔の高さが一緒になった。
「それを……婚約の話が来てから半年? 急ピッチすぎるのよね。本当は体温差の問題もどうにかしてあげたいんだけど、色々と間に合ってなくて」
「どうしてそんなに急ぐ必要が?」
「だって、アンタ年増じゃない。ゆっくりしてたら、あっという間にアンタ死んじゃうでしょう」
何の悪気もなしに、マルス様は言う。そんな今、急所を抉らないでも……。
だけど、
「アトクルィタイは他の誰でもない、アンタと結婚したいのよ。アンタたち陸の生物は短命だからね。他の雌じゃあ意味ないの。それに、アンタいいところの一人娘でしょう。子供だって産んで、あのおとーさんに孫を抱かせたいだろうしさ。だから体温の問題も早急に解決しないとなんだけど……」
と、マルス様はブツブツとごちる。
全部、私のため? まさか。そんな。
「……今日はどうして図書館に? アトル様は?」
「アトクルィタイなら、熱もだいぶ熱が下がったわ。怪我も思ったより大丈夫。風邪を引いている時だったのが不幸中の幸いね」
今日はこれを寄贈しにきたの、とマルス様は本を渡してくる。その分厚い本は、海の生物について纏められた図鑑だった。パラパラとめくると、マンボウと書かれた絵付きのページが出てくる。確かにルビィ公爵にそっくりね。
「海とは文字すら違うから、二人で描き写してたのよ。ようやく昨晩それが出来たから。まずはアンタに借りてもらおうかしら」
マルス様は安々と、冗談みたいに軽く言うけれど……。
え、二人で描き写した? アトル様とマルス様ふたりで?
この本、何ページあるの? ほとんどのページに魚の絵も描いてあって、五百ページは簡単に超える。半年前に覚えた文字を? たった二人で?
え、この二人……他にも何をした? 私たちが好むようなご飯を作ってくれた。屋敷も一から作ったはずよね? 海岸にあんな立派な館なんて今までなかったもの。人魚と人間では話す言葉もてんで違った。それに歯を作ったとも言っていて……そもそも歩くのにも苦労したって言ってなかった?
驚いて――私の目から涙が溢れた。
私との婚約で、私のために、これだけのことをしてくれていたのに……私は、何を返せたの? 二人に、何をしてあげた?
「ふふ。アンタを泣かせるなんて……アトクルィタイに怒られちゃうわね」
マルス様が涙を拭ってくれる。当然、手袋をした指先で。布越しでも、その手はヒンヤリと気持ちよかった。
「そんな心配しなぁ〜いで。この結婚がうまく行こうが行かまいが、アタシは恨まないからさぁ――ところでさぁ、アンタ実際に神様見たことある?」
突拍子もない質問に、私は横に首を振る。
礼拝堂や執筆の参考資料に読んだ神話で羽の生えた人の姿は拝見したことあるけど……当然、神様に会ったことなんてない。あるとすれば……聖女のリカ様だけじゃないかしら?
そんな私を見て、マルス様が「うふふ」と笑った。私が持っていた図鑑を取り、指先で表紙をなぞる。
「じゃあ、今晩窓の外を見てご覧なさい。いいモノ見せてあげる」
そして、マルス様は優しい声で言うのだ。
「それ見て、ゆっくりと結婚について考えてね」
そしてその晩。
「雨……?」
昼間はあんなにいい天気だったのに、突然雨が降り出した。ざぁーざぁーと大粒の雨水が窓を叩く。
私はもう湯浴みも済ませて、ネグリジェに着替えていた。本当は寝る前に手紙や書いたり執筆したりするのだけど、そんな気分にはなれなくて。
「これじゃあ、何も見えないわね……」
外はただただ暗い。この屋敷は少し高い位置にあるから、普段は遠くに水平線が見えるの。そして眼下のギリギリにアトル様たちの白い屋敷の屋根が見える。
だけどこんな暗かったらそれさえ――と思った時、稲光が海に落ちる。そのすぐ後で、バシンッと世界にヒビが入ったような轟音が響いた。
思わず身を縮めた時、
「え……?」
視界に現れたものに、目を見開く。
海に、黄金に輝く竜がいた。竜という魔物は実在しないはず。空想上のお伽話の存在。小説を書く上で空想上の魔物を調べた私だからこそ、知っているくらいの……。
蛇のように長い体躯が浜辺から海の沖まで伸びている。黄金の硬そうな鱗に、鋭い爪。馬のように長い顔が、こちらを向いている。その額に焦げ付いたような跡があった。その形は、まるで添えられた手のようで。
そして、竜は鳴く。
泣いているような、悲しい声で。キューンと、何かを、誰かを、乞うように。
その時、視線の端で何かが光った。それは部屋の中。机の上に置いておいた、海の図鑑。寄贈された直後に借りた本。
引き寄せられるように、私は本を手に取る。ページは自然と開かれた。それに驚く間もなく、とある文字が目に飛び込んでくる。
『落とし子。神が海や地に落とした神の孤児。その存在は、その世界の者に陸では祝福を、海では災厄をもたらすという』
そのページに、絵はない。ただその他無蔵の中のひとつに、書いてあるだけの短い文。
だけど、嫌でもわかる。わからないわけがないじゃない……。
「あれが、アトル様……」
金色の竜は、夜の間ずっと鳴いていた。雷鳴が響く中で、ずっと、ずっと。水平線の向こうから、同じ色の朝陽が昇る時まで。
その声を聞きながら、私はペンを取る。
そして、聖女様に手紙を書いた。
拝啓 親愛なるリカ=タチバナ様
私は、婚約を破棄した方がいいのかもしれません。
私と彼は、違いすぎる。姿も。形も。想いの大きさも――
私は彼に、何も返せない。
その雨は、三日三晩止まなかったけれど。
三日後に突如来訪した聖女は、玄関を開けた早々言い放った。
「納得できませんっ!」