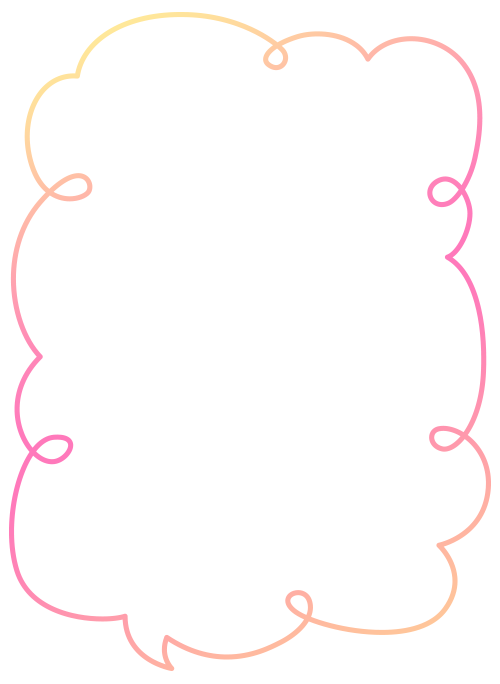後日。
マルス様は大笑いしていた。
「あっはっはっ。ウケる~、本当に何度聞いてもウケるわぁ。アンタが美貌で男を陥落させる悪女? この年増が? あぁ……何度聞いても涙が出ちゃう。陸の噂バナシの適当さは本当笑わせてくれるわねぇ~」
王太子殿下と聖女の結婚披露宴も終わり、私たちの日常が戻ってきた。今日もアトル様の海辺の屋敷で執筆に勤しむ――予定だった。せっかく久々にゆっくり書けるというのに、勝手に椅子を持ってきてマルス様が膝を叩いているのだ。
私はむすっと、いつも通り派手なオネエに言い返す。
「お言葉ですが……マルス様のお噂も大概ですよ? なんですか、色情の悪魔って。私がミハエル様たちと話しているの、そんなに長い時間じゃなかったですよね? あの短時間に何やらかしたんですか。ルビィ公爵なんて部屋に閉じこもってしまったらしいですよ?」
「ほんっっっと、噂って残酷よねぇ~。こんな美しいアタシが悪魔呼ばわりなんて。陸の醜いマンボウごときが尻揉んできたから、そのちっこいイソギンチャクを握り潰してやっただけなのに~」
白々しく肩を竦めるマルス様に、私は嘆息しか返せない。
マルス様は苦笑する。
「あ、海のマンボウはもっといい子だからね。今度紹介してあげるわ」
「それは有り難いお申し出ですが……アトル様は?」
今日は屋敷に来てから、マルス様としかお会いしていない。だから机に上にはお茶も置かれていないのだけど……
「あら、喉が乾いた? 飲み物は塩水でいいかしら?」
「いやそういうことじゃなくってですね……」
当然、飲み物の催促したわけじゃないわ。いつも真っ先に私を出迎えてくれて、お茶やらお菓子やらで執筆を支えてくれる婚約者の顔が見れないから……うん。改めて思うといたれりつくせりね。
私の質問に、マルス様が珍しく気まずそうに視線を逸した。
「あの子さぁ……風邪引いちゃって、寝込んているのよねぇ……」
「え?」
「どーして真っ先に教えてくれないんですかっ⁉」
「だって体調不良なんて不名誉なことじゃあない? そんな病弱者だとバレたら、海だと一斉に襲われて大変な騒ぎになるわよぉ」
「本当海って物騒すぎませんかね⁉ もっと慈愛の心とかないんですか? 薄情すぎません?」
「うーん……それは否定しない」
ずんずんと、勝手に屋敷を歩く私のあとをついてくるマルス様。
「アンタには教えるなって言われてだんだけどねぇ……」
「いつから熱出しているんですか?」
「披露宴帰ってきた直後から」
それってもう三日以上寝込んでいるじゃないですか……。
それに、もしかして私のせいですか? 私の『ファンサ』のせいですか⁉
アトル様の部屋の前で立ち止まった私の頬を、マルス様がニヤニヤと手袋ごしの指先で突いてくる。
「『色情の悪魔』の異名、譲りましょうか? 悪女さま?」
「結構ですっ!」
私は扉をノックして、「アトル様……」と扉を開く。
すると、本で埋もれたベッドから身体を起こそうとする少年がいた。
「ニカ……ごめんね。ろくにおもてなしも出来なくて……」
「そんなの構いませんよ、もう……」
慌てて駆け寄る私の後ろから、嘆息が聞こえる。
「アンタ、また勉強してたの?」
それにアトル様は答えない。喋ろうとして咳き込んでしまうアトル様の背中を、私はさする。薄手の寝間着を着ているアトル様の体温は、思ったより高くない。だけど顔は真っ赤だし、とてもつらそう。
「アトル様、お熱は……」
熱が高いなら、冷やすものを用意しなくちゃ。あと消化に良いものを用意して……場合によっては馬を走らせて医師を呼ぶ必要もあるかも。人間と人魚の違いがあるから、マルス様に相談して――などと、色々考えながら。
私は素手で、アトル様の額に手を当てる。
だけど、
「だめっ‼」
マルス様の制止と、アトル様の「熱っ」と顔をしかめたのは同時だった。
「え?」
私が慌てて手を引っ込めたときには、もう後の祭り。
小さく呻くアトル様の額は、私の手の形に赤く爛れていた。