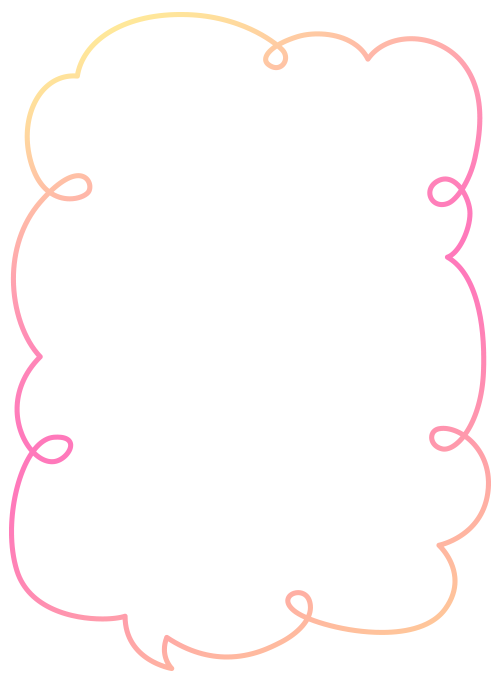リカ様は、とても綺麗だった。可愛らしい顔立ちに似合う華やかなドレス。ふんわりとしたシルエットは、私には決して似合わない形。清楚な黒い髪に、大粒のダイヤモンドが映えていた。ダイヤモンドという宝石はその名の通り、王族だと示す証だ。
世界一美しいとされるその宝石よりも、彼女の笑顔は眩しかった。
「ヴェロニカ様、お久しぶりです! 相変わらず綺麗ですね! さっきは素敵なスピーチありがとうございました! 本当に本当に嬉しかったです! あぁ、ヴェロニカ様だぁ! 本物だぁ、相変わらずいい匂いがする……さすがリアル二次元……わたしの推し……」
なんだろう……久々の『聖女節』に既視感を覚えるような……。
飛び込んできた今日の主役には驚き、変わらない彼女に少し気まずさを覚え。
それでも今声を掛けてくれたことに、有り難いと思うのも事実。
「それじゃあ、ぼくはまた……」
主役の前では分が悪いしと、ルビィ公爵が後ろに下がっていく。すれ違うようにやってきたのは、もう一人の主役だ。
「リカ。急に走り出しちゃダメだと何度も言っているだろう?」
「ごめんね、ミーシャ。でもヴェロニカ様が見えたら……」
「まったく……久々だね、ヴェロニカ」
そう私に笑みを向けてくるミハエル様は、私の記憶の中と変わらず凛々しく、そして美しかった。差し出された手を、私はそっと握り返す。
「お久しぶりです、ミハエル様。リカ様。ご結婚おめでとうございます」
「あぁ、ありがとう」
お二人が仲良さそうで何よりです。愛称で呼び合うようになったのですね。
そんな僻みを口にするつもりはないけれど。それでもミハエル様の表情が少しだけ曇る。
この気まずい握手が、今の、そしてこれからの、私と元婚約者の関係。
だからこそ、無邪気にその空気をぶち破る彼女こそが、残酷でもあり、ありがたい。だっていくら後悔しても、過去は変わらないのだから。
「それよりもヴェロニカ様! さきほどの見事なオタ芸を披露してくれた人はどちらですか? あの人がヴェロニカ様の手紙の人なんですよね⁉」
私の腕にしがみついたまま、キョロキョロと当たりを見渡すリカ様。
それに答える前に、聞かざる得ない。
「オタゲイ……て、なんですか?」
「あれ、知らないんですか? あの棒ライト持って踊るあれですよ。てっきり私のためにアイドルとオタクハロウィンしてくれたと思ったんですけど……違うんですか?」
ひとつ聞いたら知らない言葉がさらに増える……しかも本人に自覚なし。
思わずミハエル様を見上げると、肩を竦められてしまった。えぇ、知っています。本人に悪気はないんですよね。相変わらずなんですね。
「まぁ、なんでもいいです! それより、わたしにもファンサをしてくださいっ!」
え……この子はいきなり何を言い出すの……?
「ふぁんさって、ヴェロニカが婚約者を気絶させたあの行為のことかい?」
「そうです! ヴェロニカ様のハート付きウインクなんてご褒美以外のなにものでもないですよ! 死んでもいいくらい尊いものです! ぜひ! 私にも! 結婚祝いだと思って!」
押しが強いが……あんな恥ずかしいこと、できるわけないでしょう⁉ リカ様が騒ぐから注目も集まっているんですよ⁉
だけど、それもわかってミハエル様が言う。
「そうだね、私もヴェロニカからファンサを貰いたいな。僕に相談もなくあんな素敵な余興をしてくれたんだもの。おこぼれくらい頂戴したいね」
あぁ……やっぱりあの余興は問題ありでしたよね。
「すでに何件の苦情を処理したと思う?」
と耳打ちされて、私は頭が上がらない。
本当、これだから嫌なのよ。二人とも……特に未だ腕に引っ付いているリカ様の距離が近すぎる。私なんて、ただの臣下の娘。リカ様からしたら、夫の元婚約者なんて、目障りのはずじゃないの?
「お二人は……お変わりないですね……」
思わず本音を零すと、二人は顔を見合わせた。そして吹き出す。
「ヴェロニカは変わったね。美貌で男を悶絶させるなんて、なんて悪女だ」
「より魅力的になって惚れ直しちゃいました。なので、ぜひファンクラブ会員会長のわたしにもお情けを!」
そこ言葉たちに、私も思わず吹き出して。みんなで、為政者たちが集う場ということも忘れて、声をあげて笑ってしまう。
もう……本当にひどい二人だわ。