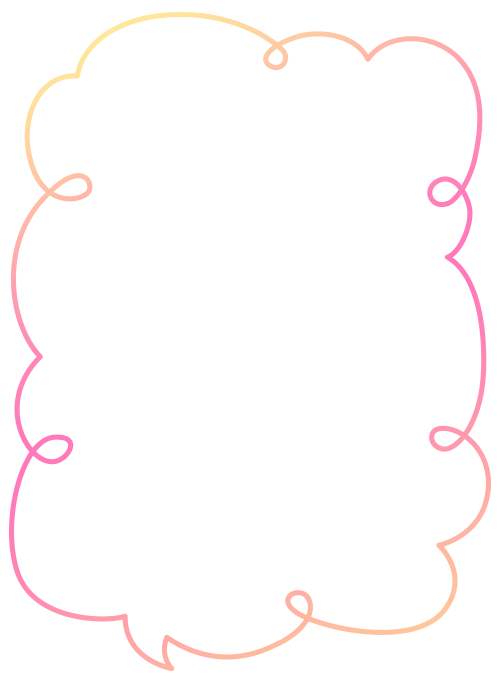「教室に残して来たんだねっ!? どうして、残して来たの!」
優斗の剣幕に、芽衣もたじろいだ様子だった。でも、そんなのには構っていられない。
「なんで、…って、だって、沙耶が残るっていうんだから、別に良いかなって思って……」
「教室に、崎谷先生が居ただろっ!」
優斗の言葉に、芽衣の顔がはっとした。その顔を見て、一瞬で理解した。芽衣は、共犯者なのだ。
「………っ!」
一瞬でも早く教室に行かなければならない。そう思って、芽衣の横をすり抜けようとしたときに、腕を後ろから捕まれた。
「…っ、芽衣ちゃんっ!」
「優斗くん! 今は、教室は駄目っ!」
「なんで! 沙耶と……、沙耶と先生が二人で居るんだろっ!」
そんなの、許せない。二人になった途端に、あの先生は沙耶に何をするか分かったものではない。
ぎり、と芽衣をねめつけると、それ以上に真剣な芽衣の視線が強くぶつかってきた。
「確かに、教室に二人とも居るわよ。…だけど、あの二人が望んだ時間なのよ。もう、許してあげてよ……」
芽衣の言葉に、優斗は激高した。
「許すって、何だよ! 芽衣ちゃんは、先生の味方するのか! おかしいだろっ!? 教師と生徒で、なんてっ!」
「でも、本人たちは真剣なのよっ!」
芽衣の言葉が理解できない。教師が…、大人が高々十七の子供に真剣だなんて、そんな訳あるか。絶対に崎谷先生が沙耶を弄んでいるだけに違いない。
「真剣なわけあるか! 沙耶は騙されてるんだ!」
もうこれ以上芽衣と話をしていても結論は出ない。優斗は芽衣の腕を振り切って廊下を走ろうとした。それを、芽衣が背後から腕を引っ張るようにして止める。
「本気なのよ! 先生も、沙耶も! 優斗くんたち、親友でしょ!? 分かってあげてよ!」
「そんな訳ない! 沙耶は…、騙されてるんだっ!」
芽衣の静止を引き摺って、勢い良く教室の扉を開ける。そこには……。
唇が触れ合わんばかりの距離で、先生と沙耶が寄り添っていた。先生は明らかに優斗を目で威嚇していて、扉の開く音に驚いた沙耶が体を引いても、沙耶の傍から離れようとはしなかった。
認めたくない。沙耶は、絶対に俺が守る。そう思っていたのに……。
「違う! 優斗! 私、本当に……、…本当に先生のこと好きなの……っ」
沙耶の口から、一番聞きたくない言葉だった。先生が何を言っても、沙耶が本気だなんて、思ってなかった。絶対に、先生に騙されているだけだと思っていた。…だから、自分が守ってやらなくてはと必死で…。
…でも、沙耶の瞳が、彼女の揺るぎない気持ちを物語っている。…本気だと、言っている。
信じたくなかった。信じたくなかった。でも……。
「…悔しいだろうけど、男だったら、好きな子の幸せ、喜んであげてよ……」
芽衣が優斗の腕を引っ張ったまま、そう言った。…そうしたかった。本当に、そうしたかった…。自分がちゃんと祝福してあげられる男子と結ばれてくれたのなら、いくらだって喜んでやれた。なのに……。
でも、もう何を言っても駄目だって、分かった。
大事な大事な幼馴染みの沙耶は、その手で自分の幸せを掴まえてしまっていた……。
*
秋の空。絹糸を引くような雲が薄紅に染まろうとしている。眩しいほどの金色の夕日が教室に差し込んでいて、優斗の背後に長い影を作っていた。
今日の部活はお休み。終礼後、久しぶりに友達と教室で無駄話をしながら過ごした。その友達たちも、そろそろ帰る、と言って、教室を出て行った。優斗も机の中身を確認する。忘れ物はないようだ。
ふと、窓際に立って体育館の脇の紅葉した桜の木を眺めていると、あまり人の通らないそこに、二人の人影があった。
沙耶と、先生。
眩しいくらいの光の影で、二人はのんびり歩いている。沙耶の、先生に向ける笑顔が金色の夕日よりも眩しくて、優斗は窓辺から身を離した。
…もう直ぐ沙耶が教室に戻ってくる。そうしたら、笑って駅前のハンバーガーショップに誘ってみよう。
まだ少しだけ、ほんの少しだけ胸が痛いけれど、でもきっと楽しい話をしながらハンバーガーを食べることが出来る。
誰にも譲りたくない、沙耶の幼馴染みとして、きっと優斗は隣に居られるのだ……。