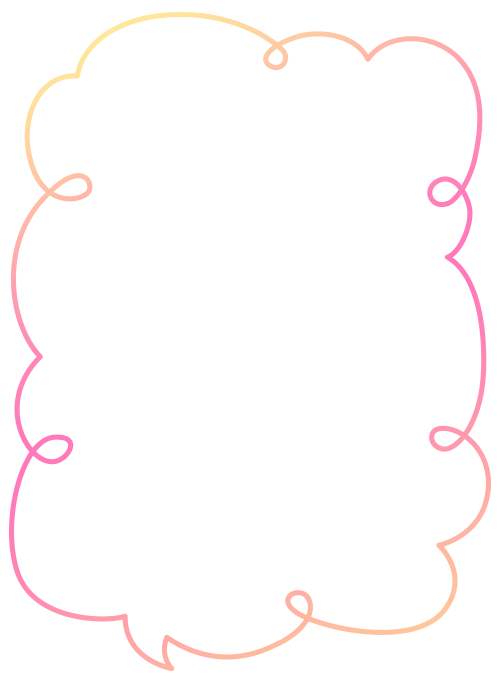「良かったのか? 断ってしまって」
体育館の壁に寄りかかってこちらを見ていたのは、崎谷先生だった。あまりに突然現れるものだから、咄嗟に上手い言葉が出てこなかった。
「…っ、……んで……」
「なんでって、そりゃ、沙耶が俺に隠し事しようとするからだろ。どーせそんなこっちゃないかって思ったけど、本当にそうだとはなあ。つか、あの三年生、まだ諦めてなかったのもすごいっつーか…」
おとなしそうな子なのになあ、なんて、彼が去って行った方を見る。でも沙耶はびっくりした顔のまま、先生の顔を見てしまってばかりだった。
「……良かったの?」
「………え?」
「だから、断ってしまって。…ふつーの恋愛出来るチャンスだったんじゃないの?」
崎谷先生が薄明るい空を背に立っているから、目を凝らしても表情は見えない。でも、茶化すような口調にもかかわらず、声がなんとなく自虐的な雰囲気だった。
「…だったら、なんで最初のとき、あのタイミングで呼んだんですか…?」
もし、今の先生の言葉が全部本当なら、あの時先生は意図的にあの場に割って入ってきたということになる。なのに、どうして今、そんなことを言うのだろう。
「ん? 本当はどーなのかなーって思って。本当のことは、沙耶しか分からないからな」
「…分かってください…。先生、大人でしょう?」
「大人でも、自信ない時だってあるんだよ」
立場利用してない自信もねーし。
くしゃくしゃと乱暴に髪の毛を触って、そんなことを言っている。そんな風にしたら、綺麗な髪の毛が乱れてしまうのに。
「…利用してでもいいですから、そんなこと言わないで下さい……」
泣きそうになる。どんなことをしてでも奪ってほしいのは、先生だけだ。
「……悪い大人の見本だな」
「…悪くてもいいです」
「お前、そんなこと言って…。知らんぞ」
悪い大人だったら、嫌って言っても、離してやれんぞ。
脅したつもりなのだろうか。でも、沙耶にはこれから先ずっとの約束をもらったような気がして、心が震えるばかりだ。
「…離さないでいてください…。私は、先生が、いいです……」
先生が、好きなんです……。
やさしい先生も、悪い大人の先生も、全部全部が、好き。
沙耶が言うと、先生は体育館の壁から体を離して、影の中へと入ってきた。
「……やっとちゃんと言ったな」
やさしくて深い声が、沙耶の耳に届く。沙耶の前まで歩いてきた先生は、腕をそっと回して、沙耶のことを抱き締めてくれた。先生の言葉に応えるように、沙耶はきゅっとその背中にしがみつく。
「もう、離してやらん。…絶対だ」
耳元で告げられた言葉に、体が震えそうだった。濃くなっていく夕闇が、やがて二人を取り込んでいく。
学校の片隅で、二人はそっと、キスをした。