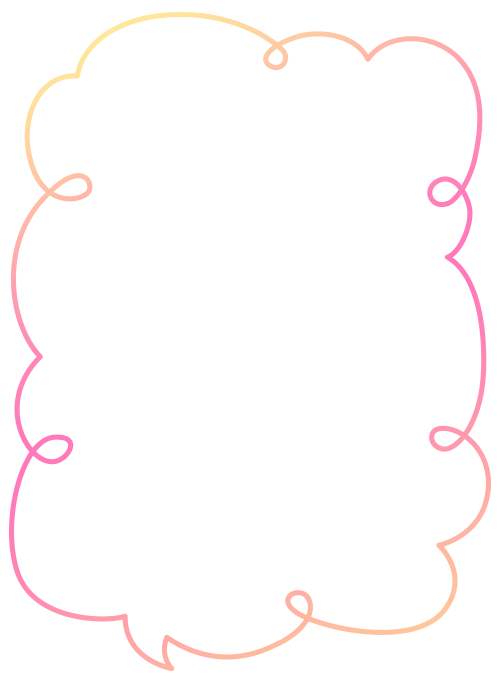「あ、そーだ。今日、午後の練習休みなんだ。沙耶、帰り一緒に駅まで帰らない? ハンバーガー食べていこう?」
え、と思った。確か、優斗にテスト前に世話になったお礼におごると言う話が流れたままだった。でも、今はなんとなく、優斗と長い時間一緒に居ない方がいいような気がする。何がきっかけで昨日のことがばれてしまうか分からないし、もしばれてしまったら、先生にも迷惑がかかる。
「ううん。それより、彼女と帰ってあげてよ。痴漢の件、まだ落ち着いてないでしょ? それに、私、放課後は図書室行くし」
沙耶の言葉に、優斗も、ちょっと耳を赤くしながら、あー、うん、と照れながら頷いた。やっぱり、大事な彼女を放ってはおけないらしい。そこは大変微笑ましいので、なんとなく沙耶も顔が綻んでしまう。
(良いな、こういうの)
本当に、優斗たちの付き合いは好印象だ。勿論他の付き合ってる同士の子たちもそうなのだろうけど、沙耶は生憎優斗たちしか知らないので、彼らのことをあたたかく見守ってやりたいと思う。学生の恋愛って、こうだよなあという見本みたいだ。
そう思うと、自分の気持ちはどうなのかと、少し胸の奥の方が罪悪感でちりちりする。相手は大人で担任の先生で…。でも、昨日のことを優斗に隠しておきたいと思うくらいには、気持ちが崎谷先生の方に向いてしまっている。決して嫌な記憶としてじゃなく、こっそり大切な秘密にしておきたい、という意味だ。
『大人が本気出したら、俺ら高校生なんてちょろいもんじゃん』
いつかの優斗の言葉を思い出す。…先生は、自分のことをどうしたいんだろう。手玉にとって、遊んでみたいんだろうか…。もしそうだとしたら、もう沙耶は十分先生に翻弄されている。
『崎谷先生は、多分そういうところ、凄く真面目だと思うわ』
先刻芽衣が言っていたことは、優斗の言葉とは反対のことだ。…でも、あんなにカッコよくて、性格も悪くないと思うし、…なにより大人だから、恋愛の対象ならもっと選り好みが出来るはずだ。…なにも沙耶じゃなくたって。そんな人が、どうして自分に対して本気だって思えるだろう。…だって、沙耶は先生から見たら絶対子供だし、きっと今まで崎谷先生が恋してきた大人の女の人の足元にも及ばないと思うのだ。
どうして……。
(…どうして、私なんかを、相手にしてるんだろう……)
遊ぶ相手だとしても、…考えられないけど、もし本気だったとしたら、余計に。
でも、そう考えるだけで、心臓が甘く疼いてしまう。どんな理由であれ、崎谷先生に気にかけてもらえることは、沙耶の鼓動を逸らせるばかりだ。真っ暗な深い深い海の底に、光が差したような喜び。…どこかで、間違いでもいいって思ってる。
『本当に好きだったら、ちゃんと先生のほう向いてあげてね』
向いた先に、何があるんだろう。見えない道に、沙耶の心臓は走ったままだった。