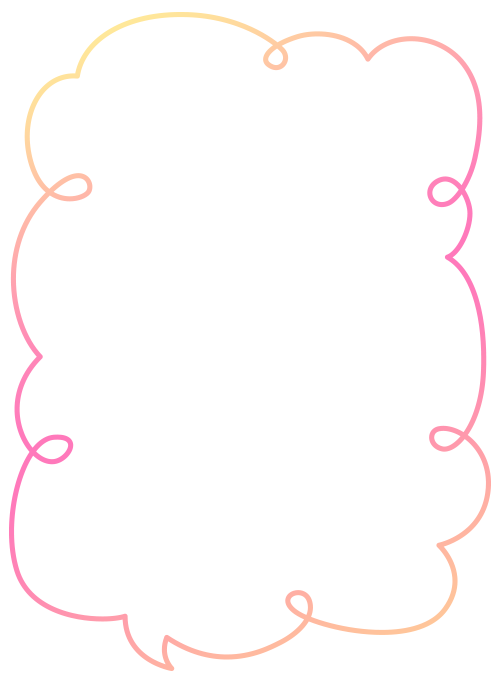「さや」
聞いたことのない、声。低くて、とても崎谷先生のものとは思えない。知らない、大人の人みたい。
なかなか顔を上げない沙耶を、先生が頬に触れさせていた手を顎を支えるようにするりと移動させて、そしてそっと持ち上げてしまう。きっと真っ赤になっているに違いない自分の顔を先生の前にさらしたくなかった沙耶は、小さな声で、いや、と叫んだ。
「…さや。目ぇ開けて。……ちゃんと、俺を見て」
先刻のからかう声はどこにもなかった。もしかして鼻先が触れてしまうかもしれないくらいに、きっと傍に居る。先生の息遣いが分かって、もう堪らなくなった。
恥ずかしさと、後ろめたさで、涙が出そうになる。堪えるためにも頑なに目を閉じたままでいたけれど、先生はそれを許してくれない。
さや、と秘め事のように囁かれる。応えることが出来ずにいたら、不意に右の瞼に触れる感触があった。
「………っ!」
思わず、目を開ける。目の前には、声と同じくらい真剣な表情の先生がいて、合わさった視線が外せない。
……先生は、眼鏡を外していた。
硝子を通さないやさしいカーブの瞳が、まっすぐに沙耶を射抜く。狩りをする獣みたいな物騒な光が黒目の奥の方に見えて、ますます目が離せない。
「……せ…」
んせい、とは続けられなかった。
崎谷先生の右の手がしっかりと沙耶の頬下を支えていて、そのまま近づいてくる先生の顔を避けることは出来なかった。…避けるだなんてこと、思いつきもしなかった。
湿ったやさしい感触が、右のこめかみに落ちる。なにが起こったのか、瞬時には理解できなかった。
「………、……」
固まって呆然としていた沙耶に、先生は見たこともない笑みで微笑ってきた。…汗の、においがする。
「………黙っとけよ?」
にやりと、鋭さとやさしげな色を同居させて微笑った先生が言う。先生は沙耶の顔を捉えていた手を外すとそのまま日誌をその手に取り、教室を出て行ってしまった。
取り残された沙耶は、こめかみに篭る熱と、甘くて陶酔しそうな先生の残り香の中で、その場を動けなかった。