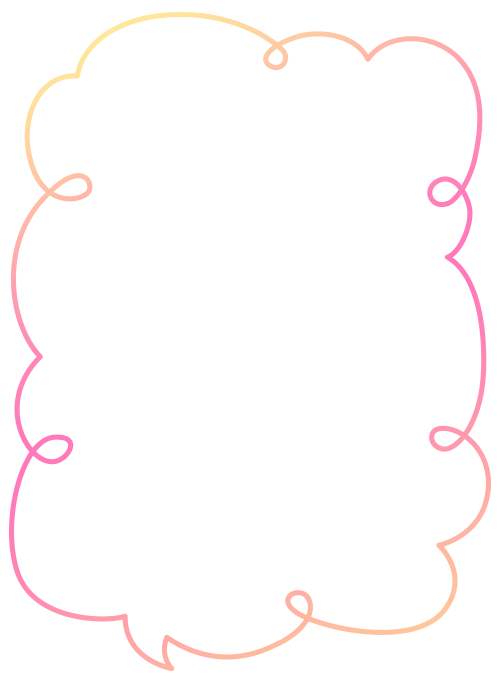「…大丈夫だって思って聞かなかったけど、崎谷先生と一緒で、本当にに良いのかな? 崎谷先生はなんにもしてないって言ってたけど、もし、なにか崎谷先生に理由があるんだったら、一緒に帰るのも体調に悪いし…」
沢渡先生も、横尾先生と同じ心配をしてくれる。でも、本当に崎谷先生の所為ではないのだ。足元の崖の下の深い海は、沙耶が勝手に感じているだけのもので、だからその所為で崎谷先生が不名誉な疑いを持たれるなんてこと、あってはならないのだ。
「大丈夫です。崎谷先生の所為じゃないです」
「…自分で、心当たりはあるの?」
保健医の先生らしく、沙耶の体調を細かく心配してくれる。…ふと、沢渡先生なら分かるかなと思って、聞いてみた。
「……先生。…先生は、何かのにおいが怖いって思うこと、ありますか?」
「におい?」
沢渡先生は、突然の問いに大きな目をぱちりとして、それから意味ありげに目を細めた。
「…逆の話は聞くけど。好きな人の体臭をいいにおいだっていう人が多いのよね。それは、より良い遺伝子を残そうとする本能が、においでそれを嗅ぎ分けていて、だから例えば恋人の汗のにおいなんかを甘いにおいだとか言うのよ。怖いって言うのは逆のことで、異性として危険を感じてるのかな? 時々あるのよ。女の子が、誰々先生の傍に立つと汗のにおい嗅いだだけで身震いしちゃう、ってことが。…まあ、単に苦手なだけかもしれないけど」
「……そうですか」
足元の深い海に飲み込まれそうだ。でも、必死で崖の端にしがみついている。
「ありがとうございました。私、帰ります」
「うん。気をつけて。…なにかあったら、また保健室にいらっしゃい」
沢渡先生は微笑んで送り出してくれた。廊下に出ると職員室の方から横尾先生が走ってきて、そして肩をわっしと掴まれた。
「沙耶。崎谷と一緒で大丈夫なのか? また具合悪くなったりとか…」
「大丈夫です。ほら、もうちゃんと歩けますし。ちょっと体がだるいけど」
「そ、そうか…」
横尾先生は、まだ少し納得していないみたいだったけど、沙耶が足を出すと、付き添うように隣を歩いてくれる。正面玄関へ向かうと、崎谷先生がジャケットを羽織っていた。ロータリーにはもうタクシーが来ていて、沙耶は崎谷先生が玄関を出るのに続いて硝子のドアを出た。
開いた車のドアの横に先生が立っている。多分奥に座りなさいという意味なんだろう。ありがたくシートの奥に座ると、崎谷先生が乗り込んできて、タクシーは学校を後にした。
沢渡先生も、横尾先生と同じ心配をしてくれる。でも、本当に崎谷先生の所為ではないのだ。足元の崖の下の深い海は、沙耶が勝手に感じているだけのもので、だからその所為で崎谷先生が不名誉な疑いを持たれるなんてこと、あってはならないのだ。
「大丈夫です。崎谷先生の所為じゃないです」
「…自分で、心当たりはあるの?」
保健医の先生らしく、沙耶の体調を細かく心配してくれる。…ふと、沢渡先生なら分かるかなと思って、聞いてみた。
「……先生。…先生は、何かのにおいが怖いって思うこと、ありますか?」
「におい?」
沢渡先生は、突然の問いに大きな目をぱちりとして、それから意味ありげに目を細めた。
「…逆の話は聞くけど。好きな人の体臭をいいにおいだっていう人が多いのよね。それは、より良い遺伝子を残そうとする本能が、においでそれを嗅ぎ分けていて、だから例えば恋人の汗のにおいなんかを甘いにおいだとか言うのよ。怖いって言うのは逆のことで、異性として危険を感じてるのかな? 時々あるのよ。女の子が、誰々先生の傍に立つと汗のにおい嗅いだだけで身震いしちゃう、ってことが。…まあ、単に苦手なだけかもしれないけど」
「……そうですか」
足元の深い海に飲み込まれそうだ。でも、必死で崖の端にしがみついている。
「ありがとうございました。私、帰ります」
「うん。気をつけて。…なにかあったら、また保健室にいらっしゃい」
沢渡先生は微笑んで送り出してくれた。廊下に出ると職員室の方から横尾先生が走ってきて、そして肩をわっしと掴まれた。
「沙耶。崎谷と一緒で大丈夫なのか? また具合悪くなったりとか…」
「大丈夫です。ほら、もうちゃんと歩けますし。ちょっと体がだるいけど」
「そ、そうか…」
横尾先生は、まだ少し納得していないみたいだったけど、沙耶が足を出すと、付き添うように隣を歩いてくれる。正面玄関へ向かうと、崎谷先生がジャケットを羽織っていた。ロータリーにはもうタクシーが来ていて、沙耶は崎谷先生が玄関を出るのに続いて硝子のドアを出た。
開いた車のドアの横に先生が立っている。多分奥に座りなさいという意味なんだろう。ありがたくシートの奥に座ると、崎谷先生が乗り込んできて、タクシーは学校を後にした。