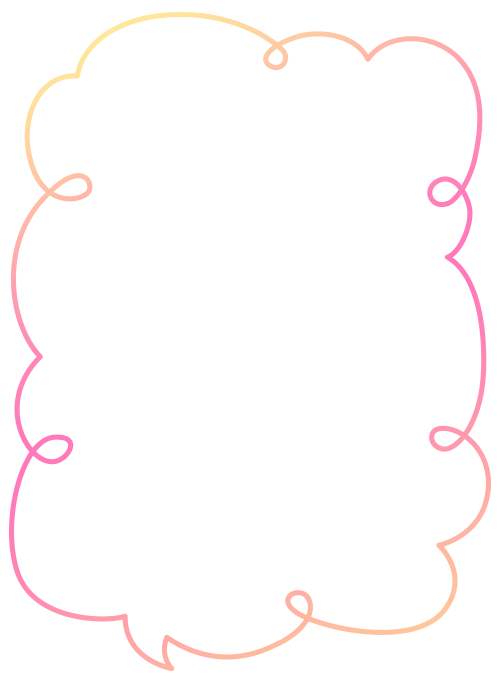「沙耶?」
咳の音と、ベッドが軋む音に気が付いて、カーテンが勢いよく開けられた。顔を覗かせた横尾先生が心配そうな顔をしている。
「大丈夫か、沙耶。苦しくないか?」
すぐにベッドの脇に寄ってきてくれる横尾先生に、頷いて返事をした。咳をしてしまったから、ちょっと顔がゆがんでいたかもしれない。
「辛いか? …泣いたな?」
「あ、…いえ、これは……」
こめかみを伝って落ちた涙のあとを、横尾先生が見つけて、心配そうに顔を覗き込んでくる。その向こう、カーテンの隙間から、保健室のドクターキャビネットの前で立ち尽くしている崎谷先生が見えた。じっと眼差しは沙耶の方を見ていて、でも、どうやって近寄ったらいいのか分からない、みたいな顔をしている。
…こんな、不安そうな先生、初めて見た……。
保健室はそれほど広くはないけれど、でもベッドの周りにはカーテンが巡らされていて、小さな声だと布に吸収されてしまうかもしれない。だから、なるべくはっきりと言った。
「これは、先刻、無理矢理体を動かそうとしたら零れただけで、泣いてないです」
「そうか」
安堵する横尾先生の向こうに立っている崎谷先生を見る。少し表情が和らいだように見えるのは、きっと見間違いじゃない。…胸の奥がじんわりとあたたかくなってしまって、困る。
どうして、こんなに生徒のことを思い遣ってくれる先生のことを怖いなんて思ったんだろう。沙耶は自分で自分の感情を責めた。あの時だって、傘を差し出したのは沙耶なんだから、先生には全然悪いところなんてないのだ。
「すみません、ご迷惑おかけしました。私、帰ります」
ベッドから下りようとすると、横尾先生が体を支えてくれようとした。でも、もう発作は治まってしまっているし、少しだるいけど歩けないほどではない。大丈夫です、と言ったら、タクシーを呼ぶから待っていろ、と言われた。
横尾先生が職員室へ戻っていっている間に、沢渡先生がベッドに寄ってきてくれた。念の為、と、脈拍と血圧だけ測ったけど、どちらとも正常値で、大丈夫ね、と先生は笑んでくれた。
「…崎谷先生」
まだ、キャビネットの前を動けない先生に、沙耶は呼びかけてみた。目の前で倒れた生徒を、おっかなびっくり見るような、でも心底心配している表情。
「本当に、…大丈夫なのか…?」
「大丈夫です。呼吸も治まりましたし、タクシーを呼んでいただけるのなら、もう全然心配ないです」
保健室の端と端で話しているのがもどかしい。でも、体がだるいから、距離はこのまま。代わりに、ちゃんと安心してもらえるように、一生懸命笑って見せた。先生は、ほっと息をついて、そうして漸く肩の力を抜いたようだった。
「…ちゃんと、横尾先生に送ってもらえ」
え、と思う。だって、横尾先生は担任でもなんでもないのに……。
「多分、横尾先生が送るって言って聞かないと思うから」
咳の音と、ベッドが軋む音に気が付いて、カーテンが勢いよく開けられた。顔を覗かせた横尾先生が心配そうな顔をしている。
「大丈夫か、沙耶。苦しくないか?」
すぐにベッドの脇に寄ってきてくれる横尾先生に、頷いて返事をした。咳をしてしまったから、ちょっと顔がゆがんでいたかもしれない。
「辛いか? …泣いたな?」
「あ、…いえ、これは……」
こめかみを伝って落ちた涙のあとを、横尾先生が見つけて、心配そうに顔を覗き込んでくる。その向こう、カーテンの隙間から、保健室のドクターキャビネットの前で立ち尽くしている崎谷先生が見えた。じっと眼差しは沙耶の方を見ていて、でも、どうやって近寄ったらいいのか分からない、みたいな顔をしている。
…こんな、不安そうな先生、初めて見た……。
保健室はそれほど広くはないけれど、でもベッドの周りにはカーテンが巡らされていて、小さな声だと布に吸収されてしまうかもしれない。だから、なるべくはっきりと言った。
「これは、先刻、無理矢理体を動かそうとしたら零れただけで、泣いてないです」
「そうか」
安堵する横尾先生の向こうに立っている崎谷先生を見る。少し表情が和らいだように見えるのは、きっと見間違いじゃない。…胸の奥がじんわりとあたたかくなってしまって、困る。
どうして、こんなに生徒のことを思い遣ってくれる先生のことを怖いなんて思ったんだろう。沙耶は自分で自分の感情を責めた。あの時だって、傘を差し出したのは沙耶なんだから、先生には全然悪いところなんてないのだ。
「すみません、ご迷惑おかけしました。私、帰ります」
ベッドから下りようとすると、横尾先生が体を支えてくれようとした。でも、もう発作は治まってしまっているし、少しだるいけど歩けないほどではない。大丈夫です、と言ったら、タクシーを呼ぶから待っていろ、と言われた。
横尾先生が職員室へ戻っていっている間に、沢渡先生がベッドに寄ってきてくれた。念の為、と、脈拍と血圧だけ測ったけど、どちらとも正常値で、大丈夫ね、と先生は笑んでくれた。
「…崎谷先生」
まだ、キャビネットの前を動けない先生に、沙耶は呼びかけてみた。目の前で倒れた生徒を、おっかなびっくり見るような、でも心底心配している表情。
「本当に、…大丈夫なのか…?」
「大丈夫です。呼吸も治まりましたし、タクシーを呼んでいただけるのなら、もう全然心配ないです」
保健室の端と端で話しているのがもどかしい。でも、体がだるいから、距離はこのまま。代わりに、ちゃんと安心してもらえるように、一生懸命笑って見せた。先生は、ほっと息をついて、そうして漸く肩の力を抜いたようだった。
「…ちゃんと、横尾先生に送ってもらえ」
え、と思う。だって、横尾先生は担任でもなんでもないのに……。
「多分、横尾先生が送るって言って聞かないと思うから」