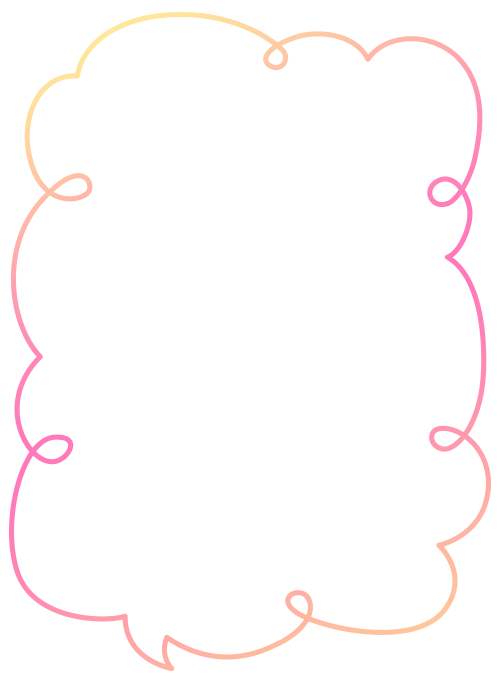暗闇の空間の向こうで、誰かが話をしている。話をしている、ということは、そこに居るのは一人ではない。ぼんやりと、誰だろう、と思った。
体中がだるくて仕方ない。重たい腕や足は思うように力が入らず、かろうじて深呼吸だけは出来た。ほう…、と深い息を吐き出して、やはり重たい瞼をこじ開けるようにして持ち上げる。視界が霞んで見えて、沙耶は苦しくて少し泣いたのかもしれない、と分かった。瞬きをしたら、余韻の涙がひとつこめかみへと落ちていった。
クリーム色の天井を、薄い水色のカーテンが区切っている。カーテンレールから床近くまで落ちているそれは、勿論沙耶の部屋のものではない。少し、消毒用のアルコールのにおいがする。保健室だな、と分かった。
「……本当に、病院は良いのか」
「大丈夫だって言ってるでしょ。呼吸も収まったし、起きたら帰れるから。崎谷先生は、心配性ねえ」
男の人の声と、女の人の声。保健室には何度かお世話になったことがあるので、今の声の主は、崎谷先生と保健の沢渡先生だと思う。多分、今、沙耶のことを話しているんだろう。
「でも、本当にお前、何にもしてねーのかよ。倒れるなんてさ」
この声も知ってる。横尾先生だ。沙耶は開けた瞼を、重たさに耐え切れずにもう一度下ろした。体の奥に重たい鉛がぶら下がっているみたいだ。
「…してませんよ。なんで俺が岡本に悪いこと、しなきゃならないんですか」
聞いたことのない、明らかに不機嫌な崎谷先生の声。穏やかに微笑う教室での先生からは、想像の付かない声だった。
「だってよ、パニック障害ってストレスが要因のひとつなんだろ? お前がなんかしたって考えんのが、フツーじゃんよ。この場合」
「だから、してませんよ。傘に入れてもらっただけです」
「本当に、それだけかよ」
「それだけって、なんですか」
剣のある二人の声が短い言葉の応酬をしている。喧嘩腰なのが分かって、沙耶は重たい体を動かそうとした。でも、力が入らない。
「沙耶と一緒の傘に入って、沙耶がストレスに感じるようなことを、お前が以前してんじゃねーかって言ってんだよ」
「そんなこと、してません。なんで、俺が…」
「やめなさいっ、二人とも。ここは保健室なんだから、静かに…」
沢渡先生が仲裁に入ったタイミングで、沙耶はこほんと咳をしてしまった。無理に体を動かそうとして、とっさに上手に呼吸が出来なかったのだ。
体中がだるくて仕方ない。重たい腕や足は思うように力が入らず、かろうじて深呼吸だけは出来た。ほう…、と深い息を吐き出して、やはり重たい瞼をこじ開けるようにして持ち上げる。視界が霞んで見えて、沙耶は苦しくて少し泣いたのかもしれない、と分かった。瞬きをしたら、余韻の涙がひとつこめかみへと落ちていった。
クリーム色の天井を、薄い水色のカーテンが区切っている。カーテンレールから床近くまで落ちているそれは、勿論沙耶の部屋のものではない。少し、消毒用のアルコールのにおいがする。保健室だな、と分かった。
「……本当に、病院は良いのか」
「大丈夫だって言ってるでしょ。呼吸も収まったし、起きたら帰れるから。崎谷先生は、心配性ねえ」
男の人の声と、女の人の声。保健室には何度かお世話になったことがあるので、今の声の主は、崎谷先生と保健の沢渡先生だと思う。多分、今、沙耶のことを話しているんだろう。
「でも、本当にお前、何にもしてねーのかよ。倒れるなんてさ」
この声も知ってる。横尾先生だ。沙耶は開けた瞼を、重たさに耐え切れずにもう一度下ろした。体の奥に重たい鉛がぶら下がっているみたいだ。
「…してませんよ。なんで俺が岡本に悪いこと、しなきゃならないんですか」
聞いたことのない、明らかに不機嫌な崎谷先生の声。穏やかに微笑う教室での先生からは、想像の付かない声だった。
「だってよ、パニック障害ってストレスが要因のひとつなんだろ? お前がなんかしたって考えんのが、フツーじゃんよ。この場合」
「だから、してませんよ。傘に入れてもらっただけです」
「本当に、それだけかよ」
「それだけって、なんですか」
剣のある二人の声が短い言葉の応酬をしている。喧嘩腰なのが分かって、沙耶は重たい体を動かそうとした。でも、力が入らない。
「沙耶と一緒の傘に入って、沙耶がストレスに感じるようなことを、お前が以前してんじゃねーかって言ってんだよ」
「そんなこと、してません。なんで、俺が…」
「やめなさいっ、二人とも。ここは保健室なんだから、静かに…」
沢渡先生が仲裁に入ったタイミングで、沙耶はこほんと咳をしてしまった。無理に体を動かそうとして、とっさに上手に呼吸が出来なかったのだ。