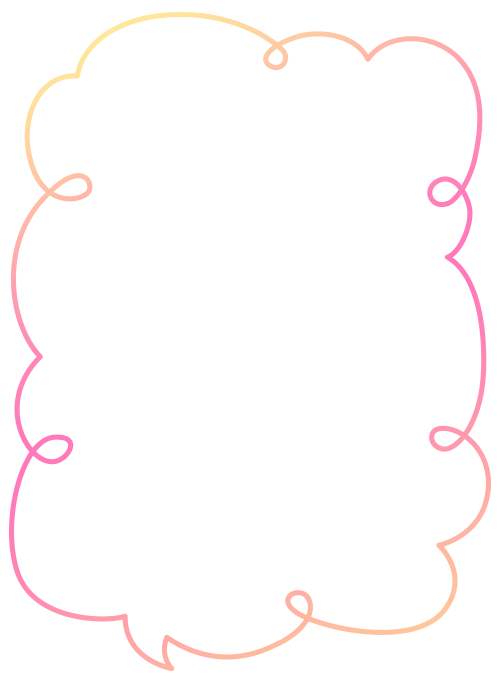「俺が持つか、岡本」
ちょっと見つめてしまっていたような気がしたので、隣から呼びかけられて、飛び上がるほどびっくりした。先生の左手が動いて、沙耶から傘の柄を取り上げてしまう。そりゃあ先生の方が背が高いからその方がいいのだろうけど、この狭い空間の中で主導権を握られてしまったような気がする。いつも先生は先生で、沙耶は生徒だから、主導権なんてあったもんじゃないけど、こんな雨の中をゴミ拾いにうろうろしている先生を放っておけなくて、助けにきてあげたのは自分なのに…、という気持ちになる。
「や…、その、…」
だって、それは自分の傘なのに、という言葉も出てこない。会話に窮した沙耶と握り拳ひとつ分だけ離れた体からは、この湿気からか、汗のにおいがした。
水のにおいの中に混じる、それ。
それは、幼馴染を入れてあげたときと、確実に違う感覚だった。
くさいとか、嫌なにおいだとか、そういうことではない。そんなの沙耶だってこの湿度に汗をかいているからお互い様だ。そんなんじゃなくて……。
「今頃帰りなんて、遅かったな」
崎谷先生が、話しかけてきてくれる。だから平静に応えなければいけない。
「…あ、図書室に寄っていたので」
「図書室?」
「…あの、…今日の授業の、復習を……」
「そうか。そりゃ、エライな」
崎谷先生が微笑って、ぽんと沙耶の頭の上に手のひらを乗せた。大きな手のひら。一層近くなる、汗のにおい。
どくん、と心臓が打つ。大きな、波だった。
「………っ」
こわい、と思った。
知らないにおい。母親でもなく父親でもなく、姉でもない。勿論クラスメイトとも優斗とも違うこのにおいが、沙耶の中に圧倒的に迫ってくるような感覚だった。
……こわい。足元に広がる崖の淵から、海の底まで落ちていってしまいそう。深海の海。右も左も分からない、心細くて不安な場所。水が纏わり付いて、動きも呼吸すらもおぼつかない。
「岡本?」
すぐ横で呼ばれて、足が竦みそうだった。でも、この感覚をなんて説明したらいいのか分からなくて、沙耶は先程よりも更に慎重に平静を装った。
「はい」
声が震えそうだった。呼吸が浅く、早くなって、まずいと思う。
「…大丈夫か、お前。なんか、顔色悪いぞ?」
先生の声が、遠くに聞こえる。指先が痺れるような感覚で包まれて、視界が利かなくなる。本当にまずい、と思ったのと、かすかに沙耶の名を呼ぶ声が聞こえたのは
多分同時で、後は暗闇に紛れて分からなくなった。