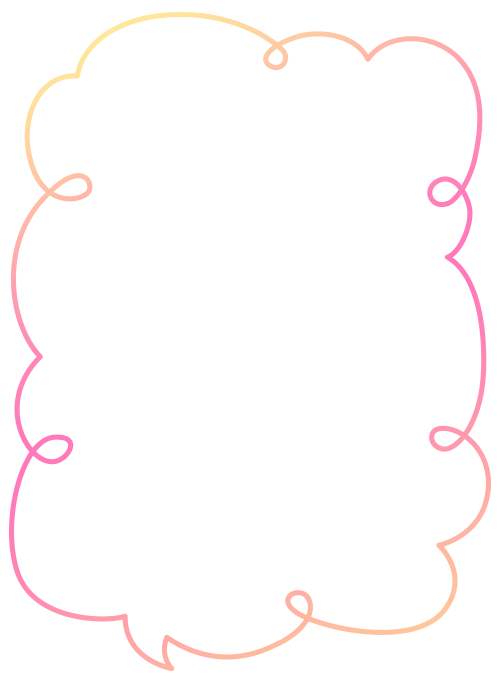「休みなのに学校に出てこなきゃなんねーのは、つまんねーだろう。昼休みに俺がジュースでもおごってやろうか」
横尾先生が、廊下の窓から腕を伸ばして、沙耶の頭をぽんぽんと撫でてくれた。励ましてもらえているんだと分かって、ちょっと嬉しい。
「ありがとうございます。でも、問題集八割解けたら、崎谷先生がジュースご馳走してくれるって」
先生って、皆おごるときはジュースなのかな、と思わず笑ってしまった。確かに手っ取り早くて、沢山ご馳走しようとしたら単価的にも妥当なんだろう。
沙耶が応えたら、横尾先生が「あんにゃろ」と呟いた。多分、崎谷先生と同じことを言ってしまったのが、面白くなかったのだろう。校内にはご馳走するものも限られているから、そんなこと思わなくてもいいのに。
「あんまり崎谷を付け上がらせるなよ?」
横尾先生が、独特の目線でそう言った。崎谷先生を付け上がらせるって、なんだろう? 崎谷先生は、何かを鼻にかけたりするような先生じゃないって、一年のときに担任を受け持ってもらった子が言っていたと思うけど。
「そういう意味じゃ、ないさ」
横尾先生は、ちら、と職員室の方へ視線をやった。でも、職員室の扉は閉められているから、何も誰も見ることは出来なかっただろう。
「? 先生?」
「いや、なんでもない。生徒に気に入られると、そいつだけを贔屓する教師も居るからな。特別にしてもらうのが、良くねーんじゃねーの? とも思うわけだよ、俺は」
生徒に気に入られると? それは立場が逆じゃないだろうか?
「そういうことだって、あるさ。教師だって人間だからな。好かれれば、嫌われるよりは嬉しいさ」
「へえ」
凄く大人の人だと思っている相手が、そんなことを思ったりすることもあるんだ。それは沙耶にとって、ちょっと意外なことだった。私生活はどうか知らないけれど、少なくとも学校ではそんなことはないんだと思っていた。