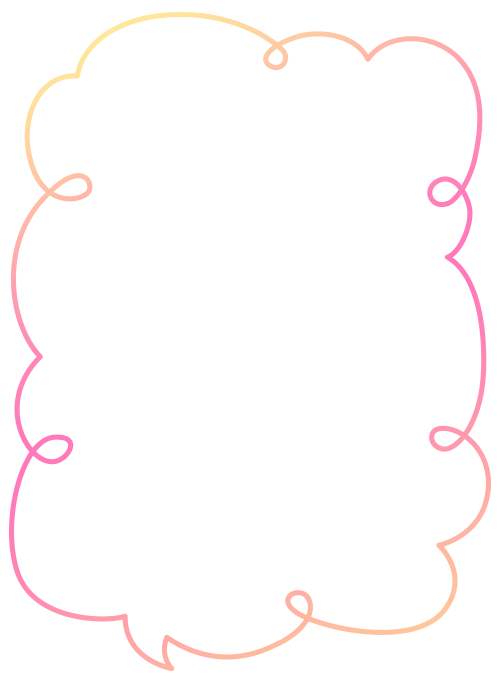雨が降る。しとしととアスファルトを濡らして、地面を真っ黒にしていく。水溜りの上になんて立っていたら、そのまま深海の海に飲み込まれてしまいそう。雨は水のにおいをつれてきて、ますます意識が水没する。
***
「…わ」
思わず呟くような小さな声が出てしまった。授業中だというのに夢まで見てしまって、なんだか黒板の方を向けない。文法を板書している古文の女性教師に握られたチョークが、硬い音を立てていた。
辺りを見渡すと、幸い沙耶の呟きに気づいた生徒は居ないようだった。それほど内に篭る呟きだったのだろう。少しほっとして、教科書の文章を目で追う。
しんとした教室に、窓の外の雨音が染み込んでくるようだった。実際は窓を開けてないから、音なんて忍び込むはずがないけれど、教室内の湿度がそう思わせていた。そう、この、水が纏わりつくような感覚。
じっとりした空間を、チャイムの音が切り裂いていく。授業の呪縛から解かれた生徒から漏れるため息で、教室内の湿度がまた上がったような気がした。
「じゃあ、今日はここまで」
先生の合図で生徒たちの気持ちが一気に緩む。教室の前の方の席から、優斗が開放感に満ち溢れた顔で近づいてきた。
「優斗ぉ、ちょっとノート見せて?」
「どうしたの。寝てた?」
「うん…。なんか、夢まで見ちゃった」
「熟睡だなあ」
正確に言うと夢は脳が起きているときに見るのだから、熟睡ではないのだけど、先生の声も板書の気配も途切れていたということは、授業中の転寝にしては熟睡だろう。
優斗は笑って自席までノートを取りに行って戻ってきてくれた。沙耶は自分のノートの、ミミズが這っているあたりからの記述を写させてもらう。一生懸命写している沙耶の横で、優斗が時々体を揺すりながら立っていた。…少し、リズミカルにも見える。
「…ゆうと?」
「ん?」
返事をした優斗は、自分が体を揺らしていたことに気づいていないようだった。なので、理由を聞くのは止めておいた。…なんとなく、いいことのような気がしたから、それなら何時か優斗も自分に話してくれるだろう。
「今日、部活は?」
「…休みだけど…」
けど、の後が消えた。やっぱり沙耶の考えは当たっていると思う。じゃあ今日は、図書室に寄ってから一人で帰ろう。
「じゃあ、また今度ね」
「……何がだよ」
多分まだクラスにも広まってないだろう。騒がれて囃し立てられると恥ずかしいって言う気持ちは良く分かるから、あんまり明確な言葉は使わない。その所為で、優斗の耳が赤いのだとしても。(だって、ちゃんと言葉にしたって、きっと赤くなるのだから)
胸の内側があたたかくなる。幼馴染の穏やかな恋を、やさしく見守ってやりたいなと思った。
***
「…わ」
思わず呟くような小さな声が出てしまった。授業中だというのに夢まで見てしまって、なんだか黒板の方を向けない。文法を板書している古文の女性教師に握られたチョークが、硬い音を立てていた。
辺りを見渡すと、幸い沙耶の呟きに気づいた生徒は居ないようだった。それほど内に篭る呟きだったのだろう。少しほっとして、教科書の文章を目で追う。
しんとした教室に、窓の外の雨音が染み込んでくるようだった。実際は窓を開けてないから、音なんて忍び込むはずがないけれど、教室内の湿度がそう思わせていた。そう、この、水が纏わりつくような感覚。
じっとりした空間を、チャイムの音が切り裂いていく。授業の呪縛から解かれた生徒から漏れるため息で、教室内の湿度がまた上がったような気がした。
「じゃあ、今日はここまで」
先生の合図で生徒たちの気持ちが一気に緩む。教室の前の方の席から、優斗が開放感に満ち溢れた顔で近づいてきた。
「優斗ぉ、ちょっとノート見せて?」
「どうしたの。寝てた?」
「うん…。なんか、夢まで見ちゃった」
「熟睡だなあ」
正確に言うと夢は脳が起きているときに見るのだから、熟睡ではないのだけど、先生の声も板書の気配も途切れていたということは、授業中の転寝にしては熟睡だろう。
優斗は笑って自席までノートを取りに行って戻ってきてくれた。沙耶は自分のノートの、ミミズが這っているあたりからの記述を写させてもらう。一生懸命写している沙耶の横で、優斗が時々体を揺すりながら立っていた。…少し、リズミカルにも見える。
「…ゆうと?」
「ん?」
返事をした優斗は、自分が体を揺らしていたことに気づいていないようだった。なので、理由を聞くのは止めておいた。…なんとなく、いいことのような気がしたから、それなら何時か優斗も自分に話してくれるだろう。
「今日、部活は?」
「…休みだけど…」
けど、の後が消えた。やっぱり沙耶の考えは当たっていると思う。じゃあ今日は、図書室に寄ってから一人で帰ろう。
「じゃあ、また今度ね」
「……何がだよ」
多分まだクラスにも広まってないだろう。騒がれて囃し立てられると恥ずかしいって言う気持ちは良く分かるから、あんまり明確な言葉は使わない。その所為で、優斗の耳が赤いのだとしても。(だって、ちゃんと言葉にしたって、きっと赤くなるのだから)
胸の内側があたたかくなる。幼馴染の穏やかな恋を、やさしく見守ってやりたいなと思った。