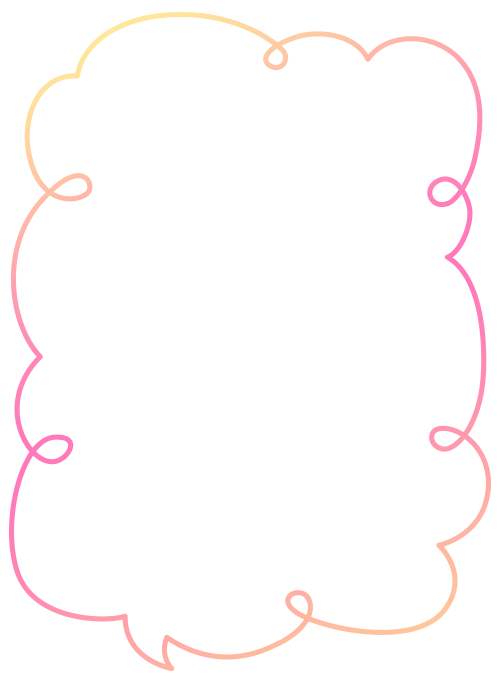「ね! 沙耶! うんって言ってくれたら、それで良いんだ! 俺、本当に本当に、沙耶に幸せになって欲しいだけなんだ!」
「そ、それはありがたいけど…、それだったら優斗だって幸せにならなきゃいけないのよ?」
沙耶が優斗の剣幕に押されながらもそう言ってやると、優斗はまた少し耳を赤くした。
「……じゃあ、俺が彼女と付き合ったら、沙耶も崎谷先生なんかと付き合わない?」
………どういう理屈で、そんな話になってしまうのだろう。
聞いていて思わずぽかんとしてしまうようなことを、優斗が言っている。そんな理屈で彼女と付き合うんじゃなくて、ちゃんと優斗も彼女を好きだから付き合うんじゃないのか。だって、耳まで赤くしているのに。
「…それは、彼女に失礼な話じゃない? そうじゃなくて、ちゃんと優斗が彼女の気持ちに応えられるかどうかって話よ?」
「応えられるよ? だから後の心配は沙耶のことだけなんだ」
沙耶は優斗の返答を聞いて、ますます混乱した。
なに? それって、優斗はちゃんと彼女を好きで、付き合う気もあって、でも沙耶が心配だから付き合えないってこと…? え? でも、なんで私なの?
どうして優斗の恋愛のカードを自分が握っているのかが分からない。でも目の前の優斗は必死だし、彼女は優斗のことが好きで告白までしていて、優斗も好きなんだったら、もう付き合ったっていいはずなのに、自分の動向がネックで付き合えないって言うのなら……。
「…よく分からないけど、…本当に優斗がどうして私にこだわるのか分からないけど、応えてあげられるなら、ちゃんと応えてあげて? 私のことは、心配要らないから」
眼差しの真剣さに、気づいたら沙耶も一生懸命応えていた。本当に、これは実るはずの恋で、自分の所為で壊れてしまっていいようなものではないはずだ。
「ホントに!? 沙耶!」
沙耶が応えると、優斗はぱっと目を輝かせた。口には安堵の笑みを浮かべて、伸びてきた腕が、沙耶の手を握っている。
「ああー、安心した! 良かったー!」
歓喜に打ち震えるって、こういう感じだろうか。兎に角優斗は、そのまま万歳でもするかというような勢いで喜んでいた。これで優斗の恋が実るのだから、沙耶としても安心だ。いつかちゃんと紹介して欲しいな、なんて、そんなことを考える。
―――足元の不安定さは、今は見ない振り。
「そ、それはありがたいけど…、それだったら優斗だって幸せにならなきゃいけないのよ?」
沙耶が優斗の剣幕に押されながらもそう言ってやると、優斗はまた少し耳を赤くした。
「……じゃあ、俺が彼女と付き合ったら、沙耶も崎谷先生なんかと付き合わない?」
………どういう理屈で、そんな話になってしまうのだろう。
聞いていて思わずぽかんとしてしまうようなことを、優斗が言っている。そんな理屈で彼女と付き合うんじゃなくて、ちゃんと優斗も彼女を好きだから付き合うんじゃないのか。だって、耳まで赤くしているのに。
「…それは、彼女に失礼な話じゃない? そうじゃなくて、ちゃんと優斗が彼女の気持ちに応えられるかどうかって話よ?」
「応えられるよ? だから後の心配は沙耶のことだけなんだ」
沙耶は優斗の返答を聞いて、ますます混乱した。
なに? それって、優斗はちゃんと彼女を好きで、付き合う気もあって、でも沙耶が心配だから付き合えないってこと…? え? でも、なんで私なの?
どうして優斗の恋愛のカードを自分が握っているのかが分からない。でも目の前の優斗は必死だし、彼女は優斗のことが好きで告白までしていて、優斗も好きなんだったら、もう付き合ったっていいはずなのに、自分の動向がネックで付き合えないって言うのなら……。
「…よく分からないけど、…本当に優斗がどうして私にこだわるのか分からないけど、応えてあげられるなら、ちゃんと応えてあげて? 私のことは、心配要らないから」
眼差しの真剣さに、気づいたら沙耶も一生懸命応えていた。本当に、これは実るはずの恋で、自分の所為で壊れてしまっていいようなものではないはずだ。
「ホントに!? 沙耶!」
沙耶が応えると、優斗はぱっと目を輝かせた。口には安堵の笑みを浮かべて、伸びてきた腕が、沙耶の手を握っている。
「ああー、安心した! 良かったー!」
歓喜に打ち震えるって、こういう感じだろうか。兎に角優斗は、そのまま万歳でもするかというような勢いで喜んでいた。これで優斗の恋が実るのだから、沙耶としても安心だ。いつかちゃんと紹介して欲しいな、なんて、そんなことを考える。
―――足元の不安定さは、今は見ない振り。