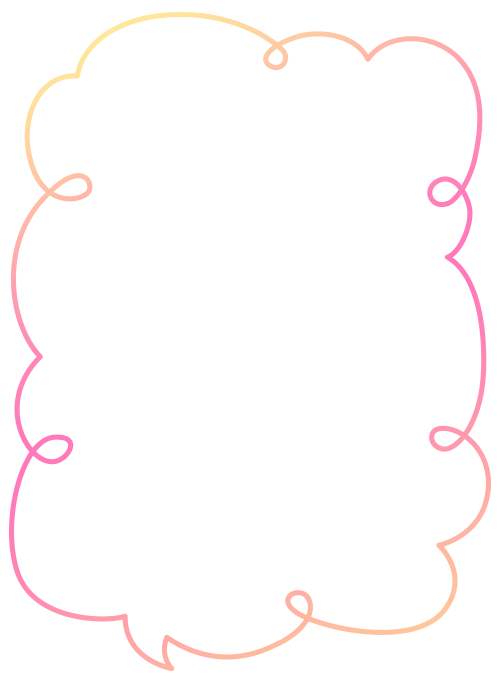駅ビルのファストフード店に、軽快なポップスが流れている。でもそれは、沙耶と優斗の頭上を、空々しく行き過ぎるばかりだった。
「だから、前から言ってたじゃん。崎谷先生は絶対沙耶のこと狙ってるって」
「…いや、ちょっと待って。彼女の話に崎谷先生は関係ないでしょ?」
沙耶は、優斗が何故気になっている彼女からの告白を受けないのか、と思っただけなのだ。そこにどうして、崎谷先生が出てくるのか、さっぱり理解できない。自分のことは言わずもがな、だ。
「幼馴染として、心配してるの。俺は」
ずずっとシェイクを啜る優斗は、沙耶の顔から視線を外さない。あまりにじっと見られるので、沙耶ですら、ちょっと居心地が悪いくらいだ。無意識に、手が髪の毛を触っていることに、沙耶は気づかなかった。
「勘違いならいいよ。でも、大人が本気出したら、俺ら高校生なんてちょろいもんじゃん。崎谷先生、あれでモテるってゆー話だし、そんな大人にしてみたら、沙耶なんて全然お手のもんだと思うし」
もー、心配で心配で仕方ないんだよ。
そう言って、優斗はテーブルに肘を付いて、ずいっと顔を寄せてきた。勿論、真剣な瞳で沙耶の目を射抜く。思わずぎょっとして、体を少し引いてしまった。
「沙耶、真面目に聞いてる?」
「や! …いや、全然真面目に聞いてるけど、……その、…優斗の方が勘違い、かな、…とか……」
「沙耶より、勘は良いよ、俺」
「…で、でも、それと彼女とは、別の話じゃない? …その、…私のことより、優斗、自分のこと考えないと……」
「だから、降って沸いた話だって言ってるじゃん」
普通は自分が異性に告白なんてされたら、幼馴染のことよりも重要なことなんじゃないのだろうか。そう沙耶は凄く思うのだけど、優斗は頑として譲らない。
「俺、本当に沙耶には幸せになって欲しいから、早く、カッコいい彼氏でも紹介して欲しいくらいだよ」
……それって、お母さんとかお父さんとか入ってない?
そう思ったけど、優斗には言わないでおいた。とても茶化すようなことを言える雰囲気ではなかったのだ。
「だから、崎谷先生なんて、以ての外なの。沙耶、頼むから崎谷先生の毒牙になんて掛からないでよ!?」
「ど…、毒牙って……」
こんな風に言われる先生もかわいそうだ。でも、やっぱり優斗が真剣なので、それも言えない。
「だから、前から言ってたじゃん。崎谷先生は絶対沙耶のこと狙ってるって」
「…いや、ちょっと待って。彼女の話に崎谷先生は関係ないでしょ?」
沙耶は、優斗が何故気になっている彼女からの告白を受けないのか、と思っただけなのだ。そこにどうして、崎谷先生が出てくるのか、さっぱり理解できない。自分のことは言わずもがな、だ。
「幼馴染として、心配してるの。俺は」
ずずっとシェイクを啜る優斗は、沙耶の顔から視線を外さない。あまりにじっと見られるので、沙耶ですら、ちょっと居心地が悪いくらいだ。無意識に、手が髪の毛を触っていることに、沙耶は気づかなかった。
「勘違いならいいよ。でも、大人が本気出したら、俺ら高校生なんてちょろいもんじゃん。崎谷先生、あれでモテるってゆー話だし、そんな大人にしてみたら、沙耶なんて全然お手のもんだと思うし」
もー、心配で心配で仕方ないんだよ。
そう言って、優斗はテーブルに肘を付いて、ずいっと顔を寄せてきた。勿論、真剣な瞳で沙耶の目を射抜く。思わずぎょっとして、体を少し引いてしまった。
「沙耶、真面目に聞いてる?」
「や! …いや、全然真面目に聞いてるけど、……その、…優斗の方が勘違い、かな、…とか……」
「沙耶より、勘は良いよ、俺」
「…で、でも、それと彼女とは、別の話じゃない? …その、…私のことより、優斗、自分のこと考えないと……」
「だから、降って沸いた話だって言ってるじゃん」
普通は自分が異性に告白なんてされたら、幼馴染のことよりも重要なことなんじゃないのだろうか。そう沙耶は凄く思うのだけど、優斗は頑として譲らない。
「俺、本当に沙耶には幸せになって欲しいから、早く、カッコいい彼氏でも紹介して欲しいくらいだよ」
……それって、お母さんとかお父さんとか入ってない?
そう思ったけど、優斗には言わないでおいた。とても茶化すようなことを言える雰囲気ではなかったのだ。
「だから、崎谷先生なんて、以ての外なの。沙耶、頼むから崎谷先生の毒牙になんて掛からないでよ!?」
「ど…、毒牙って……」
こんな風に言われる先生もかわいそうだ。でも、やっぱり優斗が真剣なので、それも言えない。