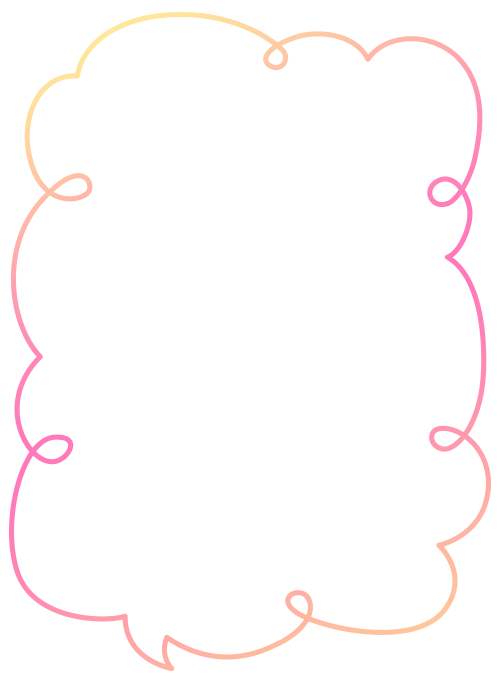焦ったように、優斗が言う。沙耶のことを一生懸命見る優斗が、本当に必死に言うので、それは嘘ではないんだろう。
「…でも、告られて、悪い気はしてない、んでしょ?」
そりゃあ、部内で話題になってしまうようなコだったら、そう告げられたときの驚きはないだろう。そう確信する沙耶に、優斗は迷って、小さく、うん…、と返事をした。
「なら…」
「だけど」
じゃあ、もう迷う必要はないじゃないか。そう言おうとした沙耶の言葉に優斗が声を被せる。
「その話は、言ってみれば降って沸いたような話だろ? それより、俺は沙耶のことの方が気になるんだ」
………は?
今、なんで自分の名前が出たんだろう?
思わず歩みが止まってしまった沙耶に、優斗は、勘違いしないでほしいんだけど、と続けた。
「沙耶の子供の頃のパンツの色まで知ってた俺が言うんだから、誓ってそういう意味じゃないけど、今、俺、沙耶の動向が心配で仕方ないんだ。新学期、クラスに慣れてきた辺りから、どーもやっぱり崎谷先生が沙耶のこと狙ってるよーに思えて仕方ないんだ。そんなの、心配じゃん。幼馴染としては。だから、正直、彼女どころじゃなくって……」
………………は?
既に止まっている足は、もう動きようがない。おまけに一生懸命に自分を見てくる優斗の視線が、がっちり沙耶の目を捉えていて、逸らしようもない。
……すみません、分からないんだけど、みつあみのコに告白された優斗が、沙耶のことを『彼女』以上に心配って、どういうことだろう?
「ああ、ホントに…。だから、あんまり言いたくなかったんけど」
まさしくこれがフリーズの見本、といったように思考停止してしまった沙耶の目の前で、優斗が大きなため息をついた。重たいそれが、足元に落ちる。
「兎に角」
優斗に腕をつかまれて、ぎょっとする。
「ここで立ち話もなんだから、やっぱ駅まで行っちゃお?」
真っ白になった沙耶のことを、優斗が腕を引いて歩いていく。さすがの運動部の力で引っ張られた沙耶は、少しよたよたしながら引き摺られていく羽目になった。