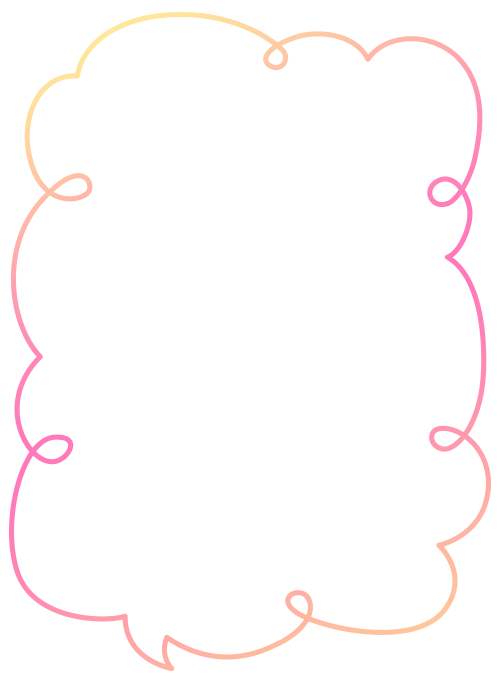「先生、もー、男子たちに言ってやってください」
「汗臭くて、敵わないの」
終礼の途端に女子に囲まれた先生は、なんだなんだと驚いていた。そりゃあ、そうだろう。しかも、先生はどっちかって言うと、男子側だと思うんだけど。案の定、
「おい、先生だって、汗掻いたらくさいと思うぞ? そりゃ、男なんだし」
と、困り顔だ。でも、先生の周りを固めた女子は諦めないらしい。先生は良い匂いがしますよ、と囲んでいた女子の一人が言った。どきりとする。
「先生、あんまり汗かかないよね?」
「あー。まあ、汗掻かない方ではあるけどな」
やっぱりー、と何故かその女子たちが納得している。なにが「やっぱり」なんだろう。いや、確かに崎谷先生は涼しい容貌をしているから、件の男子のように汗びっしょりのところなんて、思い浮かばないけれど。
「先生だったら、汗かいてもカッコイイよね」
ねー! と盛り上がる女子を、崎谷先生が諌める。
「そういう、薄っぺらいことで人をけなしたりするのは、止めろ。折角一年間、同じクラスに居るんだから、もっとお互いのことを分かって欲しいと、先生は思うぞ」
折角いいことを言ったのに、おお、なんか先生っぽいこと言ったな、俺! とか、自分で茶化している。それがなんとなく勿体無いような気がした。でも、それがないと、崎谷先生じゃないような気がするし、それがあるから、親しみやすい雰囲気も出てくるのかもしれない。
「まー、あれだ。体育祭のときになってみりゃ、俺も臭いってわかるようになるって」
最後はそんな風に言って、喧嘩は程々にしろよー、と、教室を出て行ってしまった。教室内には少しさわさわとした空気が残っていたけど、先刻みたいな喧嘩腰の空気ではなくなっていた。
何というか、熱くもなりすぎず、かといって放っておくわけでもないこの距離は、崎谷先生独特のものだなあと感心する。
「汗臭くて、敵わないの」
終礼の途端に女子に囲まれた先生は、なんだなんだと驚いていた。そりゃあ、そうだろう。しかも、先生はどっちかって言うと、男子側だと思うんだけど。案の定、
「おい、先生だって、汗掻いたらくさいと思うぞ? そりゃ、男なんだし」
と、困り顔だ。でも、先生の周りを固めた女子は諦めないらしい。先生は良い匂いがしますよ、と囲んでいた女子の一人が言った。どきりとする。
「先生、あんまり汗かかないよね?」
「あー。まあ、汗掻かない方ではあるけどな」
やっぱりー、と何故かその女子たちが納得している。なにが「やっぱり」なんだろう。いや、確かに崎谷先生は涼しい容貌をしているから、件の男子のように汗びっしょりのところなんて、思い浮かばないけれど。
「先生だったら、汗かいてもカッコイイよね」
ねー! と盛り上がる女子を、崎谷先生が諌める。
「そういう、薄っぺらいことで人をけなしたりするのは、止めろ。折角一年間、同じクラスに居るんだから、もっとお互いのことを分かって欲しいと、先生は思うぞ」
折角いいことを言ったのに、おお、なんか先生っぽいこと言ったな、俺! とか、自分で茶化している。それがなんとなく勿体無いような気がした。でも、それがないと、崎谷先生じゃないような気がするし、それがあるから、親しみやすい雰囲気も出てくるのかもしれない。
「まー、あれだ。体育祭のときになってみりゃ、俺も臭いってわかるようになるって」
最後はそんな風に言って、喧嘩は程々にしろよー、と、教室を出て行ってしまった。教室内には少しさわさわとした空気が残っていたけど、先刻みたいな喧嘩腰の空気ではなくなっていた。
何というか、熱くもなりすぎず、かといって放っておくわけでもないこの距離は、崎谷先生独特のものだなあと感心する。