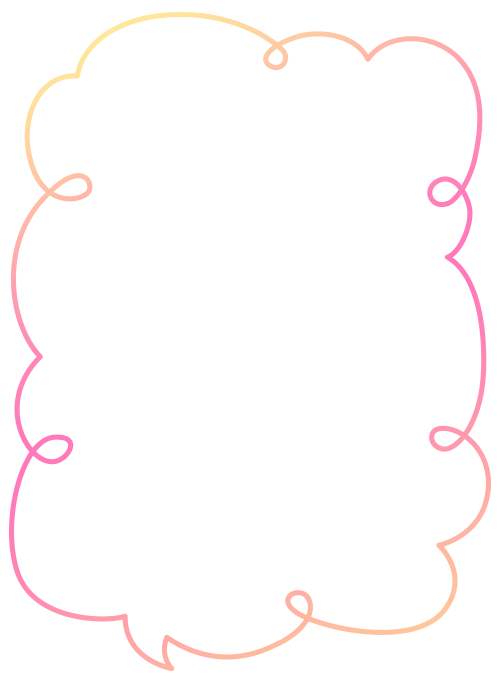翌日。午前中の授業を終えて、沙耶は優斗に誘われて購買部に向かった。いつもながら売店は混んでいて、この時期は、ちょっと人ごみが暑いくらいだ。なんとかサンドイッチをゲットした後、会計の列に並んでいると、後ろから頭をぽんと撫でられた。
「沙耶たちも買いにきてたの?」
「あ、芽衣ちゃん」
頭の上に手を置かれたままだったので、沙耶は後ろを振り返るのではなく、首を上に仰いだ。にこにこと笑っている芽衣の手にはおにぎりがひとつ。三人は仲良く会計の列に並んだ。
「今日はちょっと急いで食べような、沙耶」
「あ、そうね」
昼休み中に、優斗に昨日やってきた数学の問題集を見てもらうのだ。教室じゃ煩いだろうから、図書室に行くことにしてある。
「へえ、勉強? 頑張るわねえ」
私なんて、もう小テストなんて捨てちゃってるわよ、なんて言って芽衣が笑う。別に成績に響くわけでもない小テストだけど、崎谷先生には連休中にもお世話になっているし、出来ればあまり悲惨な点数は取りたくないな、というのが沙耶の気持ちだ。
「まあ、あんまりな点数も、なんだかなーって思って」
「良い心がけだ」
沙耶が苦手意識から苦笑いで言うと、会計の列の前の方からこちらに向かって崎谷先生が歩いてきていて、声を掛けてくれた。手には会計の済んだビニール袋が提げられている。先生は今日もお弁当を頼み損ねたようだった。
「崎谷先生」
沙耶の顔が綻ぶのと、優斗の目つきが鋭くなるのが同時だったことに、芽衣は気付いた。
「しっかり勉強してこいよ。小テスト悪かったら、また補習するからな」
「えー、またですか?」
補習、の言葉に、連休のことを思い出している二人の間に、優斗が割って入る。
「大っ丈夫です。今日、沙耶と一緒に俺が勉強しますから」
「おう、高崎。そういうお前も、気ぃ抜くなよ?」
崎谷先生が優斗に視線をやって、言う。そうなのだ。だから、なるべく優斗の負担になってはいけない。大丈夫。ゆっくりきちんと解けば間違わないって、崎谷先生が教えてくれたから、小テストのときも、そうすればいいのだ。
会計の列が動く。沙耶は一歩前に進んで、でも優斗は先生と向き合ったままだった。
「先生の思うとおりになんか、させませんから」
優斗は先生に向かってはっきりと言った。少し剣のある声に聞こえた。空気も、なんだかぴりぴりしたものになっている。