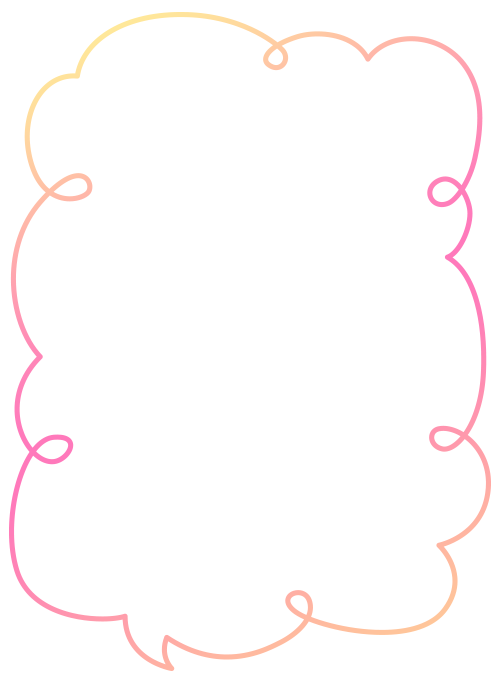◆ ◆ ◆
「けど、本当に僕を皇帝にしていいの?」
ミュラー帝国までは何日もかかる。
ゆっくりと馬車に揺られながら、僕は向かいに座る配下たちに尋ねた。
「どういうことでしょう?」
「だって、きみら本当は再建派でしょ?」
ジョナサンたちは、スタイナー帝国を転覆させるべく潜り込んでいた者たちだ。だけど、このまま行けば僕は親帝国の創建派としてミュラーで活動することになる。
だけど、ジョナサンは笑った。
「構いません。私たちは、クロード皇太子に忠誠を誓ったんです。生涯、この命尽きるまで貴方様に付いていく所存です。血なんて関係ない。私たちを友として扱ってくれ、あんな一途に人を想う……貴方様という一人の人間に惚れ込んでおります」
「ふーん、重いなぁ」
僕が率直な感想を口にすると、ジョナサンがあからさまにショックを受けた顔をする。
だけど、僕はその意見を撤回することなく、口角を上げた。
「僕、ミュラーに着いたら魔法や魔女について調べたいんだ。もちろん内政とやらにも出来るだけ取り込むつもりだけど……魔女が死なない方法を、僕は手に入れたい。サナ……姉が母みたいに短命だなんて御免だからね」
ミュラー皇国には、スタイナー帝国の残っているものよりもっと昔の文献や、また神にまつわる不思議な伝承が数多く伝わっているらしい。きっとサナはこれからも魔女であることをやめないのだろうから。彼女と繋がる理由を、一つでも掴んでやる。
「諦めてなんかやるものか」
「クロード様?」
「いや、なんでもない」
僕の独り言は誤魔化して、僕は僕の忠臣たちに利用する。
「こんなわがままにも、付き合ってもらえる?」
『はっ、もちろんです!』
声を揃える彼らに、僕は「ありがとう」と告げて。
再び、車窓から景色を眺める。遠くに森が見える。あれは、僕らが暮らしていた森だ。生い茂る木々が減っているような気がするのは……大好きな姉が魔法を失敗させてしまったせい。それを含め、大切な思い出がたくさん残っている場所。
そんな場所に、別れを告げる。
隣にもう、彼女はいない。彼女は今頃、あの騎士の隣で笑っているのだろう。あの騎士には最後に少しだけ意地悪なことを教えてあげたが、そのくらいの意地悪は許されるだろう。 僕はずるい男なのだ。
「じゃあね」
「クロード様?」
「ん。なんでもない」
もちろん寂しさはあるけれど……どうやら僕も、ひとりではないらしい。