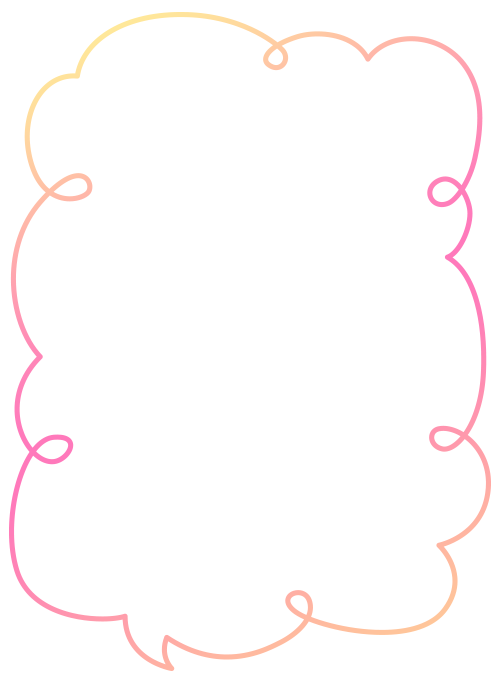クロがれっきとした大人として決めたなら、私も覚悟決めなければなりません。お姉ちゃんだからと逃げるわけにはいかない。
私は一人の女性として、本物の皇子と向き合います。
「……ごめんなさい。あなたとは結婚したくありません」
「じゃあ、その騎士は捕虜として連れて行くよ?」
「それも嫌です」
私が即答すると、皇子はクスッと笑いました。
「それはさすがにわがままじゃないかな? 国家間の契約を一人のわがままで覆すの? サナにその責任が負えるの?」
そうです。皇子の言う通りです。私のわがままで、戦争が起きるかもしれませんね。大勢の人が死に、大勢の人が悲しむことになるのかもしれない。
そんな責任、重すぎるけど……でも、それが私のせいならば。
私はまっすぐクロを見つめます。
「負います。責任取ります。もし、戦争などになってしまったら――魔女として、私が争いを止めてみせます」
「そんなこと、サナにできるわけがないよ。無謀なことを口にするのはやめなよ。サナも辛いでしょ? サナはさ、僕の隣で、何もせずに笑っていてくれるだけでいいんだよ?」
薄ら笑うクロに、私は小さく首を振りました。
「どうして……あなたはいつも『私にはできない』って言うんですか?
「だってサナは――」
「本当に、私一人だったらできないかもしれない……でも、そうしたらカミュさまに手伝ってもらいます」
私の言葉に、地面の上で胡座を掻いているカミュさまが「勝手だな」と苦笑します。
本当ですね。勝手です。でもね、私思うんだもの。カミュさまなら、きっと助けてくれるって。
だって、
「カミュさまは、私に幸せになってもらいたいんですよね? だったら私が困った時、手を貸してくれますよね?」
「あんたな……今それ言うことか?」
「言いますよ。だって、嬉しかったんです……それは、お母さんに最後に言われたことだったから」
それは、私がずっと忘れてたこと。
私は、幸せにならなきゃいけない。誰かのためじゃなくて、誰かが幸せになるためじゃなくて。
――私が、幸せにならなきゃいけない。
忘れちゃいけないんです。私の幸せを望む人が、この世界にいることを。
だけど、クロは小首を傾げます。
「だから、僕が幸せにしてあげるよ?」
「無理です。私がそばにいたいのはカミュさまです」
クロは、いつも私に「何もしなくていいよ」と言っていました。私が辛い思いをしないため。私が苦労しないため。当然それがクロの優しさだったことはわかってます。
だけど、私は出来ることが増えて嬉しかったから。
見た目を整えてみたり、お茶を淹れてみたり。いつかちゃんとお掃除したり、お裁縫も出来るようになりたいです。それこそ突拍子もない話かもしれませんが、剣を習ってみるのもいいかもしれません。
カミュさまは教えると言ってくれたから。出来るまで付き合うと言ってくださいました。だから私はあの騎士様について行きたいです。今はしてもらうことの方が多いかもしれませんが……いつか、多くのことをお返ししたいです。そして喜んでもらいたいです。
私の求める未来は、私の望む幸せな形は――そうだから。
「だからね、クロ――私たちはそろそろ姉弟離れしましょう? これ以上側にしても、お互い何も成長できないと思います」
あぁ、クロ……そんな悲しそうな顔をしないでください。私も本当は泣きたいんですよ。クロとのお別れが悲しくないわけないじゃないですか――でも、それが私たちに必要なことだと思うから。
お姉ちゃんとして、心を悪魔にするのです。
けれど、クロは「わからない」と首を振ります。
「成長って何⁉ そんなのいる? 僕に足りない点があるなら、もちろん努力する! でも僕はサナにこれ以上を求めないよ! 何回も言っている通り、サナは……サナだけでいいんだ! サナがずっと僕のそばにさえいてくれれば、僕は他に何も――」
「いい加減、醜いぞ。小僧」
割って入ってきたのはカミュさまでした。鎖の手錠を引きちぎり、自由になった手で私に下がるよう促します。いや……そんなことが出来るなら早くしてください。私がどれだけ心配を――まあ、それはあとで文句を言うことにいたしましょう。
真面目な顔でクロを見やるカミュさまを、クロは鼻で笑い飛ばしました。
「へぇ。小隊長ごときが、皇太子である僕にそんな口を利いていいんですか?」
「あんたの言った決闘が、そんな身分で結果が出るような軽薄なものでいいなら、丁重に謝罪しよう」
その言葉に、クロが固唾を呑んだのがわかりました。
カミュさまは地面に刺さっていた剣を抜きます。
「その勝敗を、今ここで着けようじゃないか。わかりやすく、剣でいいな?」
「……いいんですか? 僕は殺す気でいきますよ。あなたをここで打ち首にした所で大差ありませんから」
「もちろんだ。だけど安心しろ。俺はあんたを殺さない。外交上、陛下の顔に泥を塗るような真似はせん」
「はっ、ずいぶん舐めてくれますね」
クロは「ジョナサン、剣を」と付き人らしき人に告げます。あの付き人さん、見たことがあります。確かクロをお迎えに来ていたお友達です。
私が複雑な気持ちでいる間に、クロはカミュさまに向けて剣を構えました。それを見て、カミュさまも私に下がるように言います。
「覚悟が出来たら、あんたが合図してくれ。大丈夫だ、あんたの弟に怪我をさせるつもりはない」
「……わかりました」
私は二人の邪魔をしない位置に下がりました。ふと視線の端に、お城の角で見え隠れしている赤髪が入りました。
ありがとうございます……私のわがままに付き合ってくださって。
私ははゆっくりと息を吐き、そして――
私は一人の女性として、本物の皇子と向き合います。
「……ごめんなさい。あなたとは結婚したくありません」
「じゃあ、その騎士は捕虜として連れて行くよ?」
「それも嫌です」
私が即答すると、皇子はクスッと笑いました。
「それはさすがにわがままじゃないかな? 国家間の契約を一人のわがままで覆すの? サナにその責任が負えるの?」
そうです。皇子の言う通りです。私のわがままで、戦争が起きるかもしれませんね。大勢の人が死に、大勢の人が悲しむことになるのかもしれない。
そんな責任、重すぎるけど……でも、それが私のせいならば。
私はまっすぐクロを見つめます。
「負います。責任取ります。もし、戦争などになってしまったら――魔女として、私が争いを止めてみせます」
「そんなこと、サナにできるわけがないよ。無謀なことを口にするのはやめなよ。サナも辛いでしょ? サナはさ、僕の隣で、何もせずに笑っていてくれるだけでいいんだよ?」
薄ら笑うクロに、私は小さく首を振りました。
「どうして……あなたはいつも『私にはできない』って言うんですか?
「だってサナは――」
「本当に、私一人だったらできないかもしれない……でも、そうしたらカミュさまに手伝ってもらいます」
私の言葉に、地面の上で胡座を掻いているカミュさまが「勝手だな」と苦笑します。
本当ですね。勝手です。でもね、私思うんだもの。カミュさまなら、きっと助けてくれるって。
だって、
「カミュさまは、私に幸せになってもらいたいんですよね? だったら私が困った時、手を貸してくれますよね?」
「あんたな……今それ言うことか?」
「言いますよ。だって、嬉しかったんです……それは、お母さんに最後に言われたことだったから」
それは、私がずっと忘れてたこと。
私は、幸せにならなきゃいけない。誰かのためじゃなくて、誰かが幸せになるためじゃなくて。
――私が、幸せにならなきゃいけない。
忘れちゃいけないんです。私の幸せを望む人が、この世界にいることを。
だけど、クロは小首を傾げます。
「だから、僕が幸せにしてあげるよ?」
「無理です。私がそばにいたいのはカミュさまです」
クロは、いつも私に「何もしなくていいよ」と言っていました。私が辛い思いをしないため。私が苦労しないため。当然それがクロの優しさだったことはわかってます。
だけど、私は出来ることが増えて嬉しかったから。
見た目を整えてみたり、お茶を淹れてみたり。いつかちゃんとお掃除したり、お裁縫も出来るようになりたいです。それこそ突拍子もない話かもしれませんが、剣を習ってみるのもいいかもしれません。
カミュさまは教えると言ってくれたから。出来るまで付き合うと言ってくださいました。だから私はあの騎士様について行きたいです。今はしてもらうことの方が多いかもしれませんが……いつか、多くのことをお返ししたいです。そして喜んでもらいたいです。
私の求める未来は、私の望む幸せな形は――そうだから。
「だからね、クロ――私たちはそろそろ姉弟離れしましょう? これ以上側にしても、お互い何も成長できないと思います」
あぁ、クロ……そんな悲しそうな顔をしないでください。私も本当は泣きたいんですよ。クロとのお別れが悲しくないわけないじゃないですか――でも、それが私たちに必要なことだと思うから。
お姉ちゃんとして、心を悪魔にするのです。
けれど、クロは「わからない」と首を振ります。
「成長って何⁉ そんなのいる? 僕に足りない点があるなら、もちろん努力する! でも僕はサナにこれ以上を求めないよ! 何回も言っている通り、サナは……サナだけでいいんだ! サナがずっと僕のそばにさえいてくれれば、僕は他に何も――」
「いい加減、醜いぞ。小僧」
割って入ってきたのはカミュさまでした。鎖の手錠を引きちぎり、自由になった手で私に下がるよう促します。いや……そんなことが出来るなら早くしてください。私がどれだけ心配を――まあ、それはあとで文句を言うことにいたしましょう。
真面目な顔でクロを見やるカミュさまを、クロは鼻で笑い飛ばしました。
「へぇ。小隊長ごときが、皇太子である僕にそんな口を利いていいんですか?」
「あんたの言った決闘が、そんな身分で結果が出るような軽薄なものでいいなら、丁重に謝罪しよう」
その言葉に、クロが固唾を呑んだのがわかりました。
カミュさまは地面に刺さっていた剣を抜きます。
「その勝敗を、今ここで着けようじゃないか。わかりやすく、剣でいいな?」
「……いいんですか? 僕は殺す気でいきますよ。あなたをここで打ち首にした所で大差ありませんから」
「もちろんだ。だけど安心しろ。俺はあんたを殺さない。外交上、陛下の顔に泥を塗るような真似はせん」
「はっ、ずいぶん舐めてくれますね」
クロは「ジョナサン、剣を」と付き人らしき人に告げます。あの付き人さん、見たことがあります。確かクロをお迎えに来ていたお友達です。
私が複雑な気持ちでいる間に、クロはカミュさまに向けて剣を構えました。それを見て、カミュさまも私に下がるように言います。
「覚悟が出来たら、あんたが合図してくれ。大丈夫だ、あんたの弟に怪我をさせるつもりはない」
「……わかりました」
私は二人の邪魔をしない位置に下がりました。ふと視線の端に、お城の角で見え隠れしている赤髪が入りました。
ありがとうございます……私のわがままに付き合ってくださって。
私ははゆっくりと息を吐き、そして――