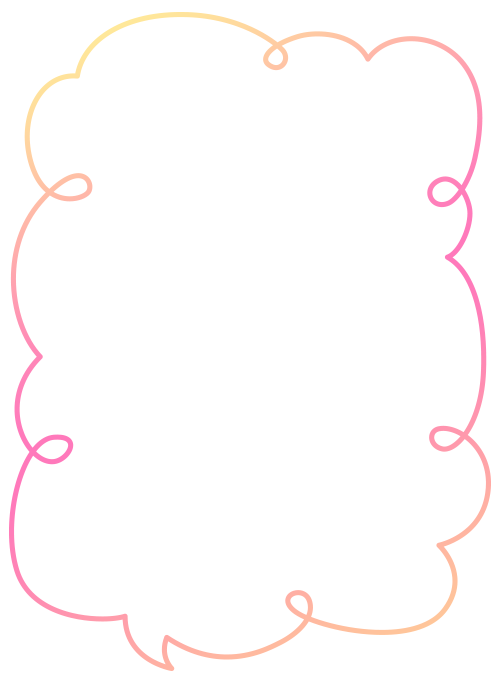「ますます、目の隈がひどい」
「……そんなことより、お茶くらいお出ししないとですよね。今レスターさんに頼んでお湯を――」
そう言われるのは、今日が初めてではありません。私は無理やり立ち上がり、カミュさまから距離を取ろうとします――が、すぐに手を掴まれてしまいました。
「昨日も眠れなかったのか?」
「……そんなことより、私のお茶を飲んでくれませんか? せっかくカミュさまから教えてもらったんですから。忘れないように毎日練習続けているんですよ」
「もう何日だ?」
「カミュさまこそ、ずいぶんお疲れのご様子ですが?」
同じようなやり取りは、毎日。今日も私は視線を逸し、返事を濁します。
だけど、珍しくカミュさまが口角をニヤリと上げました。
「近頃、俺の添い寝役が職務を放棄しているからな」
「そ、それは……!」
私は慌ててカミュさまを見るけど……続ける言葉が出てきません。
奥歯を噛み締め俯きます。
カミュさまは「手袋したままですまなかった」と手をどけて。そしてなぜか、手袋や軽鎧等、装備を外し始めました。
「カ、カミュさま……?」
「来い」
カミュさまはグイッと私の手を引きます。連れて行かれる先はベッド。「え?」と声を上げる間もなくその上に放り投げられます。このベッドもフカフカですから、痛くはありません。
だけどカミュさまのベッドの違う点は、ベッドが狭い点です。普通の一人サイズなのです。それなのに、カミュさまも堂々とベッドに上がってきます。
「今日は俺が寝かしつけてやる」
「え……で、ですが……⁉」
「なんだ? 不服か?」
「そ、そんなことは――」
ないのですが。そういうわけではないのですが!
だけどダメです。胸がとてもドキドキしてしまいます。どっちが寝かしつけようが添い寝には相違ないはずなのに……。
久々だからでしょうか。口をハクハクさせることしか出来ません。
「確か、いつもこうしてくれていたな」
そして横寝したカミュさまは、私のお腹をトントン。
ななな……なんでしょう。この――包容感とでもいうのでしょうか。大きな身体に包まれているような感覚は初めてです! これは前までのと違います!
「汗臭くないか?」
「む、むしろいい匂いです!」
「それは悪趣味すぎるだろう」
そんなことないのですよ⁉ 確かにお風呂に入っていないからでしょう、いつもより臭いは強いですが、カミュさまの匂いなんです。形容し難いですが……優しい、気遣い屋さんの匂いなんです。
チラッと上目で見ると、カミュさまがとても渋いお顔をされていました。それに思わずクスクス笑ってしまいます。本当に……本当に……なんでこんなに優しいんですか……?
「……カミュさま、子守唄は?」
「は? 俺は歌なんて知らんぞ」
「私はいつも歌ってましたよ」
「それはそうだが……」
「あれって今でも有効なんでしょうか?」
「何がだ?」
聞いておいてなんですが、少々言い難いです。私的にはありがたくもあったのですが、やはり申し訳なかったので。
それでも、カミュさまの眉間の皺が深くなってしまったので、後には引けないですよね。
「私がカミュさまの上官ってやつです」
「あー、なるほどな。子守唄も上官命令ってやつか?」
「そういうことで――あれ? でも今はカミュさまが『添い寝役』?」
はた、と気が付いてしまいました。陛下は『添い寝役』が『小隊長』よりも上官だとおっしゃいました。それなら、もしや『添い寝役』でない私は何でもない……?
私が悩んでいた時です。低く、ゆったりとした聞き覚えのあるメロディが聞こえました。ビックリして視線を向ければ、目を閉じたカミュさまが歌っているではありませんか。少し音程は外れていますが……これは、私が毎晩歌っていた曲。
私がジーッと見ていると、カミュさまが薄目を開けました。
「何だ。これが命令だろう?」
私は無理やり毛布を顔まで掛けられてしまいました。さすがに苦しいので顔だけ出すと……カミュさまのしかめられたお顔が、恥ずかしそう。
「さっさと寝ろ」
「……はい」
あぁ、本当になんて――――
私は自ら毛布を深くかぶり直し、目を閉じました。お腹を優しく叩くペースに合わせ紡がれる不器用な歌に、私が久方ぶりに夢の世界に行こうとした時です。
「どうか、幸せに……」
ねぇ、お母さん。眠る寸前でも、涙って流れるものなんですね。