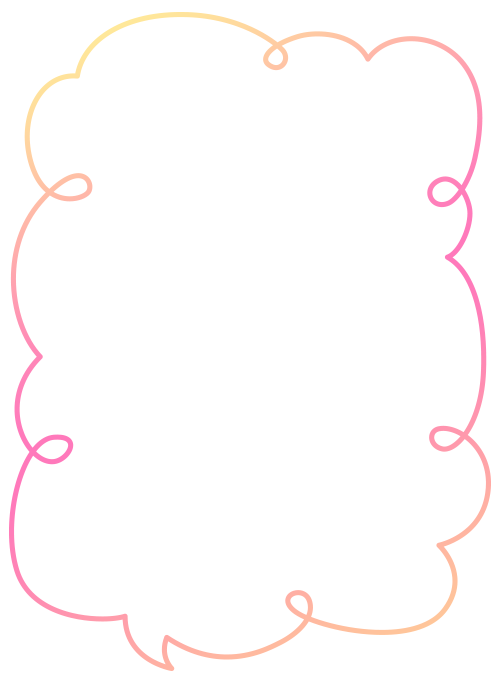◆ ◆ ◆
二人きりの時、この男は俺もことを名前で呼ぶ。
正直、男にそんな特別扱いされても、まるで嬉しくない。
「カミュさ~ん、でも意外だったっすよー」
「何がだ?」
サナを見送らせたレスターが、帰って次第ニヤニヤと話しかけてきた。
俺はフルーツサンドを呑み込んでから腑抜けた面を睨む。だけど今日に限ってレスターが笑みを崩さない。
「もちろんクロ君の決闘のことっすよー。『二度と姉さんに手を出すな』でしたっけ? いやぁ、てっきり『馬鹿なことを抜かせ』とか言って追い払うと思ったんすけどねぇ」
思い返すだけで、ため息がでる。
久々の寝不足で仕事をし、ようやく休み時間かと一息つこうかと思った時、彼はいきなりやってきた。そして『僕が勝ったあかつきには、僕らを開放してください』と来たもんだ。
いや、誰も無理やりお前らを囲ってはいないだろう。
そう突き放してやりたいが、陛下の命令がある以上、そういうわけにもいかない。彼女たちを監視するためにも、近くにいてもらわないと困る。
それに……ふと甘いパンを食べながら思う。
久々の寝不足。待ち遠しかった休憩時間。
以前ならそんなこと気にせず生活していたはずだ。常に仕事。どうせ眠れないなら、休めないならと、仕事しかしてなかった自分。
だけど休み時間には、彼女が弁当を届けに来て。
彼女に家事を教えるため、早めに家に帰り、彼女と共に眠り。そんな生活を、いつの間にか気に入っていた自分。
いつの間に、彼女らがなくてはならない存在になったのだろう。
「ところで、カミュさんはサナさんに『手を出した』んすか?」
んなわけあるか!
怒鳴りつけそうになる己をなんとか律して、厭らしい笑みを浮かべるレスターを一瞥するだけに留める。
「そ……それよりも、しっかり彼女を送り届けてきたのか?」
「それはもちろん。でもあまりに嫌がられたもんで、門のところで表向きはバイバイっす。きちんと尾行する形で屋敷まで着いていきましたけど……おれ嫌われてるんすかね~」
「遠慮しているだけだろ」
とりあえず、彼女が無事に屋敷まで帰れたなら何よりだ。彼女の顔色が悪かったのは本当だ。二日酔いだろうが、俺が席を外した間にどれだけ飲ませたんだか……あとであいつには文句を言っておかねばならんな。
そんな文句とともに渡す予定の書類が、ちょうど机の上にある。あの弟が来るまで目を通していたものだ。
内容は来週の親善パーティの警備案をまとめたもの。もとより国内の貴族と定期的に行われていた懇親会のようなものだが、前日の今日午前、急遽参加者が増えることになった。そのため警備体制も変えることになり、その報告を書いていたのである。
俺はレッドベリーの部分に齧りつきながら、ページを捲る。参加者一覧に新しく付け加えられた名前を見て、嘆息せざるえなかった。
クロード=アイネ=ミュラー。
隣国ミュラー皇国の失われた皇太子の名前。
そして、今しがた俺に決闘を申し込んできた使用人の名前だ。
俺はフルーツサンドを食べ終え、次のパンを取り出す。今度はビスケットパン。サクサクの薄いビスケット生地を乗せて焼き上げられた昔ながらのパンに齧りつくと、レスターが苦笑した。
「てか、サナさんどれだけ買ってきたんすか?」
「あと三つあるな」
「おれらにおすそ分けしてくれないんすか?」
俺は咀嚼しながら、手つかずの冷めた定食を差し出す。するとレスターは吹き出した。
「どんだけサナさんのパンを食いたいんすか!」
「例の件で胃が痛いんだ。身体が甘いものを欲している」
「真顔でつっこみどころしかないこと言わないでください! てかそのパン全部甘いやつだったんすか⁉」
「なかなかいいチョイスだな」
「お二人が意思疎通できているようでよかったっす……」
何かを諦めたレスターが、自分の席に戻ろうとする。その細身の背中を俺は呼び止めた。
「例の件はどうなった?」
それにレスターは振り返らない。
「襲撃はやっぱりパーティの日が濃厚っす。和平会議前、最後の大勝負ってことじゃないっすかね。だけどクロード皇子との繋がりが見えません。ギリギリまで調べてみますが……ねぇ、カミュさん。なにかおれらに隠していることありませんか?」
俺は部下に報告していない。
昨晩聞いた、あの弟がミュラーの皇太子であること。表向き、そんな重要人物を一介の小隊長が使用人扱いしていいはずがないのだから。
「実は残っているパンは四つある」
「……カミュさんの冗談、面白くないんすよ」
レスターが肩をすくめて「それじゃあ徹夜して調べてきまーす」と部屋を出ようとする直前。
「もしも、おれが陛下から事前に知らされていて、カミュさんが日中働いている間持ち回りでサナさんの監視をしてたら……カミュさん、怒るっすか?」
「は?」
「いやぁ、サナさんが誘拐されそうになった時のカミュさんは見ものだったっすねー。猫君に呼ばれて、街中大爆走だったじゃないですか。汗バレなくて良かったっすね」
振り返ったレスターが、にこぉと笑う。
「まぁ、冗談っすよ」
あいつ……!
本当に部屋を出ていった後、俺は机を叩きつけた。
おそらく、あいつならあの姉弟のことも調べがついているだろうと思ってはいたが……まったく、有能なやつだ。俺からの仕事もこなしつつ、有能すぎるやつだ。
俺は最後のパンを取り出しながら、今一度書類を見やる。
付け加えられた名前は、彼だけじゃなかった。
カミュ=バルバートン。自分の名前。
なんと例の皇太子からのご指名で、急遽参加することになってしまったのだ。今では忌み名のような家名だが、元は旧家。俺個人も民からの信用が厚く、陛下からの覚えがいいためパーティに参加する資格はある――と、こじつけられたらしい。
宣戦布告してきた彼の真剣な顔を思い出し、俺はもうひとつ名前を付け加えることにした。きっと面白がりの陛下は了承することだろう。
危険は覚悟の上。だけど、俺が守ればいい。下手に目を離すより、よほど安全だ。そう陛下を説き伏せよう。
だって、俺は彼女に日中も監視がついているなんて、冗談だと思っているのだから。
俺の同伴者として、書き加える名前は――――