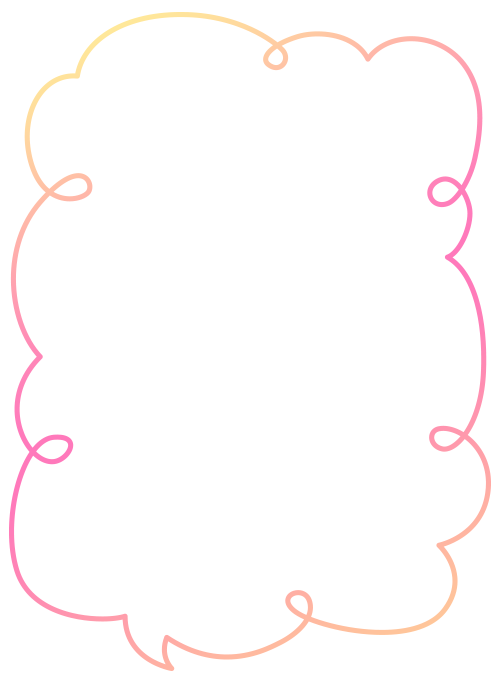◆ ◆ ◆
「馬車はやめろと、何度も言っているはずだが」
「申し訳ございません、クロード様」
僕は馬車に乗り込みながら、悪態をつく。
学校で一番に声をかけてきた同級生が、僕の第一従者となっていた。
名前はジョナサン。だけど最初に聞いたきり、一度も彼の名前を呼んだことはない。相手が名前を呼ばれることが嫌がるから。そして、呼ぶ必要もないから。
僕がひと声をあげれば、彼が一番に用を聞きにやってくる。
他にもミュラーの手の者が、あの学校には何人もいたらしい。そうして僕の護衛としてついている生徒が二人。あと御者をしている紳士が一人。護衛の二人は学校だと先輩にあたり、例に漏れず帝国内貴族の養子として学校に通っているという。御者はそのうち一人の付き人という名目だ。
どうやら、今のアルベール=デイル=スタイナー陛下の政権に納得いかない貴族が、次々とミュラー皇国と内通しているというのだ。市民格差のない社会と聞けば聞こえは良いが、元より優位だった貴族からすれば、たまったものじゃないだろう。そこに漬け込む隙を見つけたミュラーが次々と刺客を送り込んでいる状態らしい。ミュラーの正当なる後継者さえ見つかれば、正々堂々とアルベール陛下に反旗を翻し、元の『平和』なスタイナー帝国を取り戻そうと。そしてその後は、共に『平和』的な友好関係を築いていこうじゃないか、と。
僕は黙って、馬車に揺られる。
そうした思惑の渦中にいる僕としての感想はひとつだ。
まったく興味がない。
スタイナー帝国だとか。ミュラー皇国だとか。和平だとか。貴族だとか。
全部どうでもいい。
ただサナと一緒に暮らしていければ。
街の中でも。森の中でも。どこでもいい。
ずっと僕のそばで笑っていてくれた、かけがえのない人と一緒にいられれば。
国も。戦争も。王子も。魔女も。立場も。何もかも。
全部どうだっていい――そのはずなのに。
「ねぇ、愛人ってどう思う?」
腕を組みながら、指を動かすのを止められない。そんな僕の突然の質問に、ジョナサンは目を丸くしていた。
「はっ……それはクロード様がお求めであるという解釈でよろしいでしょうか?」
「いや、そういうわけじゃないんだけど……」
やっぱりそう聞こえるよね……。
我ながら突拍子すぎる発言に反省しつつ、僕は少しだけ言葉を付け足した。
「妙齢の女性がいたとして。その女性が『愛人としてでもいいからそばにいたい』という発言に、どういう意図があると思う?」
「……その質問は私への試験でしょうか」
「まぁ、そういうことでいいや」
真面目すぎるジョナサンの態度に、まるで悪いことを聞いているような気分になる。まぁ、本当に八つ当たりみたいなものなんだけど。
そしてジョナサンは固唾を呑んでから発言した。
「『私の命をあなたに捧げます』ということかと」
「重いなぁ……」
たぶん、サナの発言にそこまで深い意図はない。
だけど間違いなくそこ発言の元には『好意』という感情があり、きっと『恋慕』という感情もあるのだろう。
馬車は静かにガタガタと揺れ続ける。市街地から少し離れ、もうすぐ学校の門が見えてくるだろう。その風景を眺めていた僕の視線の端に、顔を青白くしたジョナサンの顔が映った。
「なに、どうしたの?」
「わ、私めは……従者失格でしょうか……」
「え? あぁ……」
そういえば、さっきの質問は『試験』になっちゃってたんだっけ?
この数ヶ月、彼らと行動を共にしてわかったこと。
どうもミュラー皇国の風趣はとても厳格らしい。
それこそ先程の『私の命をあなたに捧げます』という思考も、ミュラーでは結婚するなら当然のこと。当然不貞行為=神への冒涜であり、死に値する罪。だから『愛人』なんてものを持つのが許されるのも神のみ――すなわち王族のみだ。
従者も主に生涯尽くすのが当然であり、解雇すなわち死。そして従者に求められるのは、主の思考や行動を先読みし、滞りないよう配慮、準備が求められる。主に褒められることこそ最高の名誉であり、主が神に近い存在ほど自身も神に仕えるとして崇高な魂を持つ……とかなんとか語っていたような気がしたが、興味がなかったのであまり覚えていない。
だけど、僕の気まぐれに振り回されてガクブルするのは、少し可哀想だと思うから。
「そんなことない。きみの答えこそ、僕への忠誠だと受け取ったよ」
適当なことを言うと、ジョナサンの表情がぱあっと華やいだ。
「はっ! ありがたき幸せっ!」
うーん……これで涙浮かべられると、本当に悪いことしている気になるなぁ。
いつまでも慣れない優越感を呑み込むと、いよいよ学校も目の前だ。
このままでは、今日の授業はろくに集中できないだろう。
サナがあの騎士の愛人になりたいと言った。
あの騎士と共に寝るようになって数ヶ月。その『行為』に『感情』が伴ってしまっても、何も不自然はない。
わかっていた。わかっていたんだ。
いつか、こうなってしまうんじゃないかと。
良くいえば素直、悪くいえば単純な彼女だ。情が移っても仕方ない。己の感情を勘違いしても仕方ない。
ならば、僕が出来ることは――
「あのさ、お願いがあるんだけど」
「御子であるクロード様のおっしゃることなら何なりと!」
下げて上がった忠誠心が、まっすぐ僕に頭を下げてくる。
その好意を、僕は存分に利用しよう。
「昼休みに学校を抜け出して行きたい所があるんだ。連れて行ってくれる?」