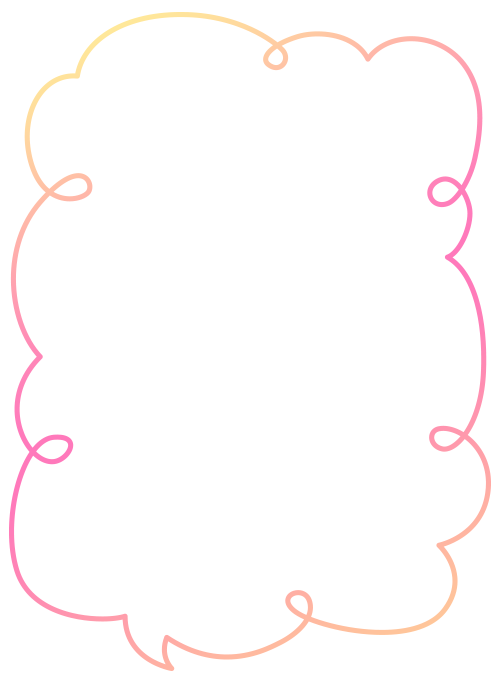◇ ◇ ◇
私はお母さんのことが大好きでした。だから、たとえ昔のことを夢見ているだけでも、とても幸せな気分なんです。
『いい、サナ。これはお母さんとの秘密だよ?』
湖の畔を散歩する時、毎回こう言っては少しだけ魔法を見せてくれました。お母さんの手の中から、真っ赤な炎が生まれるんです。
『それ!』
お母さんは魔女でした。お母さんの掛け声とともに、その炎は小さな獣の姿となって、私の周りをグルグル回ります。炎の揺らぎが、フワフワと毛並みのようです。私が思わず手を伸ばすと、
『熱いから……!』
と怒られる所までがお決まりでした。
だけど――いつの頃からか、新しいお決まりが始まってしまったのです。
ゴホゴホと、お母さんが苦しそうに咳き込みます。
『おかあさんっ、大丈夫……⁉』
私が慌てて駆け寄ると、お母さんは私をギューッと抱きしめてくれます。
『大丈夫だよ……大丈夫だから……』
何度もそう言うお母さんは、ゆっくりと息を落ち着かせて。
いつも言うのです。
『サナ……魔法を、嫌いにならないでね』
でも、幼い頃の私は思っていたのです。
魔法は素敵な力だけど、お母さんが苦しむなら……。だってそんな力があってもなくても、私はお母さんのことが大好きなのですから。
だけど、お母さんは言うのです。
『たとえどんなに無駄と思われる力でも、どんなに嫌われる力でも……生きていれば、必ず役に立つ時が来るから。自分にできることを、大切にしてね』
でもね、お母さん。
その時の私は、言っていることの意味がよくわからなかったのです。
ただ、お母さんが魔法を大切にしていたから。
そんなお母さんが大好きだったから――だから、私も魔法が使えるようになりたかったのです。
いくつになっても、私の魔法はぽんこつだけど……。
そんなことを話していると、お家の方から『ご飯が出来ましたよー』とお父さんが私たちを呼びます。片手にはまだ小さいクロと手を繋いでいました。
ご飯、という単語に、私のお腹もグーッと鳴ります。
『それじゃあ戻ろうか!』
『うん!』
いつでも抱きしめてくれるお母さんが大好きでした。
でも、幼い頃の私は――たとえどんなに苦しそうにしていたとしても、お母さんがいなくなると想像もしたことがなかったのです。
それは私が十三歳の時でした。その頃もお母さんから魔法を教わっていたのですが、一向に才能は開花せず。落ち込む私に、お父さんが『気晴らしに旅行に行きませんか』と提案してくれたのです。
楽しい家族旅行。レルモンドという街では星祭が有名で、私も一度見てみたいとずっと憧れていた場所でした。
家族四人。初めての旅行。とても楽しかったです。みんなで迷子になったり、落とし物をしたり。トラブル全部が楽しかったのを覚えています。
だけど私がお財布をお昼を食べたお店に忘れてきてしまった時です。お父さんとお母さんは今晩の宿を探してました。祭りの日だからどこも混み合っていたのです。私たち二人は荷物番をしてました。
『まったく姉さんはそそっかしいなあ。ぼくが取ってきてあげるよ!』
その当時、クロは十歳。その頃からとても頼りになる弟でした。だからこの時もお願いしたのですが……そのお店は目と鼻の先なのに、全然帰ってきません。
荷物番も大切なお仕事。だけど弟のことはもっと心配です。私は後ろ髪引かれながらも、お店に戻りました。
苦いような、酸っぱいような、独特のお酒の香り。
お店に入ると、クロは男の人に髪を引っ張られてました。
『その首の印、まさかおまえが――』
『そんなわけないだろ! 離せ、ぼくの家は――』
大変です、クロが襲われています! 私は考えるよりも先に男の人からクロを引き離そうと突撃しました。でも呆気なく吹き飛ばされてしまいます。
『姉さんっ!』
そんな私を見たクロは表情を引き締めた後、男の人の腕に噛み付きました。男の人が怯んだ隙に腕から抜け出し、私の元へ駆け寄ろうとします――が、すぐに他の人に取り押さえられました。
『せっかく無傷で引き渡そうと思ったのにな!』
そして、思いっきり頭を殴られます。ガクッとクロの首の力が抜けたのがわかりました。
『クロ……』
クロ。私の大好きなクロ。たとえ血が繋がっていなくても、私の大切な弟です。お父さんとお母さんとクロが揃ってこその家族です。
なんでクロが襲われてしまったのでしょう?
私がお財布を忘れてしまったからです。
なんでクロが殴られてしまったのでしょう?
私がクロにお財布を取りに行かせてしまったからです。
私のせいです。私のせいで、クロが……クロが……。
目が熱いです。指の先からつま先まで熱いです。まるで血が燃えているような気さえします。
その中で、最初にクロを捕まえていた人が、私を見て笑っているのがわかりました。
その時、ふと思うのです。そもそも、こんな人がいなければ良かったのでは?
『リィーリ』
なぜ、あの子の名前がわかったのか――それは未だにわかりません。だけど、ずっと私の中に眠っていたような。ずっと私に呼んでもらうことを待っていたような。そんな感覚が、ふっと溢れてきたのです。あぁ、私は魔女なんだ……なぜかそんな実感が、急に湧いたのです。
私がその名を口にすると、その人は力なく床に倒れました。気が付けば、その側には耳の長い獣がいます。無色透明。だけど、たしかに耳の長い獣が私には視えます。
あぁ……あなたが私の魔物さんですね。リィーリ、ようやく会えましたね。
だけど、感傷に浸る時間はありませんでした。
悲鳴。うるさいです。あなたもいなければ――そう思うと、リーリィが叫んでいた女の人を噛み付きました。すると、その人も倒れました。そうですね。なんていい子なんでしょう。クロを殴った人はいなくていい人。それを騒ぎ立てる人もいりませんね。ずっとずっと眠っていればいいと思います。
だって、クロも今眠っているのですから。
誰のせい? そんなの――
『あははは……あははははははははは』
リィーリが噛み付くと、みんな倒れていきます。その光景に、私は何も感じませんでした。それなのに、私はずっと笑っていました。みんなが倒れて。新しくお店に入ってきた人たちも倒れて。楽しくもないのに、私は笑っていました。みんなみんな倒れて。私だけが笑っていて。
どうしてこんなことになったのでしょう?
どうして私だけが残っているのでしょう?
あぁ、こんなお酒の匂いは嫌いだな。
わたしもみんなといっしょにねむらなくちゃ――
『サ……サナ、サナっ‼』
私が笑っていると、急にお母さんの声が聞こえました。
気がつけば、あたりが火の海です。その中で、お母さんが私の名前を呼びながらも、苦しそうに咳き込んでいます。
あ、お母さん。具合悪いのですか?
今、みんなでねんねしようとしているのです。おかあさんもやすみますか? いっしょにねむりましょう?
私がお願いすると、リィーリは――――
◇ ◇ ◇
当時の記憶が、私にはなかったのに。
うっすらと覚えているのは、炎の中で眠るお母さんの寝顔だけだったのに。
「どうして今になって……思い出してしまったんですか?」
私をベッドに置いたカミュさまが、ゆっくりと扉を閉めて出ていきました。
私はふかふかのベッドの上で、嗚咽しようになる唇を懸命に噛み締めます。
あとから聞いた話では、私たちは騎士の方々に助けてもらったらしいです。どうやら街中が炎に包まれて、私とクロだけが奇跡的に生き延びていたのだとか。
お母さんも、それからお父さんも。どこへ行ったのかわかりません。
私たちは孤児院に連れて行かれそうになったのですが、クロがとても嫌がったので、こっそりと逃げ出して家に帰ってきてしまいました。
そうして二人暮らしが始まったのですが……のちに知ります。
その一連の出来事は『レルモンドの大火災』と呼ばれ、炎の魔女が死に際に暴走した事件として、人々に語り継がれていることを。
なのに……どうしてこんな時に、思い出してしまうのでしょうね。
お母さんが死んだのは、魔力の欠乏によるものじゃない、と。
私が――お母さんを殺したのだと。
ねぇ、お母さん。私、好きな人ができました。
とても凛々しい、格好いい騎士さまです。
私の不出来に呆れながらも、何度も根気強くお茶の淹れ方を教えてくれました。
服装やお化粧にも気を使えるよう取り計らってくれて。
私が失敗しても、何度も注意して、挑戦させてくれる優しい人なんです。
そんな騎士さまは「私を殺せ」と命令を受けていました。
それを騎士さまは「命令とあらば」と受諾していました。
それでも――カミュさま。私はカミュさまのことが好きです。
もっと、いろんなことを教えて下さい。
お料理も。お洗濯も。そしてカミュさまのことも。
私はもっともっと知りたいのです。
そしてもっともっと、カミュさまのお役に立ちたいのです。
ねえ、お母さん。お父さん。そんな私を許してくれますか?
それとも、これは親殺しの罰なのですか?
私、生まれて初めて、好きなひとができました。
たとえ、その人に殺されるかもしれなくても。私は――――
自分から香るお酒の香りに、私は一晩中涙が止まりませんでした。