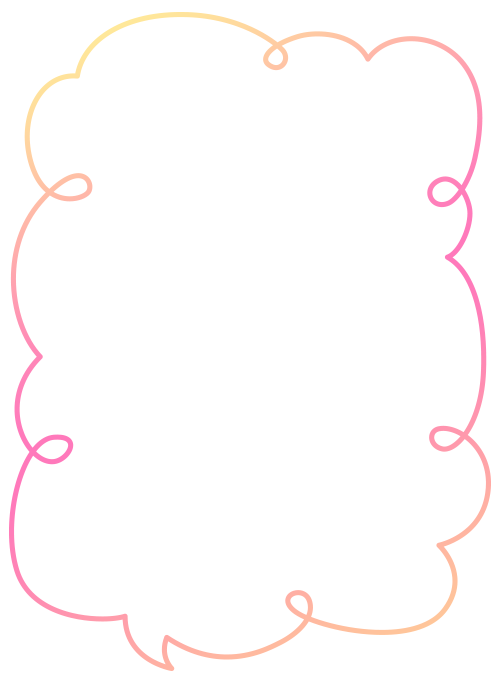◆ ◆ ◆
厨房に来ると、嫌でも思い出す。
この一ヶ月、『たかが茶淹れ』に苦戦した日々。
最初に茶淹れを教えたのは、彼女に達成感を味合わせるためだった。
自分で飲むにしろ、大好きな弟に振る舞うにしろ。自分で作ったものを『美味しい』と言われたら、誰だって嬉しいだろうから。
カップに湯を入れておく。茶葉を適量入れる。お湯を適量入れる。待ち時間にカップの湯を捨て、代わりに茶を淹れる。作業はそう難しいものでないし、選ぶ茶葉によって置く時間を変えたり、日によって茶器を変えてもいい。その作業が彼女の日々に楽しみになればいいと、そんなことを思ったりもした。厨房の勝手もわかり、今後料理をしてもらう際の架け橋となればと思ったのだ。
だが――想像以上だった。彼女が火を起こせないのはわかっていた。薪の焚べ加減がわからないのだろう。マッチを擦ることができないのだろう。下手に火事を起こされたら困る。
だけど、毎晩茶器を割られるとは思っていなかった。お湯をこぼし、猫をヤケドさせそうになるとは思わなかった。茶葉をひっくり返すだけでなく『オリジナルブレンドです!』と全量混ぜられてしまうと思わなかった。一応、それなりの値段する茶葉を揃えておいたんだぞ? それに茶器だって、古いものとはいえアンティークだ。多少壊される覚悟はしていたが、あれだけあったのにまさか買い足すはめになるとは思わなかった。当然、安価なものにさせてもらった。
「ははっ」
毎晩きゃーきゃー騒ぐ彼女を思い出すたびに、笑ってしまう。剣を振るい、命を掛けるわけではない。それなのに、あんなに本気になったのはいつぶりだっただろう。
「みゃあ!」
俺についてきた猫が鳴く。まったく、俺がやった首輪をいつも着けやがって。
とりあえず猫にミルクをやり、俺は陛下と彼女に出すつまみを考える。彼女の期待に満ちた目に応えて、手の混んだものを作ってもいいが……。下手に格の違いを見せるのも気が引ける。
「陛下に下手なこと吹き込まれても困るしな」
「にゃ!」
彼女の猫の同意も得られたところで、俺は手早く出来そうなものを探す。
そして急いで正解だった。
「で、なんでこいつは陛下の足の間で寝ているんですか?」
「どうせなら、もうちょっと色気のある体勢で寝て欲しかったよねぇ」
俺がソーセージやチーズの燻製を炙って戻ってみれば、俺の添い寝係がアルベール皇帝陛下を椅子にして眠っていた。
……いつのまにそんな偉くなったんだ?
だけど椅子にされている当人は、まるで気にしないように話題を変える。
「ギギちゃんはちゃんとミルク貰えたかあ?」
「みゃあ」
「そいつオスですよ」
「え、そうなの? 興が冷めるなぁ。じゃあ差し詰めサナちゃんの騎士ってことか」
動物にまで女を求めるな。
そう罵りたい気持ちをグッと堪えていると、俺の足下にいた黒猫は飼い主の膝の上へと帰っていった。
そうだ、お前はいい子だな。
だから赤いデカいやつ、お前も帰れ。
だけど、俺の祈りがこいつに届いた試しはない。
「それで? お前はこの子に気があるの?」
「……俺は誰も娶る気なんかありませんよ」
阿呆か。俺が色恋と無縁だなんて、お前が一番よくわかっているだろう。
俺も絨毯の上に座りながら憮然と答えてやると、陛下が大笑いしだす。
「ははっ、気が早いだろー! 誰も婚約するのかとか聞いてないぞ⁉」
「なっ……」
その時だ、タイミング悪く寝かけている彼女の寝顔がへらっと歪む。
「ほら、サナちゃんも笑ってる」
「寝てるじゃないですか。夢見ているだけでしょう、きっと」
くそ、毎夜のことながら気持ちよさそうに寝やがって。髪の毛を食べているから取ってやると、陛下がニヤリと口角を上げる。
「でも、彼女のこと気に入っているんだな」
お前が無理やり押し付けたくせに、何を言ってるんだか。
それでも、俺は皮肉を口にしなかった。彼女から貰った言葉が脳裏から離れないから。
「……あなた出会えて良かった、と真っ向から言われたことがありますか?」
「すごい口説き文句だな。でも、俺もいつも言われているぞ――でっぷりなオッサンたちに」
「社交辞令の話ではなくてですね」
「あぁ、わかっているよ」
そうだ、社交辞令じゃないだろう。無駄に人の裏表を多く見てきた分、嫌でも機微になる。
貴族の恥さらしだと蔑まれ、売国奴だと愚弄され。
親の犯した大罪が正しいことだったと――胸を張ることはできない。だけど非難する気にもなれない。
あのまま、自分も断罪されたかった。逆賊のレッテルを背負って生きるなら、何も知らぬまま死にたかった。
だけど生き延びてしまった。生き延びさせてしまった馬鹿で間抜けで鼻頭を赤くした皇帝陛下は、目元をくしゃっと歪まさせた。
「だけど、お前がそう言われたなら、俺も嬉しいよ。お前を好くのが俺だけじゃなくて、本当に嬉しい。それでこそ、就任直後にわがまま言った甲斐もあるってもんだ!」
せめて、この馬鹿な友人のために生きようと思った。こいつが望んだ命なのだから、せめてこいつの役に立てようと思った。たとえ、二度と『友』と言えなくとも。こいつのわがままがきちんと国益となるよう、ただのわがままではなく先見の明があったのだと周りに言わしめるために――努めようと思った。
だけど、何にも関係のない女が、俺と出逢えて良かったと言ってくれた。俺の存在を、肯定してくれた。
どれだけ驚いたか。
どれだけ嬉しかったか。
たぶんきっと、分不相応な場所で気持ち良さそうに寝ている彼女は、知る由とないだろう。
「俺も、初めて誰かさんのわがままに付き合わされて良かったと思いましたよ」
「おぉう、相変わらず俺の心の友は辛辣だねぇ」
「そんな俺がお好きなんでしょう?」