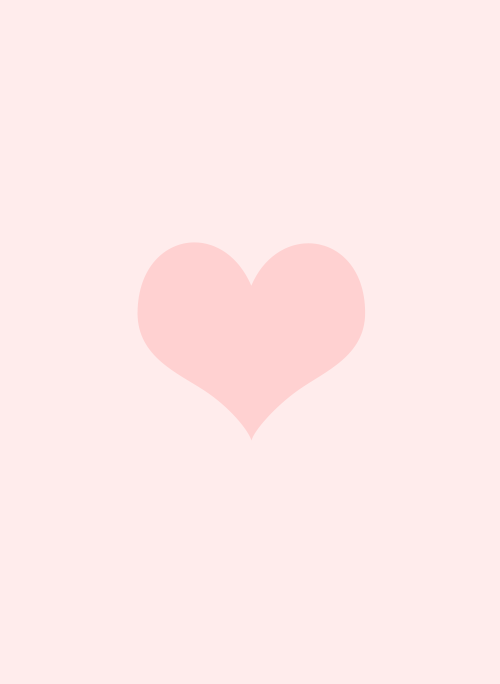わたしはずっと、幼なじみとしてハルのそばにいた。
だから。
良家の長男として物心つく前から、その家を継ぐものとしての重圧をかけられていたこと。
ハルが懸命にそれに応えようとしていたこと。
不慮事故で足を自由に動かせなくなってもなお、家のためにともがいたこと。
……そんなハルに、彼の両親含め親族が
彼を死んだものとして扱う判断をしたこと。
全部、見てきた。
『ねえ、サキ。おれ、もう死んだんだって』
『自分の足で立てないおれは、この家の一員ではないんだって。馬鹿げてるよね。』
動かない両足を地面に投げ出して、わたしを見上げてきたがらんどうな瞳を、今でも時々思い出す。
当時ほんの中学生だった彼に、残酷すぎる仕打ちをしたすべてのものが、許せなかった。
わたしだけはどんなことがあってもハルの幸せを守ろう。
そう、心に誓った。
それから高校を卒業し、介護の専門学校を出たわたしは、ヘルパーとして毎日ハルと一緒に過ごしている。