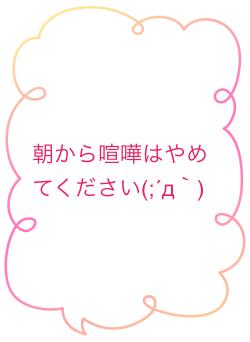「秌場くん、どうしたの?」
「...いえ。なんでもありません。」
「...やっぱり変な味するかな。」
「いいえ。美味しいです。
でも、いつもと違うのは確かです。」
「...そうなんだ。」
「あまり気にしない方がいいですよね。
河津さんにも、知られたくないこともあるでしょうから。」
「...でも、何か感じてはいるんでしょ?」
「その何かが一体どんなものなのかは分かりません。意識的に摂取しようとしなければいいだけなので安心してください。」
「...知ろうと思えば知れるの?」
「それは、人間同士のやりとりと一緒です。
どんな気持ちでいるのか、心の中は見えませんから、伝えたり、伝えてもらったりしなければ。」
「...知りたい?」
「本当は少し気になります。
僕は、河津さんの気持ちを十分に分かってあげられるわけではありません。もし、悲しいことや寂しいことだったら、1人で抱え込ませてしまうことになります。
もしそうなら、本当は力になってあげたいです。」
「...。」
やだ、そんなに真剣な顔で...。
「大丈夫。そういうのじゃないから。
秌場くんは、最近どう?悩みとかない?」
「いえ。僕は今とても幸せですよ。」
「ご飯は沢山食べてるようになったもんね。」
「はい。
わがままを言うなら、僕は、河津さんにもっともっと幸せになってもらいたいなと思います。」
「私?」
「はい。
初めて会ったときからそう思ってました。」
「私が幸せになれば、秌場くんはお腹空かなくて済むからね。」
「そうですね。
でも、もし僕が人間だったら、お腹が空いてでも河津さんのこと幸せにしたいです。」
「絶対何も食べちゃいけないって言われても?」
「はい。お腹が空くときのつらさなんて、河津さんが寂しい思いをしてしまうのに比べたらどうってことはないんですよ。」
うそだ。
そんなわけないのに。
「...いえ。なんでもありません。」
「...やっぱり変な味するかな。」
「いいえ。美味しいです。
でも、いつもと違うのは確かです。」
「...そうなんだ。」
「あまり気にしない方がいいですよね。
河津さんにも、知られたくないこともあるでしょうから。」
「...でも、何か感じてはいるんでしょ?」
「その何かが一体どんなものなのかは分かりません。意識的に摂取しようとしなければいいだけなので安心してください。」
「...知ろうと思えば知れるの?」
「それは、人間同士のやりとりと一緒です。
どんな気持ちでいるのか、心の中は見えませんから、伝えたり、伝えてもらったりしなければ。」
「...知りたい?」
「本当は少し気になります。
僕は、河津さんの気持ちを十分に分かってあげられるわけではありません。もし、悲しいことや寂しいことだったら、1人で抱え込ませてしまうことになります。
もしそうなら、本当は力になってあげたいです。」
「...。」
やだ、そんなに真剣な顔で...。
「大丈夫。そういうのじゃないから。
秌場くんは、最近どう?悩みとかない?」
「いえ。僕は今とても幸せですよ。」
「ご飯は沢山食べてるようになったもんね。」
「はい。
わがままを言うなら、僕は、河津さんにもっともっと幸せになってもらいたいなと思います。」
「私?」
「はい。
初めて会ったときからそう思ってました。」
「私が幸せになれば、秌場くんはお腹空かなくて済むからね。」
「そうですね。
でも、もし僕が人間だったら、お腹が空いてでも河津さんのこと幸せにしたいです。」
「絶対何も食べちゃいけないって言われても?」
「はい。お腹が空くときのつらさなんて、河津さんが寂しい思いをしてしまうのに比べたらどうってことはないんですよ。」
うそだ。
そんなわけないのに。