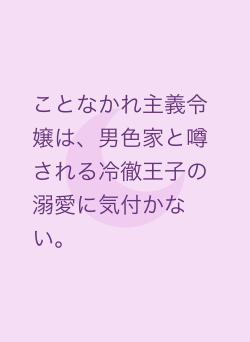帰り道、やっぱりまだ旭君の目を見られないまま。
でもこのままじゃよくないから、精一杯話題を見つけて明るく努めた。
「で、でね?その時先生が…」
「なぁ」
「え!な、何?」
「何でこっち見ねぇの?」
旭君が、真っ直ぐに私を見つめてるのが分かる。それでも、私は視線を返せない。
「別に見てるよ」
「見てねぇ」
「見てるってば」
「ちゃんと見ろ」
「っ」
旭君が立ち止まって、私の手首を掴む。また大袈裟に反応してしまったけど、旭君は離そうとはしない。
「ひまり」
「あ、あの…」
「ひまり、俺見て」
「え…っと」
「ちゃんと俺見て」
「あ…」
上目遣いに彼を見れば、少しだけ眉間にシワを寄せた表情の旭君と目が合って。
それが恥ずかしさからきてるものなんだろうなって思ったら、更に恥ずかしくなってすぐに目を逸らした。
「…ひまり」
「ご、ごめんなさい。私…」
「嫌になった?」
「え?」
「俺のこと、嫌になった?」
呟くように言われて、私はようやく真っ直ぐ顔を上げる。それだけは違うってちゃんと証明したかった。
「そんなこと、絶対ないよ!私が旭君を嫌になることなんて絶対…っ」
「じゃあ、何で?朝からずっと変じゃん」
「そ、それは…あの…」
「何」
「は、恥ずかしくて…」
ゴニョゴニョと口にする私と、微かに目を見開く旭君。
「今まで、どうやって旭君と話してたのかも分かんない…」
「何だそれ」
「だ、だって私達もうただのお隣さんじゃないから。その…私は旭君の」
「彼女」
その言葉に、ボボッと一瞬で顔に火がついた気がした。
高校生にもなってこんな反応おかしいって分かってる。
だけど今までずっと、旭君は大好きな憧れの存在で。
大袈裟に言うと芸能人とかマンガの向こうのキャラみたいな、そんな感覚で。
昨日は気持ちが通じ合ったこと凄く嬉しかったけど、今はおこがましいような分不相応なそんな気分。
まさか旭君が私を、なんて考えたこともなかったから。
私と話してくれるのは、単に幼馴染でお隣さん。それだけの理由しかないと思ってて。
凄く嬉しいはずなのに、喜んで飛び込んでいけない。
でもこのままじゃよくないから、精一杯話題を見つけて明るく努めた。
「で、でね?その時先生が…」
「なぁ」
「え!な、何?」
「何でこっち見ねぇの?」
旭君が、真っ直ぐに私を見つめてるのが分かる。それでも、私は視線を返せない。
「別に見てるよ」
「見てねぇ」
「見てるってば」
「ちゃんと見ろ」
「っ」
旭君が立ち止まって、私の手首を掴む。また大袈裟に反応してしまったけど、旭君は離そうとはしない。
「ひまり」
「あ、あの…」
「ひまり、俺見て」
「え…っと」
「ちゃんと俺見て」
「あ…」
上目遣いに彼を見れば、少しだけ眉間にシワを寄せた表情の旭君と目が合って。
それが恥ずかしさからきてるものなんだろうなって思ったら、更に恥ずかしくなってすぐに目を逸らした。
「…ひまり」
「ご、ごめんなさい。私…」
「嫌になった?」
「え?」
「俺のこと、嫌になった?」
呟くように言われて、私はようやく真っ直ぐ顔を上げる。それだけは違うってちゃんと証明したかった。
「そんなこと、絶対ないよ!私が旭君を嫌になることなんて絶対…っ」
「じゃあ、何で?朝からずっと変じゃん」
「そ、それは…あの…」
「何」
「は、恥ずかしくて…」
ゴニョゴニョと口にする私と、微かに目を見開く旭君。
「今まで、どうやって旭君と話してたのかも分かんない…」
「何だそれ」
「だ、だって私達もうただのお隣さんじゃないから。その…私は旭君の」
「彼女」
その言葉に、ボボッと一瞬で顔に火がついた気がした。
高校生にもなってこんな反応おかしいって分かってる。
だけど今までずっと、旭君は大好きな憧れの存在で。
大袈裟に言うと芸能人とかマンガの向こうのキャラみたいな、そんな感覚で。
昨日は気持ちが通じ合ったこと凄く嬉しかったけど、今はおこがましいような分不相応なそんな気分。
まさか旭君が私を、なんて考えたこともなかったから。
私と話してくれるのは、単に幼馴染でお隣さん。それだけの理由しかないと思ってて。
凄く嬉しいはずなのに、喜んで飛び込んでいけない。