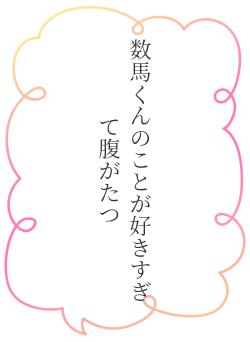それに、1つ聞きたい事があったんだ。
でも、俺は紅音にこんな事を聞いてどうするんだろう。
机に顔を伏せた。
呼んだのは俺の方なのにやっぱりいいって、なにをやっているんだろう。
紅音がズカズカと近寄ってきて正吾の机の上に勢い良く自分の鞄をバッーンと叩きつける。
正吾が驚いて顔を上げた。
「んっ……どうしたんだよ?」
「何よ、言いかけてやめないでよ!」
「ごめん……」
言いかけて止めたのは、きっと信じてもらえないだろうと思ったからだ。
「で、……何?」
「あ、聞こえた?」
「聞こえたって、何が?」
「いや、さっき女の子の声が……」
「私は、聞こえなかったよ」
紅音が不思議そうな顔をして正吾を見ている。
「そう、ならいいや」
「うん」
紅音がペットボトルのジュースをひとくち口に含みながら正吾の顔をじっと見ている。
「はい、これっ。空っぽのペットボトル、正吾にあげる!」
「うれしくないよ。こんなのもらったって……」
「ウソに決まってるじゃん。冗談だよ」
「冗談って、なんだよ……」
「だって、正吾、笑わないから。つまらないんだもん」
「つまらない、かぁ」
「正吾はまだ帰らないの?」
「うん、もうすぐ、帰る」
「一緒に帰る人がいないなら、私、途中まで一緒に帰ってあげてもいいよ」
「えっ」
「いやなら、別にいいよ」
俺の頭の中に嫌という返事は思い浮かばなかった。
「紅音と一緒に帰る」
どうしても、こんな日は絶対に1人でいたくなかったから。
紅音がこんな風に言って俺を誘ってくれたことが凄く嬉しかった。
俺は急いで帰る準備をして鞄を持とうとした。