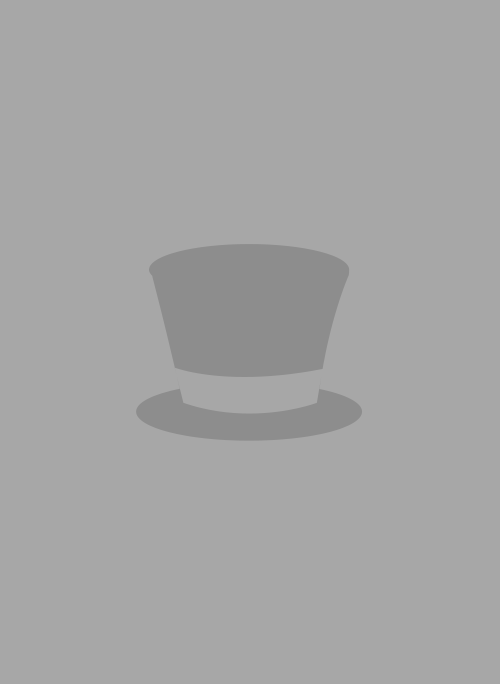山道を、軽い足取りで歩く幾多の後ろから一台の車が追い越すと、
止まった。
幾多は、ゆっくりと車に近づくと、
何も確認せずに扉を開け、中に入った。
「お疲れ様です」
幾多を迎えに来たのは、かつて幾多と長谷川が通っていた高校の先生だった。
「ご苦労様」
幾多は、助手席に深々と座り込んだ。
静かに発車した車のハンドルを握りながら、
女は口を開いた。
「幾多様…。今回は、なぜこのようなことを?」
「別に意味はないよ。ただ…」
幾多は笑い、
「正流が、こっち側に来たプレゼントのようなものさ。それに…」
「…」
女は前を向きながら、口を閉じた。
「あそこには、人の社会で生きていく資格がある者がいなかったからさ」
幾多の言葉に、女は無表情を装いながら、きいた。
「一般の人間なんて…そんなものではないですか?」
「フン」
幾多は鼻を鳴らすと、
「そんなことはない。人は素晴らしいよ」
女に笑いかけた。
「こう見えても、僕は人を信じてるんだよ。みんな…優しくなれるってね」
女はその言葉に微笑むと、
「あまり…無茶をなさらないようにして下さいね。あなた様に、もしものことがあれば…」
幾多は、女の横顔を見つめると、
ゆっくりと手を伸ばし、
女の足に指を這わした。
「心配するな。お前のような女を置いて死ぬことは、ないよ」
「い、幾多様!う、運転中です!」
女の体が、ビクッと反応した。
その瞬間、車も左右に揺れた。
「あ、危ない!」
何とかハンドルを切り、体勢を整える女の体に、指を這わせながら、
幾多は耳元で囁いた。
「別にいいだろ?2人でいるんだから…。それに」
幾多は息を吹き掛け、
「お前となら、死んでも構わないよ」
「い、幾多様!」
女は、急ブレーキを踏むと、
「ああ!」
恍惚の声を上げた。
終わり。
止まった。
幾多は、ゆっくりと車に近づくと、
何も確認せずに扉を開け、中に入った。
「お疲れ様です」
幾多を迎えに来たのは、かつて幾多と長谷川が通っていた高校の先生だった。
「ご苦労様」
幾多は、助手席に深々と座り込んだ。
静かに発車した車のハンドルを握りながら、
女は口を開いた。
「幾多様…。今回は、なぜこのようなことを?」
「別に意味はないよ。ただ…」
幾多は笑い、
「正流が、こっち側に来たプレゼントのようなものさ。それに…」
「…」
女は前を向きながら、口を閉じた。
「あそこには、人の社会で生きていく資格がある者がいなかったからさ」
幾多の言葉に、女は無表情を装いながら、きいた。
「一般の人間なんて…そんなものではないですか?」
「フン」
幾多は鼻を鳴らすと、
「そんなことはない。人は素晴らしいよ」
女に笑いかけた。
「こう見えても、僕は人を信じてるんだよ。みんな…優しくなれるってね」
女はその言葉に微笑むと、
「あまり…無茶をなさらないようにして下さいね。あなた様に、もしものことがあれば…」
幾多は、女の横顔を見つめると、
ゆっくりと手を伸ばし、
女の足に指を這わした。
「心配するな。お前のような女を置いて死ぬことは、ないよ」
「い、幾多様!う、運転中です!」
女の体が、ビクッと反応した。
その瞬間、車も左右に揺れた。
「あ、危ない!」
何とかハンドルを切り、体勢を整える女の体に、指を這わせながら、
幾多は耳元で囁いた。
「別にいいだろ?2人でいるんだから…。それに」
幾多は息を吹き掛け、
「お前となら、死んでも構わないよ」
「い、幾多様!」
女は、急ブレーキを踏むと、
「ああ!」
恍惚の声を上げた。
終わり。