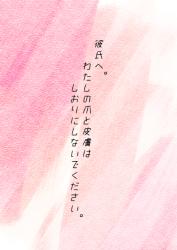わたしにできるせいいっぱいは、首を横に振ること。いやじゃない。声に出すこと。それだけだった。
「いやじゃない。……いやじゃないの、橘」
一瞬、緩んだ腕の力。
そこからするり、抜け出して。彼のほうを向いた。
縋るようにゆっくりと、伸びてくる右手。
きっと彼だったら、わたしが離れる前に抱き寄せることだって、できてしまったはずだ。
それでもしなかったのは、わたしが壊れることを、不思議なくらいに恐れているようにも思えた。
「だって紗奈ちゃん、篠山のことがすきなんじゃないの」
きつく目を閉じてから、ようやっと。目を開けた。
少し暗い教室。寄せられ、中央の上がり具合が左右で異なった眉。細められた、濡れた瞳。震えながらも、きゅっと結ばれたくちびる。