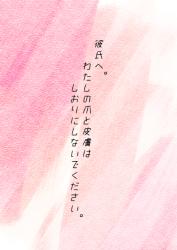ほんのすこしだけ開けていた目を閉じて、橘の睫毛を感じる。
くちびるどうしが、あつい。
離れて、目を開ける。
名残惜しそうにしてしまった自分に、くやしさまでも芽生えてきた。どうしよう。わたし、自覚しきれないほどだいすきだ。
「あ」
その音のくちのかたちのままに、とんとんと自分のくちびるを人差し指で示した橘。
言われるがままにくちをひらくと、また、キスが降りてきた。
さらに深く、熱が混ざる。
「……っ、紗奈ちゃん」
そんなに熱をわけないで。吐息を抑えるようにして呼ばないで。
「ちょうだい……っ、」
橘のぜんぶが、いつの間にか、ほしくなっていたんだ。