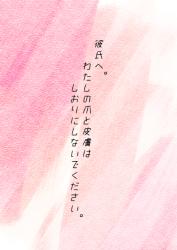ドン、と一発目の花火が上がる音がした。
校舎に隠れて姿は見えない。
わたしの存在をたしかめるようにして、あらためてゆっくりとこちらを向いた橘は。
花火の音の在処を探すようだった表情から一転し、真剣そのもので、またわたしをとらえてしまう。
「ねぇ紗奈ちゃん、キス、してほしかったの?」
「ちが、その、橘が……」
「おれが?」
目を逸らそうとするわたしから逃げ場を奪うみたいに、顔が、長い睫毛が、すこしずつちかづけられていく。
「っ、橘の、せいじゃん。キスしてきたり、そういう発言したり、する、から……」
目を閉じてしまいそう。でも、閉じられない。閉じたくない。
わたし、たいへんなわがままになっちゃった。
「紗奈ちゃん」
「──何、」
不機嫌を装ってみたって、熱はひかないし、目も逸らしきれないな。