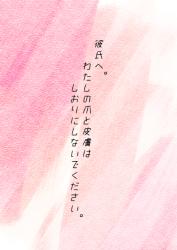*
そのあとの授業では、予想に反して、やつが大人しかった。
ご褒美なんて言っていたくらいだから、何かしてくると思ったのに。
──わたしがしてほしくてしかたなかった、みたいだな。そんなことはない。
帰り支度をしていると、わたしよりも先に終えたらしい橘が、立ち上がった。
ガタリ。その音に、思わず肩が跳ねる。
そっか、バスケ部。早く行かないとだもんね。
わたしはいままで、橘の行動のどれほどを見ていなかったのだろう。いや。見ていたうえで、どれだけが心に留まっていたのだろう。
橘のこと、断片的にしか知らない。
みんなが話していた、部活中の彼。
わたしが直接、知ったのは──わたしの隣にいるときの彼、それだけ。