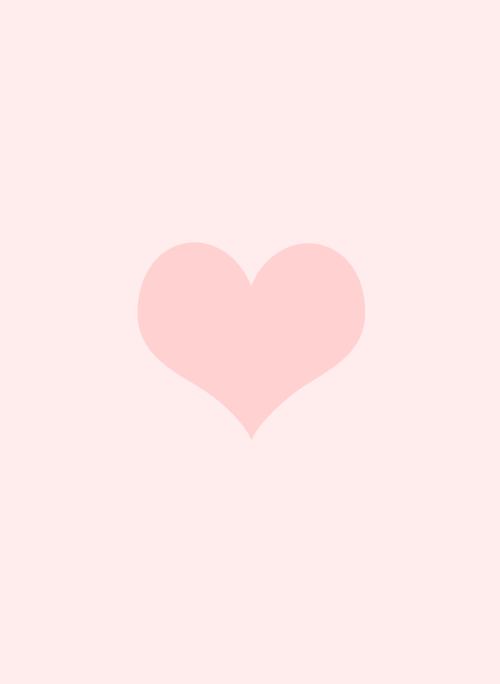・
・
・
「ごめん、冷やすのこれしかなかった」
目を冷やすためにって、律くんが冷蔵庫から取り出してくれたのは……缶ビール。
「まぁ、ないよりはいいじゃん?」
「うん、ありがとう」
もらったビールはひんやりしていて、熱い目にはぴったりの冷たさ。
目に当ててみたら、熱を持った瞼にじんわり沁みてくる……
「それ持ったままカッシーんとこ行く?」
「うん」
ビールを瞼に当てたまま、玄関で靴を履く。
私の後ろで棚から鍵を取る音が聞こえて、急いで靴を履いて先にドアを出た。
後ろから出てきた律くんが、靴をトントンしながら部屋の鍵を閉めている。
「よし、行こう」
「、」
行こうって言って、手を引くように繋がれた。
「彼女、なんでしょ?」
「うん」
「手ぐらい繋ぐもんじゃん?」
「うん…」
「なんで泣くんだよ」
「、…ごめ」
ビールで顔を隠すみたいに、涙を堪えた。
悲しいんじゃない。
怖いんじゃない。
どうしようもなく安心するだけ。
律くんの服を一方的に握っているときよりも、ずっとずっと安心するだけ。
律くんがいてくれて、本当によかった……
・
・
「ごめん、冷やすのこれしかなかった」
目を冷やすためにって、律くんが冷蔵庫から取り出してくれたのは……缶ビール。
「まぁ、ないよりはいいじゃん?」
「うん、ありがとう」
もらったビールはひんやりしていて、熱い目にはぴったりの冷たさ。
目に当ててみたら、熱を持った瞼にじんわり沁みてくる……
「それ持ったままカッシーんとこ行く?」
「うん」
ビールを瞼に当てたまま、玄関で靴を履く。
私の後ろで棚から鍵を取る音が聞こえて、急いで靴を履いて先にドアを出た。
後ろから出てきた律くんが、靴をトントンしながら部屋の鍵を閉めている。
「よし、行こう」
「、」
行こうって言って、手を引くように繋がれた。
「彼女、なんでしょ?」
「うん」
「手ぐらい繋ぐもんじゃん?」
「うん…」
「なんで泣くんだよ」
「、…ごめ」
ビールで顔を隠すみたいに、涙を堪えた。
悲しいんじゃない。
怖いんじゃない。
どうしようもなく安心するだけ。
律くんの服を一方的に握っているときよりも、ずっとずっと安心するだけ。
律くんがいてくれて、本当によかった……