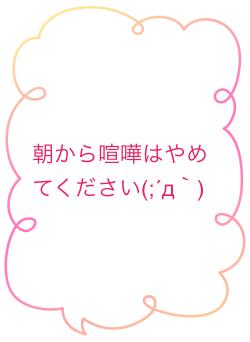次の日。
学校が終わっても、憂鬱な気分だ。
すると、
「先輩。」
廊下で上條くんに声をかけられた。
「今日委員会あったっけ?」
「いいえ。」
「そっか...。」
「今日もお見舞いに行かれるんですか?」
「え、うん...。」
「そうですか。
いつも大変ですよね。」
「大丈夫...。」
「でも、少しお疲れなんじゃないかと...。」
「え、そう見えるの?」
「はい。最近は少しそう思います。」
「まあ...中間テストとかあったから。」
「なるほど...。それに委員会、部活もお見舞いもなんて...先輩はすごいと思います。」
「そんなことないよ。」
「いえ。
何か手伝えることあったらご遠慮なく言ってください。」
...。
「優しいんだね。上條くんは。」
「え、いえ...。」
「どうして、いつもそんなに優しくしてくれるの?」
「それは...。
僕、先輩のこと...。」
「...?」
「あの、先輩のことをすごく尊敬してるというか...。本当にそう思ってるんです。先輩はそうやって言われてるの、嫌かなって思うんですけど。」
「ううん、嬉しい。」
「本当ですか?」
「うん。ありがとう。」
「...。」
「...上條くん。」
「はい。」
「でも、私、上條くんが思ってるほど素晴らしい人じゃないの。
むしろ、きっと私...。」
「僕に、是非相談してみてもらえませんか?」
「え?」
「いえ...すみません。
先輩、何か悩みがあるのかなって。」
「あ...うん、少しね...。」
「やっぱり。
悩みを持ったまま、ひたすら頑張るって辛いと思うので...。少しでもお役に立てればなって...。」
「...うん。」
学校が終わっても、憂鬱な気分だ。
すると、
「先輩。」
廊下で上條くんに声をかけられた。
「今日委員会あったっけ?」
「いいえ。」
「そっか...。」
「今日もお見舞いに行かれるんですか?」
「え、うん...。」
「そうですか。
いつも大変ですよね。」
「大丈夫...。」
「でも、少しお疲れなんじゃないかと...。」
「え、そう見えるの?」
「はい。最近は少しそう思います。」
「まあ...中間テストとかあったから。」
「なるほど...。それに委員会、部活もお見舞いもなんて...先輩はすごいと思います。」
「そんなことないよ。」
「いえ。
何か手伝えることあったらご遠慮なく言ってください。」
...。
「優しいんだね。上條くんは。」
「え、いえ...。」
「どうして、いつもそんなに優しくしてくれるの?」
「それは...。
僕、先輩のこと...。」
「...?」
「あの、先輩のことをすごく尊敬してるというか...。本当にそう思ってるんです。先輩はそうやって言われてるの、嫌かなって思うんですけど。」
「ううん、嬉しい。」
「本当ですか?」
「うん。ありがとう。」
「...。」
「...上條くん。」
「はい。」
「でも、私、上條くんが思ってるほど素晴らしい人じゃないの。
むしろ、きっと私...。」
「僕に、是非相談してみてもらえませんか?」
「え?」
「いえ...すみません。
先輩、何か悩みがあるのかなって。」
「あ...うん、少しね...。」
「やっぱり。
悩みを持ったまま、ひたすら頑張るって辛いと思うので...。少しでもお役に立てればなって...。」
「...うん。」