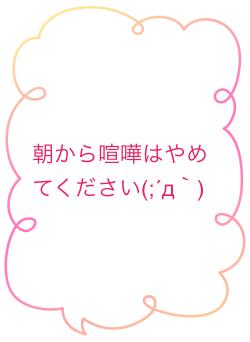「...。」
彼の目の前には、また。
お医者さまが、どんな夢を見るかと何度か
きかれるので、重い口を開き、
彼はやっと答えた。
まだ夜になると、何度か戻ってくる。
あちら側に。
上を向くと、天井に吊り上げられ、
...目が合うから。
もうそれ以上は、いえない。
...。
まだそれでもと様子をきかれるので、
パチパチと、音もすると言った。
色がみえるのは、そのような火薬が火花となって巻き上がる様子だけ。
それが、いつしか音が消えて花びらとなり、
あの子が来ていると気づくことがある。
現実には、あり得ない。
でも、幻覚にしては出来過ぎた惨劇だと思う。
そう答え、彼は目を閉じた。
また、いつかは引き戻されてしまうのだろうか。
そのような不安は口にしなかったが。
お医者さまは、薬を飲んでほしいと言った。
拒みはしない。
でも、それでも意味がないと彼は思う。
自分の頭の損傷はもう治ることはないのだから。
消えることはないから。
彼の目の前には、また。
お医者さまが、どんな夢を見るかと何度か
きかれるので、重い口を開き、
彼はやっと答えた。
まだ夜になると、何度か戻ってくる。
あちら側に。
上を向くと、天井に吊り上げられ、
...目が合うから。
もうそれ以上は、いえない。
...。
まだそれでもと様子をきかれるので、
パチパチと、音もすると言った。
色がみえるのは、そのような火薬が火花となって巻き上がる様子だけ。
それが、いつしか音が消えて花びらとなり、
あの子が来ていると気づくことがある。
現実には、あり得ない。
でも、幻覚にしては出来過ぎた惨劇だと思う。
そう答え、彼は目を閉じた。
また、いつかは引き戻されてしまうのだろうか。
そのような不安は口にしなかったが。
お医者さまは、薬を飲んでほしいと言った。
拒みはしない。
でも、それでも意味がないと彼は思う。
自分の頭の損傷はもう治ることはないのだから。
消えることはないから。