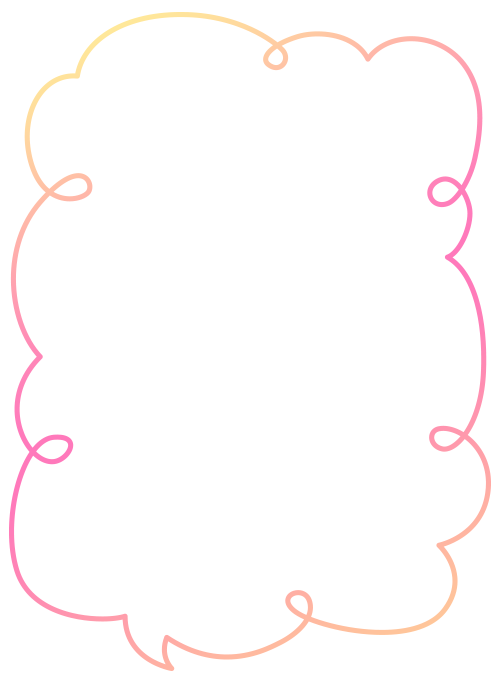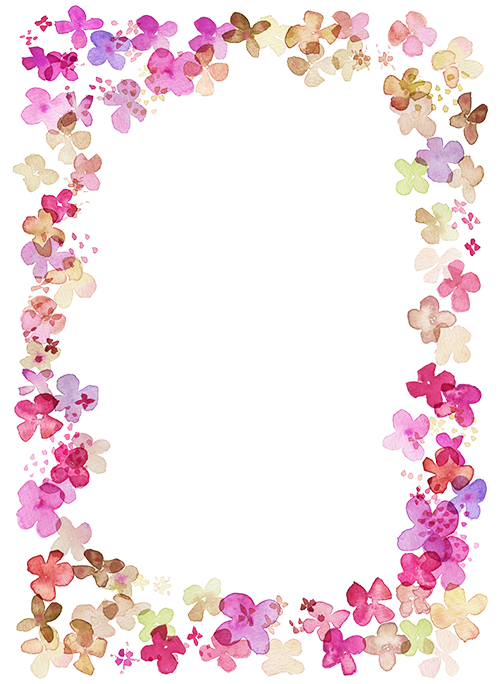「アンタさぁ、どういうつもり」
「あのっ……わたし……」
近くのトイレに連れてこられたわたしは怒っているカスミちゃんを何とか落ち着かせようと必死だった。
「アンタ、実はアイツにチクったとかないよね?」
「まさか!わたしがそんなことするはずないよ。カスミちゃんとわたしは友達でしょ?友達を裏切るような真似しないから」
必死だった。カスミちゃんをこれ以上怒らせないために必死になってゴマをする。
「ふ―ん、友達ねぇ……」
カスミちゃんが不満げにうなった。
彼女の一挙一動に神経を尖らせる。
「チクってなくても、わざとバレるようにしたってことも考えられるよね」
「ち、違う!!」
「なに慌ててんの?バレて焦ってんの?」
カスミちゃんはそう言うと、わたしの頬を平手打ちした。
パシンッという乾いた音が誰もいないし静かなトイレ内に響き渡る。
「カスミちゃ――」
名前を呼び終える間に再び飛んできた手のひらが、わたしを滅多打ちにする。