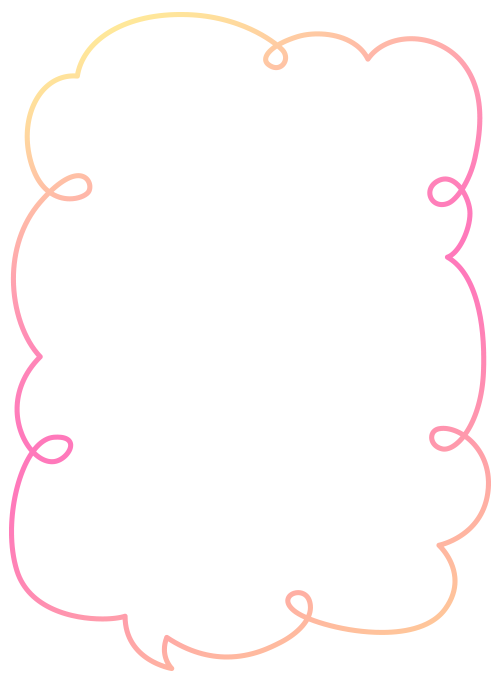最初は何をされているのか理解できなかった。でも理解したと同時に全身に鳥肌が立ち、とんでもないことをしでかしてしまったという罪悪感が体中を包み込んだ。
その日、家に帰ってきた母に泣きつき金城にされたことを話すと、母は鬼のような形相であたしの頬をひっぱったいた。
『アンタ、小学生の癖に男に色目遣うのか!気色悪い!わたしにもう近付くんじゃない!』
自分の娘に手を出した金城を母はかばった。それどころか、あたしに金城を取られたと激高した。
頼れる人間は一人もいない。大人は誰も信用ならない。
いや、自分以外の人間は信用してはならない。心も許してもいけない。
信じられるのは自分だけ。あたしは小学生ながらにそれを学んだ。
「……ハァ?テメェ、何言ってんだよ。死ねよ、クズ」
あたしは吐き捨てるように言うと、制服とバッグを掴み上げ部屋を出た。
「おー、怖い怖い。昔は可愛かったのによぉ」
クックッと喉を鳴らして嫌な笑い声をあげる金城を無視する。
たまに気が向くとふらりとこうやって家にやってくる金城にあたしは辟易していた。
「カスミ、腹減ってねぇか?最近、ちょっといいことがあって金周りがいいんだよ。飯でもいくかぁ?」
怒りと憎しみがごちゃまぜになって沸き上がってくる。
金城の言葉を無視して学校へ行く用意を済ませた頃、自分の部屋から金城のいびきが聞こえてきた。
その日、家に帰ってきた母に泣きつき金城にされたことを話すと、母は鬼のような形相であたしの頬をひっぱったいた。
『アンタ、小学生の癖に男に色目遣うのか!気色悪い!わたしにもう近付くんじゃない!』
自分の娘に手を出した金城を母はかばった。それどころか、あたしに金城を取られたと激高した。
頼れる人間は一人もいない。大人は誰も信用ならない。
いや、自分以外の人間は信用してはならない。心も許してもいけない。
信じられるのは自分だけ。あたしは小学生ながらにそれを学んだ。
「……ハァ?テメェ、何言ってんだよ。死ねよ、クズ」
あたしは吐き捨てるように言うと、制服とバッグを掴み上げ部屋を出た。
「おー、怖い怖い。昔は可愛かったのによぉ」
クックッと喉を鳴らして嫌な笑い声をあげる金城を無視する。
たまに気が向くとふらりとこうやって家にやってくる金城にあたしは辟易していた。
「カスミ、腹減ってねぇか?最近、ちょっといいことがあって金周りがいいんだよ。飯でもいくかぁ?」
怒りと憎しみがごちゃまぜになって沸き上がってくる。
金城の言葉を無視して学校へ行く用意を済ませた頃、自分の部屋から金城のいびきが聞こえてきた。