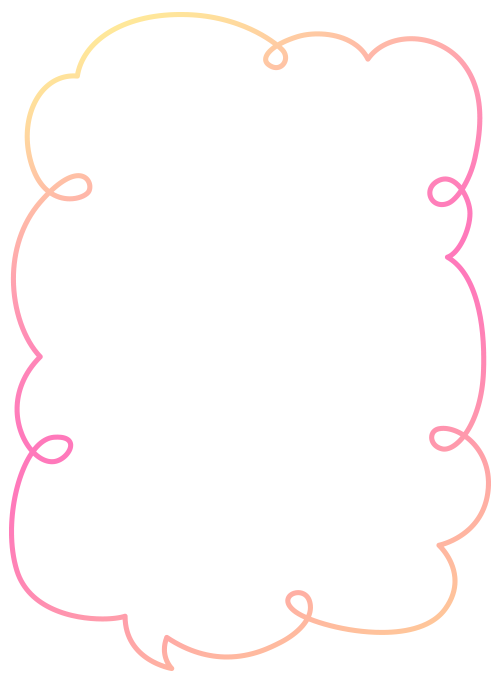金城は典型的なダメ男だった。女、酒、たばこ、ギャンブル、そのすべてに手を出した。
その思い付きと計画性のなさは折り紙付きで、身内にだけでなく知人にも借金を重ねてそのたびに夜逃げする生活を送っていたらしい。
そして、金を持つとうまいこと言い弱い人間にとんでもない利息をつけて金を貸し、ヤクザまがいの恫喝をして金を取り立てた。
そんな悪魔のような男の魔の手に落ちたのが母だった。
無職の金城を『あたしがいないとダメなのよ』とうぬぼれたことをいい、スナックで毎日深夜まで働き生活の面倒を見てあげている母も大バカ者だ。
そのくせ、男の面倒は見るくせに子供の面倒は一切みなかった。
血も涙もない母はそういう冷血な女だ。その女から生まれたあたしもその血は引いているのかもしれない。
自分の周りの誰かが例え死のうが苦しもうが別にどうだっていい。
自分以外の、いや、自分にもあまり興味はない。
ただ惰性とそのときの感情で生きているだけだ。
「なぁ、カスミ。ずいぶん、大きくなったなぁ。久しぶりに遊ぶか……?隣にこいよ?なぁ?」
金城が自分が寝転んでいる布団の隣をポンポンッと叩いた。
あたしは黙って金城を見下ろす。
小学生のとき家から帰ると常に母は不在だった。
金城とあたしの二人っきりになることも多かった。そのたびに、金城はあたしをおもちゃのようにして遊んだ。
その思い付きと計画性のなさは折り紙付きで、身内にだけでなく知人にも借金を重ねてそのたびに夜逃げする生活を送っていたらしい。
そして、金を持つとうまいこと言い弱い人間にとんでもない利息をつけて金を貸し、ヤクザまがいの恫喝をして金を取り立てた。
そんな悪魔のような男の魔の手に落ちたのが母だった。
無職の金城を『あたしがいないとダメなのよ』とうぬぼれたことをいい、スナックで毎日深夜まで働き生活の面倒を見てあげている母も大バカ者だ。
そのくせ、男の面倒は見るくせに子供の面倒は一切みなかった。
血も涙もない母はそういう冷血な女だ。その女から生まれたあたしもその血は引いているのかもしれない。
自分の周りの誰かが例え死のうが苦しもうが別にどうだっていい。
自分以外の、いや、自分にもあまり興味はない。
ただ惰性とそのときの感情で生きているだけだ。
「なぁ、カスミ。ずいぶん、大きくなったなぁ。久しぶりに遊ぶか……?隣にこいよ?なぁ?」
金城が自分が寝転んでいる布団の隣をポンポンッと叩いた。
あたしは黙って金城を見下ろす。
小学生のとき家から帰ると常に母は不在だった。
金城とあたしの二人っきりになることも多かった。そのたびに、金城はあたしをおもちゃのようにして遊んだ。