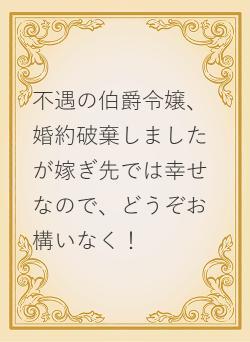その日の晩はライラさんが私の好物のクリームスープとハンバーグを作ってくれて、みんなで美味しく食べた。
「いいか、ハルナは可愛いんだからうっかり王都の路地裏とかに行ってはいけないよ?」
とか、ローライドさんにはとっても心配そうに言われた。
「ハルナ、ネコ科のオスに言い寄られてもついていかないんだよ?」
なんかちょっぴり怖い笑顔でカーライドさんに言われたりしつつの夕飯タイムだったが、最後のライラさんのニッコリ笑顔で二人は黙った。
「私たちのハルナですからね、大丈夫ですよ。ハルナ、しっかり立ち上げをお手伝いして。早めに帰ってらっしゃいね?」
うん。
この家ではライラさんが一番強いと思うので、私はその言葉にしっかり頷いて返事をした。
「うん。私この村が好きだから、早く帰ってくるね。夏より前に帰るからね!」
私の返事にライラさんは満足そうに頷いて、一緒に片付けをしてこの日珍しいことに私はライラさんと一緒に寝るという。
「可愛いハルナ、無事に帰って来てね」
私が一人暮らしをするときに送り出した母と似た雰囲気を感じて、私はギュッとライラさんに抱き着いた。
「大丈夫、ちゃんと帰ってくるからね。私、もうここの子よね?」
私は抱き着いたまま、すこし恥ずかしくって顔を上げられないままに告げた本心。
そんな私の髪を撫でて、ライラさんが囁いた。
「もちろんよ。ハルナはもう私の娘なの。だから無事に帰ってくるのよ」
その囁きに、ライラさんの腕の中で頷いた後それぞれ布団に入り手をつないで眠った。