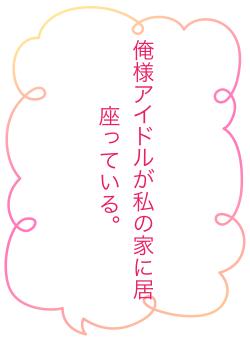「お前と話すようになってから毎日騒がしかったけど、今日が間違いなく人生一振り回されたな」
こちらを見ずに彼は続けた。
「でもなんでだろうな、全然嫌じゃない。人に頼られるのも、感謝されるのも。前は関わることすら面倒だったのに」
それは長い独り言のようで、でも確かに私に向かって言葉が紡がれているような気がした。
「変わったんだよ。いい方向に」
こちらを振り向いた。
またあの綺麗な瞳で、私のことを見つめている。
「私が変えちゃったかな」
心臓の早鐘に気付かないふりでごまかした。
次の瞬間、強く抱きしめられる。
「ゆ、夕くん!?」
「お前が教えてくれた。人と関わりたいって気持ちも、もっと相手を知りたいって気持ちも、一緒にいたいって気持ちも」
花火は上がり続けていた。
夕くんの制服はほのかにフレグランスの香りがする。
その香りが頭の中にじんわりと広がっていくような感覚。
「ありがとう」
次は何があってもやめないから。
言葉の真意を考える間もなく、唇が重なった。
それは花火のように刹那的で、星のきらめきのように永劫的だった。
突然のことに一瞬で私の体が熱を帯びる。
思考回路も今は完全に停止していた。
「ストロンチウム色。真っ赤で可愛い」
一回唇を離した彼は先ほどの答え合わせをして、私が言い訳する暇もなくまた唇が重なる。
いつもあんな遠くにある眼鏡が私の肌に当たっていた。
閉じられた瞼を見て、私もそっと目を閉じた。
「お前ら!!!!!! ここは立ち入り禁止だぞ!!!!!!」
先生の怒鳴り声が響き渡った。反射的に立ち上がり、急いで屋上を後にする。
幸いにも向こうの屋上からだった。
「危なかった。今日は間に合ったな」
笑いながら手を繋ぎ走る。
私たちは結局いつもこうだ。でも今日はいつもと違った。
しっかりと握られた手は指を絡められ、ちっとも離れそうにない。
窓の外はフィナーレを迎えた花火と歓声を上げる生徒たち。
ほんの少し感触が残る唇を想う。
夕くんとの思い出が一つ一つ、私の心の中に咲いていく。