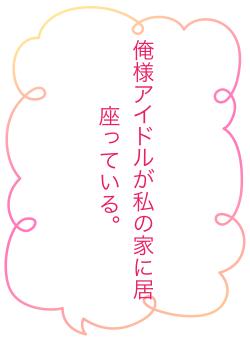後夜祭のラストは花火。
なっちゃんと校庭に向かっていた私は、後ろから腕をぐいと引っ張られた。
「夕くん」
「ついてきて。森中には言ってある」
楽しんで~と手を振ったなっちゃんは三年生の方へ消えていった。
環境の変化に対応できない私は慌ててしまう。
「どこ行くの?」
「いいところ」
全校生徒が一度に体育館から出ようとしているせいで、辺りの混雑具合は某遊園地をゆうに超えていた。
夕くんは玄関を抜けて校庭ではなく校内へ進んでいく。
花火のために消灯された学校は薄暗く気味が悪かった。
最上階まで階段を上る。
私たちの足音だけが校舎に響いた。
「入って」
ドアノブをあけると涼しい風が吹いた。屋上だ。
向かいの校舎の屋上からは話し声がするけれど、こちらの校舎には誰もいなかった。
「すごい!」
「穴場だな。誰もいないとは思わなかったけど」
はじめての屋上に興奮して、私は思わず仰向けになる。
いつもと違い今日はライトが消えているグラウンド。
夜空には星が輝いていた。
夕くんも私の横に寝ころぶ。
「ここ、誰に聞いたの? クラスの人と友達になったのは今日なのに」
そうからかったけれど、メイクを落としてもなお綺麗な顔は眉一つ動かない。
「昨日のヨーヨーの先輩、今日結局来てさ。先輩は今日花火をあっちで彼女と見てるらしい。でも毎年人が多いって言ってたから、こっちなら空いてるかもって思っただけ」
「夕くん、全然人見知りしないよね。自分から話さないだけで」
「今日は強引にしゃべらされて疲れた」
ため息をつく横顔の向こうで花火が上がり始めた。
私は起き上がって、食い入るように見つめる。
「花火って、カラフルだし綺麗なのに、儚さがいいよね」
学園祭のおまけとは思えないほど気合の入った花火が咲き乱れる様子に気圧されながら、隣の彼に話しかけた。
返事がないと思ったら、なにやら呟いている。
「カルシウム、カリウム、銅‥‥‥」
「花火の色、物質名で言われたらなんだか興ざめだよ」
「癖だから見逃して」
「どんな癖?」
この前はそんなこと言ってなかったくせに。
私は思わず笑った。つられたのか夕くんも笑う。
「学習の一環。赤の物質名は? 去年やったよ」
「‥‥‥文系だもん」
「彩、理系割と壊滅的だもんな。テスト終わるとすぐ抜けるタイプだろ」
「花火の音でなにも聞こえなーい!」
くだらないやり取りが妙にツボに入ってしまった。
ひとしきり笑った私が落ち着いたのを見計らって、彼が口を開く。
真剣な顔だった。