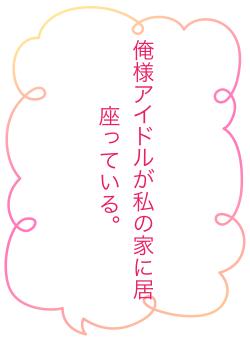左右の屋台を吟味していると、射的の前を通りかかった。
東雲くんになにかほしいものはあるか聞かれ、中段の真ん中にいたお気に入りのクマのキャラクターのぬいぐるみを指さす。
おもむろに人のよさそうなおじさんにお金を渡した彼は、おもちゃの銃を構えた。
三発五百円と、結構お高めで、一つ倒すともう一発追加らしい。
「できるの?」
「わからないけど一度やってみたかったから。見てて」
そう言った彼は一発撃つ。ぬいぐるみのお腹に当たって、少し揺れたが倒れない。
「‥‥‥なるほど」
そうつぶやくと急に机に肘をつき、本格的な構えを始めた。
その気合の入れ方におじさんもテンションが上がったのか、急に立ち上がり声援を送り出す。
「彼氏くんいいねえ! 彼女にプレゼント?」
「えっ彼女じゃ—」
「はい。いいとこ見せたいんですけど、コツとかありますか」
被せるようにそう言い放った東雲くんに驚いて声も出ない。数人だが周りの人に冷やかされる。おじさんはこりゃまいったな!と言いながらもコツを伝授していた。
いつも通りの無表情の彼の行動は唐突すぎて理解がおいつかない。
店主からコツを教わろうという作戦なのだろうが、それより彼が私の彼氏だと、嘘でも認めたことに胸の鼓動が収まらなかった。
私が悶々としていることなどつゆ知らず二発目でぬいぐるみを落とした彼は、「教えてくれたお礼です」と残り弾を消化することなく銃を返却する。
「行くぞ」
とても自然に手を繋がれる。拍手喝采の中、私たちは店の前を去った。
何が起こっているか全く理解できないまま手を引かれ歩く。
繋がれた手に視線を落とすと、男の子と手を繋いでいるという自覚がだんだんと出てきた。
いつもシャーペンを持つ指は白くて細長いのに、こんなにも力があるんだ、と変なことを考えていた。
屋台が出ていない人通りの少ない場所で手を離される。少しだけ名残惜しさを感じながら東雲くんの体温が残る手を引っ込めた。
「はい」
とれたてほやほやのぬいぐるみが無造作に差し出される。
「いいの?」
「言っただろ。お前にあげるって」
「あ、じゃあお金」
「大丈夫だから」
体に押し付けられたぬいぐるみを受け取った。私の様子を確認してから彼は近くの
ベンチに座った。私も横に腰を下ろす。
「ちょっと疲れた」
「そうだね、人多いし。ていうか、二人は?」
「完全にはぐれたな」
スマホを確認したが、連絡は来ていない。
二人は二人できっと楽しんでいるはずだ。特に連絡せずスマホを閉じる。
「なにか来てたか?」
「ううん。きっと楽しんでるから、何も送らなかった。送った方がいいかな」
「いや」
眼鏡の位置を直しながら彼は言う。
「来たら返信すればいい」
「そうだよね」
騒がしい空間にいるはずなのに、私たちの周りだけ透明な壁があると錯覚するような静けさ。
けれど前のような気まずさはなくて、むしろなんだか安心できる。
むにむにとぬいぐるみで遊んだ。
もともと可愛いキャラクターなのに、東雲くんからのプレゼントだと思うと愛しくてしょうがない。
このぬいぐるみを見るたびに私は今日のことを思い出すのだろう。
「望月」
呼ばれて顔を上げる。
「もうすぐ花火だけど、いいところを知ってるんだ。行かないか?」
「行く!」
「よし」
ん、と手を差し出された。え?と東雲くんの顔を見つめる。とりあえず手に持っていたわたあめの袋を渡す。
違う、と言いながらもふくろは逆の手に持ち替えた。
「お前まではぐれたら大変だろ」
半ば強引に手を取られ、そのまま歩き出した。
今度は横並びに歩こうと、二、三歩走る。
でもこれじゃあまるで本当にカップルみたいだ、と思ってしまった後に後悔した。
気付いてしまったらあとは緊張しかない。
その上結構な身長差があるにも関わらず同じペースで歩けているのは歩調を緩めてくれているとしか思えなくて、私の脳内は混沌を極めた。
東雲くんになにかほしいものはあるか聞かれ、中段の真ん中にいたお気に入りのクマのキャラクターのぬいぐるみを指さす。
おもむろに人のよさそうなおじさんにお金を渡した彼は、おもちゃの銃を構えた。
三発五百円と、結構お高めで、一つ倒すともう一発追加らしい。
「できるの?」
「わからないけど一度やってみたかったから。見てて」
そう言った彼は一発撃つ。ぬいぐるみのお腹に当たって、少し揺れたが倒れない。
「‥‥‥なるほど」
そうつぶやくと急に机に肘をつき、本格的な構えを始めた。
その気合の入れ方におじさんもテンションが上がったのか、急に立ち上がり声援を送り出す。
「彼氏くんいいねえ! 彼女にプレゼント?」
「えっ彼女じゃ—」
「はい。いいとこ見せたいんですけど、コツとかありますか」
被せるようにそう言い放った東雲くんに驚いて声も出ない。数人だが周りの人に冷やかされる。おじさんはこりゃまいったな!と言いながらもコツを伝授していた。
いつも通りの無表情の彼の行動は唐突すぎて理解がおいつかない。
店主からコツを教わろうという作戦なのだろうが、それより彼が私の彼氏だと、嘘でも認めたことに胸の鼓動が収まらなかった。
私が悶々としていることなどつゆ知らず二発目でぬいぐるみを落とした彼は、「教えてくれたお礼です」と残り弾を消化することなく銃を返却する。
「行くぞ」
とても自然に手を繋がれる。拍手喝采の中、私たちは店の前を去った。
何が起こっているか全く理解できないまま手を引かれ歩く。
繋がれた手に視線を落とすと、男の子と手を繋いでいるという自覚がだんだんと出てきた。
いつもシャーペンを持つ指は白くて細長いのに、こんなにも力があるんだ、と変なことを考えていた。
屋台が出ていない人通りの少ない場所で手を離される。少しだけ名残惜しさを感じながら東雲くんの体温が残る手を引っ込めた。
「はい」
とれたてほやほやのぬいぐるみが無造作に差し出される。
「いいの?」
「言っただろ。お前にあげるって」
「あ、じゃあお金」
「大丈夫だから」
体に押し付けられたぬいぐるみを受け取った。私の様子を確認してから彼は近くの
ベンチに座った。私も横に腰を下ろす。
「ちょっと疲れた」
「そうだね、人多いし。ていうか、二人は?」
「完全にはぐれたな」
スマホを確認したが、連絡は来ていない。
二人は二人できっと楽しんでいるはずだ。特に連絡せずスマホを閉じる。
「なにか来てたか?」
「ううん。きっと楽しんでるから、何も送らなかった。送った方がいいかな」
「いや」
眼鏡の位置を直しながら彼は言う。
「来たら返信すればいい」
「そうだよね」
騒がしい空間にいるはずなのに、私たちの周りだけ透明な壁があると錯覚するような静けさ。
けれど前のような気まずさはなくて、むしろなんだか安心できる。
むにむにとぬいぐるみで遊んだ。
もともと可愛いキャラクターなのに、東雲くんからのプレゼントだと思うと愛しくてしょうがない。
このぬいぐるみを見るたびに私は今日のことを思い出すのだろう。
「望月」
呼ばれて顔を上げる。
「もうすぐ花火だけど、いいところを知ってるんだ。行かないか?」
「行く!」
「よし」
ん、と手を差し出された。え?と東雲くんの顔を見つめる。とりあえず手に持っていたわたあめの袋を渡す。
違う、と言いながらもふくろは逆の手に持ち替えた。
「お前まではぐれたら大変だろ」
半ば強引に手を取られ、そのまま歩き出した。
今度は横並びに歩こうと、二、三歩走る。
でもこれじゃあまるで本当にカップルみたいだ、と思ってしまった後に後悔した。
気付いてしまったらあとは緊張しかない。
その上結構な身長差があるにも関わらず同じペースで歩けているのは歩調を緩めてくれているとしか思えなくて、私の脳内は混沌を極めた。