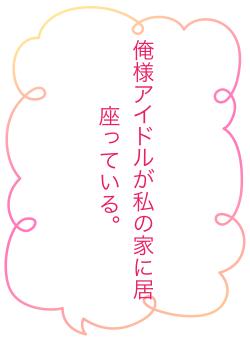クラスマッチが終わり、夏休み直前。
東雲くんと前のような距離感をなんとか取り戻した私はひとまず安堵していた。
しかし席が遠いというのは本当に話す機会がない。
更に私と東雲くんは理系クラスと文系クラスで授業も違うので、全然話せない日が続く。
……あと、誰かさんのあからさまな悪意を感じている。
「東雲くん、おは」
「彩、コミュ英の予習見せろ」
「……はいはい」
遂に命令形になった。本当に図太い性格をしている。
この間に東雲くんどっか行っちゃうし。
「あの、し」
「次古典」
「……」
こんなことがかれこれ数十回続いた。
書道の時間。
二人で周りを気にせず話せる時間。
なっちゃんや東雲くんを気にせずとも済む時間。
「耐え難いよ……」
「はあ? なんのことだよ」
「知らないふりしないでくれる!?」
あれが全部事故だっていうのか。どう足掻いてもわざとだ。
「なんだよ、俺に予習してこいって?」
「そうだよその通りだよ」
いい加減東雲くんと話したい。数学の質問もしたいし、もっと彼が知りたい。
「はあ、どうして太一の私怨に付き合わされてるんだろ」
筆を置いて紙を取り替える。
その時太一を見るとすごい顔をしていた。
「なにその顔。おもしろ」
「いや……太一って呼んだと思って……」
「自分が呼べって言ったんじゃん。忘れてたなら戻すけど」
「いや! 絶対戻すな。戻すなよ。絶対だからな」
「フリ?」
「ちげーよ」
そんなに言われると戻したくなってしまう、私のサガ。
それにしても、私はだいぶ呼び捨てしていたつもりだったが、本人の前は初めてだったか。
「……なあ」
「ん?」
「やっぱり、俺じゃダメなわけ」
「なにが」
「好きな相手」
「んん!?」
ぎょっとする。太一は机に伏せている。顔は見えない。
「……やっぱり俺彩のこと好きだ」
「……それは、どうも」
そんなに真面目な声で言うから、わからなくなる。騙されるな。相手は太一だ。
嘘だと思い込む。
ほだされてしまいそうで。
「本っ当に悔しいんだけど、俺じゃ東雲の代わりになれないのか」
「東雲くんは東雲くん。太一は太一だよ」
「……そうかよ」
そう言うと太一はいきなり起き上がり、うーんと伸びをした。
「俺も書道やるかー!」
「今そういう時間だからね」
「何書こうかな。俺とお前の相合傘でも書く?」
「小学生なの? 死んでもやめて」
「お前が好きだ!は?」
「あなたが嫌いな東雲くんの席に置いといてあげる」
「やめろ」
「こっちのセリフ」
別に嫌いじゃない、太一のことは。
ただ、どうしようもなく、東雲くんに惹かれている。
東雲くんと前のような距離感をなんとか取り戻した私はひとまず安堵していた。
しかし席が遠いというのは本当に話す機会がない。
更に私と東雲くんは理系クラスと文系クラスで授業も違うので、全然話せない日が続く。
……あと、誰かさんのあからさまな悪意を感じている。
「東雲くん、おは」
「彩、コミュ英の予習見せろ」
「……はいはい」
遂に命令形になった。本当に図太い性格をしている。
この間に東雲くんどっか行っちゃうし。
「あの、し」
「次古典」
「……」
こんなことがかれこれ数十回続いた。
書道の時間。
二人で周りを気にせず話せる時間。
なっちゃんや東雲くんを気にせずとも済む時間。
「耐え難いよ……」
「はあ? なんのことだよ」
「知らないふりしないでくれる!?」
あれが全部事故だっていうのか。どう足掻いてもわざとだ。
「なんだよ、俺に予習してこいって?」
「そうだよその通りだよ」
いい加減東雲くんと話したい。数学の質問もしたいし、もっと彼が知りたい。
「はあ、どうして太一の私怨に付き合わされてるんだろ」
筆を置いて紙を取り替える。
その時太一を見るとすごい顔をしていた。
「なにその顔。おもしろ」
「いや……太一って呼んだと思って……」
「自分が呼べって言ったんじゃん。忘れてたなら戻すけど」
「いや! 絶対戻すな。戻すなよ。絶対だからな」
「フリ?」
「ちげーよ」
そんなに言われると戻したくなってしまう、私のサガ。
それにしても、私はだいぶ呼び捨てしていたつもりだったが、本人の前は初めてだったか。
「……なあ」
「ん?」
「やっぱり、俺じゃダメなわけ」
「なにが」
「好きな相手」
「んん!?」
ぎょっとする。太一は机に伏せている。顔は見えない。
「……やっぱり俺彩のこと好きだ」
「……それは、どうも」
そんなに真面目な声で言うから、わからなくなる。騙されるな。相手は太一だ。
嘘だと思い込む。
ほだされてしまいそうで。
「本っ当に悔しいんだけど、俺じゃ東雲の代わりになれないのか」
「東雲くんは東雲くん。太一は太一だよ」
「……そうかよ」
そう言うと太一はいきなり起き上がり、うーんと伸びをした。
「俺も書道やるかー!」
「今そういう時間だからね」
「何書こうかな。俺とお前の相合傘でも書く?」
「小学生なの? 死んでもやめて」
「お前が好きだ!は?」
「あなたが嫌いな東雲くんの席に置いといてあげる」
「やめろ」
「こっちのセリフ」
別に嫌いじゃない、太一のことは。
ただ、どうしようもなく、東雲くんに惹かれている。