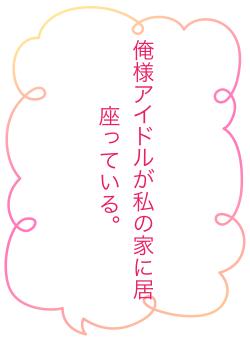悪夢にうなされ目が覚める。
ゆっくり起き上がると、湿ったハンカチが首から落ちた。
机の上には水滴がついているスポーツ飲料が置いてある。多分新品。
ハンカチとスポドリの主を探し周りを見渡すけれど、誰もいない。
とりあえず喉が渇いていたのでスポーツ飲料を頂いた。
甘さと冷たさが体中に染み渡っていく。
時計を見ると一時間程寝ていたようだった。
んー、と伸びをしたとき、勢いよく教室の扉が開いた。
「望月、起きたのか」
「東雲くん」
焦り気味の顔。また初めて見る顔だ。
小走りで私の近くまできて、隣の席に座る。
「大丈夫か? 汗かいてるのに顔真っ青で寝てたから驚いた。とりあえずハンカチ濡らしてかけたんだけど」
「ああ、これ東雲くんが……ありがとう」
本当に心配してくれたらしい。
気分も先ほどよりはだいぶ良くなったので、素直にお礼を言う。
「水分摂った?」
「うん、これ飲んだ」
「そっか、100円」
「えっ」
「嘘」
「いや、そっちじゃない、これも東雲くん?」
「そうだけど」
「うっわごめんそんないろいろしてもらっちゃって待って100円……」
「いや本当にいいから、そんな動くな」
「ぐっ」
財布を取りに行こうと立ち上がったとき、激しいめまいに襲われる。
前傾姿勢で倒れ込んだ私を東雲くんがとっさに抱き留めた。
結果抱きついたみたいになり、私は赤面する。
「……だから言ったろ」
「ごめん」
私を支えながらゆっくりと椅子に座らせてくれた東雲くん。
電車でもこんなことあったな、と余計なことを思い出す。
自分でもわかるほどの顔のほてりをごまかすようにスポドリを呷った。
彼もむず痒い空気感に耐えられなかったのか、眼鏡をカチャリと直す。
盗み見ると耳が少し赤い。
反則レベルの不意打ちに私はさらに動揺して、つい黙り込んでしまった。
静寂。
どういうテンションで接しよう、みたいな迷いがお互いに生じている感じ。
取り急ぎ私は、近頃抱え込んでいた問題について、本人に直接言及することにした。
「東雲くん、聞きたいんだけど」
「……ああ」
「私のこと最近避けてた?」
彼は気まずそうな顔をして、「実は」と話し始める。
どうやら理系クラスは相当タチが悪いらしい。
私と太一の書道中の会話は筒抜けで、しかもあろうことか東雲くんの前で気にも留めずに授業の合間の雑談のネタにされていたようだ。
思わず頭を抱えた。体調不良の頭痛なのか、もうよくわからない。
「俺は何を言われていても平気だけど、望月を巻き込んで悪かった。変なことも聞かれたみたいだし」
「いや、そんな」
そこまで知られているのか。
とりあえず誤解を解こうと思った。
好きじゃない、普通なんて、そう思われたままだったら嫌で。
「私、東雲くんのこと好きだからね」
「……!?」
そんなにぎょっとしなくても。
確かにいきなりだったけれど。
でもこうして直球にいかないと、彼に伝わらない気がした。
「太一に言われたとき、ギャラリーが完全に面白がってて、誤解を生みそうだったから『普通』って言うのが精一杯だったけど、本当に、本当に私東雲くんのことが好きで、」
「太一?」
「え?」
「いや、違う。お前の気持ちはわかったから」
「本当に? わかってる? 私が東雲くん好きってわかってる?」
「わかったって。 そんな好き好き連呼すんな……」
顔を背けられた。でもまた赤い耳が見えている。
つくづく優しい。いつも真顔だと思っていたのに、私のために変化する表情になぜか胸が締め付けられる。
「また、前みたいに話してくれる?」
「望月が、いいなら」
「……っ、ありがとう!」
「なんで泣いてんの」
「泣いてないっ」
「いや、泣いてるし」
本当に泣いていなかった。ただちょっと目から液体があふれ出しただけで。
拭けば、とハンカチを渡してくれる。
……すでに濡れているやつ。
「ありがとう……洗って返すね」
「いいのに」
「これくらい当たり前だよ。しまってくる」
「ああ」
教室を出た瞬間にもわっとした空気が肌にまとわりつく。
蒸し暑さというのは本当に不愉快だ。
トイレの手洗場でハンカチを軽くすすぎよく絞ってから、たまたま持っていたビニール袋に入れカバンの奥にしまった。
教室のドアを開けただけでひんやりとした風を感じる。クーラーとは本当に偉大だ。
東雲くんはスマホをいじっていた。いつも通り。
「どうする、試合見に行く?」
「望月が元気なら行く」
「私は元気」
クラスのグループLINEによるともうすぐ男子のバスケの試合が始まるらしい。
「次男子のバスケだね、行く?」
「春川か?」
「え、なんで?」
「……悪い、変なこと聞いた」
「いい、けど」
なんだろう。気になったけれど、東雲くんがばつの悪そうな顔をしていたので、これ以上の追及は控えておいた。
「行くか」
「うん」
これ持ってけと飲料水を渡されたので、ありがたく受け取った。
ドアを閉め、彼に並んで歩き出す。
誰もいない教室に虚しくクーラーの音が響いた。
ゆっくり起き上がると、湿ったハンカチが首から落ちた。
机の上には水滴がついているスポーツ飲料が置いてある。多分新品。
ハンカチとスポドリの主を探し周りを見渡すけれど、誰もいない。
とりあえず喉が渇いていたのでスポーツ飲料を頂いた。
甘さと冷たさが体中に染み渡っていく。
時計を見ると一時間程寝ていたようだった。
んー、と伸びをしたとき、勢いよく教室の扉が開いた。
「望月、起きたのか」
「東雲くん」
焦り気味の顔。また初めて見る顔だ。
小走りで私の近くまできて、隣の席に座る。
「大丈夫か? 汗かいてるのに顔真っ青で寝てたから驚いた。とりあえずハンカチ濡らしてかけたんだけど」
「ああ、これ東雲くんが……ありがとう」
本当に心配してくれたらしい。
気分も先ほどよりはだいぶ良くなったので、素直にお礼を言う。
「水分摂った?」
「うん、これ飲んだ」
「そっか、100円」
「えっ」
「嘘」
「いや、そっちじゃない、これも東雲くん?」
「そうだけど」
「うっわごめんそんないろいろしてもらっちゃって待って100円……」
「いや本当にいいから、そんな動くな」
「ぐっ」
財布を取りに行こうと立ち上がったとき、激しいめまいに襲われる。
前傾姿勢で倒れ込んだ私を東雲くんがとっさに抱き留めた。
結果抱きついたみたいになり、私は赤面する。
「……だから言ったろ」
「ごめん」
私を支えながらゆっくりと椅子に座らせてくれた東雲くん。
電車でもこんなことあったな、と余計なことを思い出す。
自分でもわかるほどの顔のほてりをごまかすようにスポドリを呷った。
彼もむず痒い空気感に耐えられなかったのか、眼鏡をカチャリと直す。
盗み見ると耳が少し赤い。
反則レベルの不意打ちに私はさらに動揺して、つい黙り込んでしまった。
静寂。
どういうテンションで接しよう、みたいな迷いがお互いに生じている感じ。
取り急ぎ私は、近頃抱え込んでいた問題について、本人に直接言及することにした。
「東雲くん、聞きたいんだけど」
「……ああ」
「私のこと最近避けてた?」
彼は気まずそうな顔をして、「実は」と話し始める。
どうやら理系クラスは相当タチが悪いらしい。
私と太一の書道中の会話は筒抜けで、しかもあろうことか東雲くんの前で気にも留めずに授業の合間の雑談のネタにされていたようだ。
思わず頭を抱えた。体調不良の頭痛なのか、もうよくわからない。
「俺は何を言われていても平気だけど、望月を巻き込んで悪かった。変なことも聞かれたみたいだし」
「いや、そんな」
そこまで知られているのか。
とりあえず誤解を解こうと思った。
好きじゃない、普通なんて、そう思われたままだったら嫌で。
「私、東雲くんのこと好きだからね」
「……!?」
そんなにぎょっとしなくても。
確かにいきなりだったけれど。
でもこうして直球にいかないと、彼に伝わらない気がした。
「太一に言われたとき、ギャラリーが完全に面白がってて、誤解を生みそうだったから『普通』って言うのが精一杯だったけど、本当に、本当に私東雲くんのことが好きで、」
「太一?」
「え?」
「いや、違う。お前の気持ちはわかったから」
「本当に? わかってる? 私が東雲くん好きってわかってる?」
「わかったって。 そんな好き好き連呼すんな……」
顔を背けられた。でもまた赤い耳が見えている。
つくづく優しい。いつも真顔だと思っていたのに、私のために変化する表情になぜか胸が締め付けられる。
「また、前みたいに話してくれる?」
「望月が、いいなら」
「……っ、ありがとう!」
「なんで泣いてんの」
「泣いてないっ」
「いや、泣いてるし」
本当に泣いていなかった。ただちょっと目から液体があふれ出しただけで。
拭けば、とハンカチを渡してくれる。
……すでに濡れているやつ。
「ありがとう……洗って返すね」
「いいのに」
「これくらい当たり前だよ。しまってくる」
「ああ」
教室を出た瞬間にもわっとした空気が肌にまとわりつく。
蒸し暑さというのは本当に不愉快だ。
トイレの手洗場でハンカチを軽くすすぎよく絞ってから、たまたま持っていたビニール袋に入れカバンの奥にしまった。
教室のドアを開けただけでひんやりとした風を感じる。クーラーとは本当に偉大だ。
東雲くんはスマホをいじっていた。いつも通り。
「どうする、試合見に行く?」
「望月が元気なら行く」
「私は元気」
クラスのグループLINEによるともうすぐ男子のバスケの試合が始まるらしい。
「次男子のバスケだね、行く?」
「春川か?」
「え、なんで?」
「……悪い、変なこと聞いた」
「いい、けど」
なんだろう。気になったけれど、東雲くんがばつの悪そうな顔をしていたので、これ以上の追及は控えておいた。
「行くか」
「うん」
これ持ってけと飲料水を渡されたので、ありがたく受け取った。
ドアを閉め、彼に並んで歩き出す。
誰もいない教室に虚しくクーラーの音が響いた。