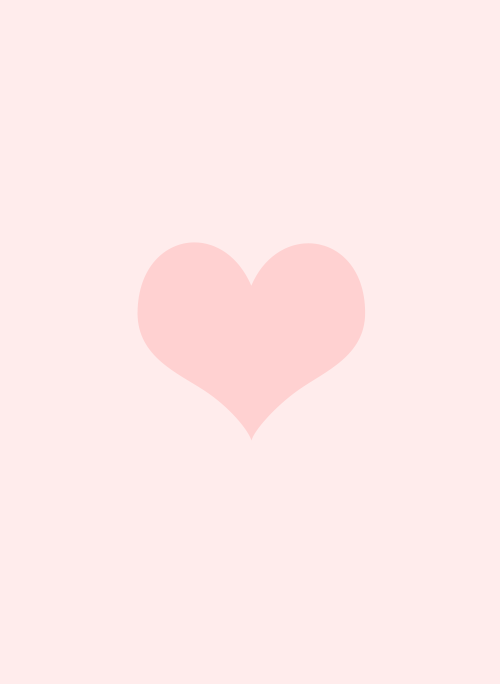「――もう、明日からどんな顔をして行ったらいいんですか……」
マンションのリビングで雫は気の抜けたような声を出す。
あの後、爆弾を落とした張本人は唖然とする面々を尻目に『車で待ってるね』と悠然と微笑んで居室を出て行ってしまった。
その後、やけに興奮した同僚たちからの質問攻めに遭いかけたのだが、関田が
『ねぇ、みんなー。安藤さんを早く返してあげないと、次期社長に恨まれるわよぉ』
と助け船を出してくれたおかげで何とか職場を脱出する事が出来た。
そして彼の車でマンションに帰って来ることになったのだ。
「ごめん、つい言っちゃった」
奏汰は既にスーツからラフなTシャツ姿に着替えている。
反省しているようなセリフと裏腹に、上機嫌で鞄からワインやらチョコレートやら北海道のお土産を出してテーブルに並べている。
『雫はチョコレートを与えると喜ぶ』というイメージがあるようで、何かにつけて彼はチョコレートを買い与えてくる……まあ、実際喜んでいるのだが。
「絶対『つい』じゃないですよね……」
確信犯だ。最近さすがに雫も彼のこういうズルい面がわかるようになってきた。
「それより、しーちゃんは寂しくなかった?全然喜んでくれないから俺ばかり君に会いたかったみたいで」
奏汰はわかっていて話題を変えようとする。
「そ、そんなこと無いですよ。さっきの事で色々吹っ飛んでしまって」
会いたかったに決まってる。奏汰が帰ってこない家にいるのは寂しかったし、出張先から電話を貰うのも、こうして無事な顔を見られるのも嬉しくて仕方がない。
ただ、照れてしまって素直に言えないのだ。
(これじゃあ、可愛げが無い女と思われてしまうよね)
「もうちょっと待って欲しいって言ってたのに……」
そう思いつつも、また可愛く無いことを言ってしまう。
「だって、出張から帰って来て、やっと君に会える!少しでも早く顔を見たいと思って会社に行ったら、会いたかった相手は迂闊にも松岡にデートに誘われてるし」
「え?まさか。デートじゃなんかありませんよ。ただ、PTの人たちと飲みにいこうと誘ってくれただけで」
そういえば、あの後何故か松岡はフリーズしたままだったけど、大丈夫だっただろうか。
すると奏汰は溜息交じりに言う。
「本当に君ってそっち方面に鈍いよね。俺はそれで苦労したんだけど……まぁいいか、俺以外の奴には鈍感なままでいてくれた方が安心だし」
――何が鈍くてしかも呆れたように言われなければならないんだろう。少々心外だ。
だが、それよりも、だ。
「数いる羽野奏汰ファンの反応が怖いです」
雫は不安げに言う。藍美が奏汰の婚約者であるという噂は社長も奏汰も否定したため消えていたのだが
今度は自分が婚約者であるという確定情報が出る事になる。
(やっぱり小物感が否めない……)
もちろんいつかはと覚悟はしていたが。
倉庫に呼び出されて何人かの女性社員に囲まれて『アンタなんて羽野さんに相応しくない』とか『図々しい』とか言われたりするのだろうか。
もしくは、ある事無い事書かれた作成者不明の怪文書が拡散されて貶められたるするのだろうか。ロッカーに入れた荷物がズタボロにされたり……。
眉間に皺を寄せながら考えている雫を見て奏汰は苦笑する。
「何考えてるか想像付くけど、そんなに俺のファンなんていないし、ウチの社員はみんな質が良いから大丈夫。万一少しでも君が嫌な思いをするような事があったら俺があらゆる手を使って何とかするから」
――『あらゆる手』は置いておいても、確かにHanontecの社員は質が良いというのは同感だ。
実はそんなことしそうなレベルの低い社員はいないのかも知れない。
「考えちゃうより、まずはやってみると意外に平気なものだよ――大丈夫」
奏汰はしっかりした口調で言うと、雫の傍らで頭を優しくポンポンとして撫でてくれる。
その後額に口づけされる柔らかい感覚を覚えた。
くすぐったさに顔を上げると、柔らかく笑う彼の整った顔があった。
雫が愛しくてしょうがないという表情だ。
――こういうところがズルいと思う。本当にこの笑顔に雫は弱いのだ。未だに胸が高鳴る。
もう、奏汰が大丈夫というなら大丈夫な気がしてくる。
彼のこういう楽観的な面は考え過ぎてしまう自分をこれまで何度助けてくれただろう。
フッと肩の力が抜ける。
「……そう、ですね」
しばらく考えてから雫は答えた。
「でも、奏汰さんにはかなり強引に前に進まされているような気がします」
「これまでの事?君に逃げられないように、かなり性急に事を進めてる自覚はあるよ」
「ふふ、確かにそうですね。今どこにも逃げ場がなくて困ってるような」
「え、ホントにそう思ってた?」
雫の頬を撫でていた手を止めて奏汰は少し慌てた声を出す。
「いえ、半分冗談です」
「半分かぁ」
「でも、嫌じゃないんです」
自分を変えようと一歩踏み出す事は簡単なようで難しい。
責任感だけはあったが、何かにつけて自信が無く、『アンドロイド』と言われ、人と関わる事も苦手だった雫の手を取り前に進めさせてくれたのは奏汰だった。
出会いは時として良い方にも悪い方にも人を変える。
辛い思いをしたこともあったし、人との関りで悩んだ事もあった。
でも今は、こんなにも幸せだ。奏汰と出会えた自分は本当に運が良かったのだ。
そう言ったらこの激甘な婚約者は『運じゃなくて運命だよ』とまた笑ってくれるのだろうか。
これからの人生、何でも上手く行く訳では無いだろう。でも、困難に直面しても彼が一緒なら乗り越えられる。そんな「確信」がある。
そして、自分も彼にとってそんな存在になれたら――
雫は吹っ切れたような笑顔を奏汰に返す。
「私、奏汰さんと出会えて、好きになれて、幸せです」
「……」
奏汰は目を見開いて雫をしばらく凝視すると、はぁー、と脱力する。
「まったく……君って……」
気付くと奏汰の耳がほんのり赤い。彼は照れると耳が赤くなるのだ。
(あれ、もしかして、私今相当恥ずかしい事を言ってしまったのでは……?)
つられて赤くなった雫を彼は正面から抱きしめ、甘やかに言う。
「俺こそ、俺と出会ってくれてありがとう――」
愛してるよ と。
しばらく、ふわふわした甘い雰囲気で抱きしめ合っていたふたりだったが、急に奏汰が声を上げる。
「あーーダメだ可愛い。早く結婚したい」
抱きしめる力が増した腕の中で雫は困ったように答える。
「結婚式はお義姉さんの出産が終わって落ち着いたらって……」
結婚式は藍美にも必ず出席して欲しいからと雫からお願いした。たった一人の弟の結婚式だ。義姉は出席したいに違いない。
それを聞いた藍美は『雫たんマジ天使!ウチに嫁に来て!』と訳の分からない事を言っていたと奏汰が不満げに教えてくれていた。
「じゃあ、やっぱり先に籍を入れたい」
これも今までふたりの間で何度か出ている話題だ。
すぐにでも籍を入れたいと言う奏汰に対し、
やはり物事には順番があると思っている雫は結婚式と同時期に籍を入れたいと主張していた。
こうして一緒に暮らしていることも本当は順番が違うのだが、そこは置いておくことにする。
婚約までがかなりのハイスピードだったので、焦る事は無いのではないかと思うのだ。
「えっと、籍を入れても入れなくても、私は奏汰さんのモノですよ?」
何となく思ったことが口から出てしまった。
――沈黙
(あれ?)
ギュウギュウと抱きしめられていた腕の力が抜けたと思うと、瞬時に体が浮き上がった。
「ふぁ!?奏汰さん!?」
「ベッド行く」
軽々と雫を抱き上げた奏汰が真剣な顔で短く告げる。
「しーちゃんが俺のモノだって実感させて」
「あ……」
雫は身の危険を感じた。
もしかしたら今日の自分は無意識且つ的確に彼のスイッチを押しまくってしまったのかも知れない。
奏汰は『そういう時』も優しく、決して乱暴な事はしない。しかし、執拗に雫を『いろいろ』翻弄し、恥ずかしがる姿を見て楽しんでいるフシがある……気がする。その時限定でちょっとS寄りなんだろうか。
とにかく後から我に返ると羞恥で死にそうだし、なんというか、体力的にもキツいのだ。
この雰囲気だといつもに増して大変な事になる気しかしない。
「奏汰さん!夕食!ご飯は!?」
雫は一応の抵抗を試みる。
「ベタな言い方で悪いけど、先に君を食べてからでも良い?雫不足で死にそうなんだ」
「えぇえ……」
――夕食は食べられない気がしますけど!?と雫は心の中で叫ぶ。
とは言え、彼に求められる事自体は嬉しくて、抱き上げられた彼の逞しい腕の温度に甘く胸が高まっていることも、結局恥ずかしがりながらも全てを受け入れてしまう事もわかっている。
奏汰は大人しくなった雫を恭しく抱いたまま、今ではふたりの寝室になった奏汰の部屋に消えていった。
ふたりがいなくなり、静まりかえったリビング。
リビングボードの上、サボ丸とサボ平の間に繊細な細工が施された小さなクリスタルのジュエリーケースが置かれている。
その中で、奏汰が雫に贈った婚約指輪が眩く上品に輝いていた。