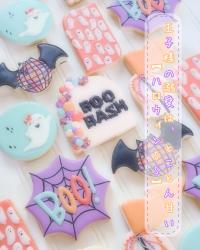「…そんなの、当たり前。芙羽梨だって、僕だけのお姫様…違う?」
「っ…違いません」
首を横にぶんぶん降ると、詩音先輩は柔らかく微笑んで頭を撫でてくれた。
近くで聞こえる波の音も、冷たい風も気にならない。
どちらかが動けば唇に触れてしまいそうな距離は、私の鼓動を早くするのに充分。
先輩の瞳に映る私は、ただ真っ直ぐ詩音先輩だけを見ている。
「…愛してるよ、芙羽梨」
目を閉じると、とろけてしまいそうなほど甘いキスが落ちてきて…。
「私も、愛していますっ…」
いつになったら全部返せるかわからないけど。
あなたに貰った幸せを、必ずいつか返しますから。